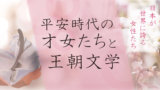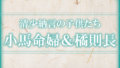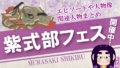紫式部の娘『大弐三位(だいにのさんみ)』。母が源氏物語の作者としてあまりにも有名すぎるので陰に隠れがちですが、娘である大弐三位も実はかなりの才女として知られています。
この記事では、そんな大弐三位の人物像などを見て行きたいと思います。
大弐三位の逸話
大弐三位は、長保元年(999年)頃の生まれとされています。母親は紫式部で、父親は藤原宣孝という人物です。大弐三位が宮仕えを始めのは長和6年(1017年)頃と言われており、母の紫式部と同じく中宮彰子の女房として活躍しました。
なお、紫式部は寛弘8年(1012年)頃まで宮仕えをしていたとされており、大弐三位と紫式部の宮仕え時期はかぶっていません。
大弐三位は、第70代天皇『後冷泉天皇』の乳母を務めたり、藤原兼隆という藤原北家の人物と結婚したりなど高貴な人々と深い関係にありました。つまり、大弐三位は宮廷で華やかな日々を過ごしており、かなり成功した人生と言えるのではないでしょうか。
母の紫式部は「紫式部日記」を読む限り、目立つのが嫌いでどちらかというと引っ込み思案な性格だったと思われるため、母親とは違った人柄だったのかもしれません。
大弐三位は永保2年(1082年)頃に没したと言われており、80歳を超えての大往生でした。
偉大な母を持ち、宮廷での立場も盤石(仕事も安定)、男性貴族たちとの恋愛に花を咲かせ、とても長生きした大弐三位の人生は、まさに順風満帆という言葉がぴったりなのではないでしょうか。
大弐三位の和歌
大弐三位は母の紫式部と同じく歌人として高く評価されているので、大弐三位の代表的な和歌をご紹介します。
有馬山 猪名の笹原 風吹けば いでそよ人を 忘れやはする
(ありまやま ゐなのささはら かぜふけば いでそよひとを わすれやはする)
【現代語】
有馬山から猪名の笹原に風が吹くと、笹が そよそよと鳴る。
そうですよ。私があなたを忘れるもんですか。
この和歌は、百人一首に選出されている大弐三位の和歌です。
意味としては、疎遠になった男性が「僕のことは忘れられてしまったかと思い心配しました」と言ってきたので「忘れるわけないでしょうが!」と返した和歌になります。
この和歌からも伝わってくつ通り、母の紫式部と比べて大弐三位は恋愛の駆け引きも優れ、男性貴族らとも上手くやっていたようです。やはり紫式部の性格は、あまり受け継がなかったようですね。
大弐三位の本名
『大弐三位』というのは、いわゆる女房名で、彼女の本名は『藤原賢子』と言います。『賢子』は、『かたいこ』、『けんし』などと読みますが、『かたいこ』と呼ばれるのが一般的です。
この時代の女房で、本名が分かっているのは非常に珍しいケースで、母の紫式部をはじめ清少納言や和泉式部といった超有名人ですらの本名は正確には伝わっていません。つまり、本名が判明している大弐三位はかなりのレアケースなのです。
紫式部には似なかった大弐三位の性格
ここまでお伝えしてきた通り、大弐三位は母の紫式部とかなり違う性格をしていたように感じます。紫式部日記を見る限り、紫式部はあまり明るい性格ではなかったようなので、大弐三位は真逆の性格だったと言えるのではないでしょうか。
個人的な感覚で大弐三位の性格を例えるなら、清少納言と和泉式部を足して2で割ったような印象です。
母親が偉大過ぎるので、どうしても『紫式部の娘』という印象が付きまといますが、その母の活躍に負けないくらいの輝きを放っていた女性だと思います。
大弐三位まとめ
以上、大弐三位についてでした。大弐三位は恋も仕事も大成功をおさめ、80年を超える生涯に幕を閉じました。清少納言の娘『小馬命婦』、和泉式部の娘『小式部内侍』らも、大弐三位と同時期に宮廷出仕しています。
著名な女性たちの娘が、同時期に同じ場所で働いていたと思うと、なんだか面白いですね。
最後までお読みいただきありがとうございました。
平安時代の女性たちによる王朝文学、そして個性豊かな女性たち、そんな平安時代の文学作品や女性たちに関してたくさん執筆していますので、↓コチラ↓からぜひご覧になってみてください。