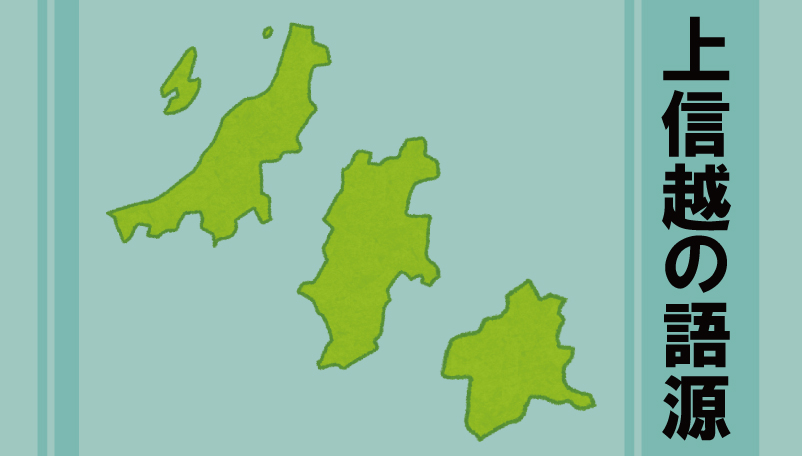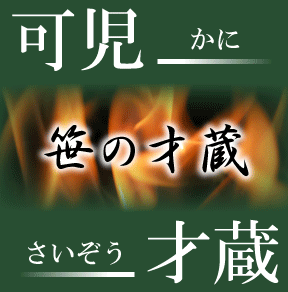時々『上信越(じょうしんえつ)』という言葉を耳にすることがあります。天気予報で『上信越地方』と言ったり、『上信越自動車道』という高速道路があったり。
ところでこの『上信越』とは、一体どのような意味があるのでしょうか?
この『上信越』という言葉の語源を、どこよりも分かりやすく解説いたします。
上信越の意味
群馬県・長野県・新潟県
結論から言ってしまいます。
『上信越』とは、群馬県、長野県、新潟県の総称です。
群馬、長野、新潟は県境が接しているため、この三県をまとめた全域が『上信越地方』になります。
ゆえに、群馬県から出発し、長野県を通過し、新潟県に至る高速道路(あるいは新潟→長野→群馬)を『上信越自動車道』と言うのです。
上・信・越とは何なのか?
ところで、なぜ群馬県、長野県、新潟県をまとめると、『上信越』になるのでしょうか?言葉だけ見ると、なんら共通点が見出せませんが、ここにもきちんとした由来があります。
実は『上信越』という単語は、群馬、長野、新潟の昔の名称(旧国名)に由来しています。
群馬の昔の名称は『上野(こうずけ)』。
長野の昔の名称は『信濃(しなの)』。
新潟の昔の名称は『越後(えちご)』。
上野、信濃、越後、それぞれの頭の文字を合わせて『上信越』です。
明治維新の『廃藩置県』によって、上野、信濃、越後という名称は廃止され、最終的に現在の群馬、長野、新潟という県名に落ち着くのです。
今もよく使われる旧国名
実は、この他にも旧国名の名残は全国各地に残っています。
上信越に関するもので言えば、『上越新幹線』。これは、群馬(上野)と新潟(越後)を結ぶ新幹線です。また、群馬を除き、長野と新潟を総称して『信越地方』と言ったりもします。
あるいは、関東地方に目を向けてみても、旧国名はいろいろなところで使われています。
例えば『房総半島(ぼうそうはんとう)』。これは、千葉県南部の海に突き出た半島部分を指す呼称です。これも旧国名に由来しています。
昔の千葉県は『上総(かずさ)』『下総(しもうさ)』『安房(あわ)』という3つの地域に分かれていました。
この上総・下総の『総』と、安房の『房』を合わせて『房総』です。
あるいは、総武線という路線。これは千葉県と東京を結ぶ路線ですが、やはり旧国名に由来します。
『総』は前述の千葉県、『武』は『武蔵(むさし)』のことで、武蔵とは現在の東京と埼玉あたりを指す旧国名です。
このように旧国名の名残が見えるものは、全国各地にたくさんあります。今回ご紹介したのは、ほんの一握りです。
それぞれの地域に根付いている名称の由来を紐解いてみると、意外な発見がありかもしれませんよ。
まとめ
以上、上信越の由来でした。
- 群馬の昔の名称は『上野(こうずけ)』。
- 長野の昔の名称は『信濃(しなの)』。
- 新潟の昔の名称は『越後(えちご)』。
この三県の旧国名をとって『上信越』と呼ぶのでした。
他にも日本各地の地域名の由来を記事にしていますので、ぜひご覧になってみてください。