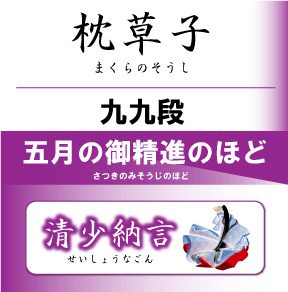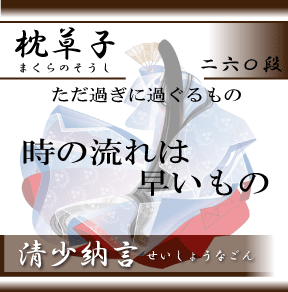平安時代、清少納言が書いた枕草子。
今回ご紹介するのは、九九段『五月の御精進のほど』(さつきのみそうじのほど)
このエピソードは「和歌」が一貫したテーマとなっており、清少納言の和歌に対する考えが伝わってくる、たいへん興味深い章段となっています。
↓なお、非常に長い章段なので、要点をまとめると話の流れはこんか感じ↓
1.ホトトギスを聴きに行って、和歌を詠もうとする
2.事あるごとに目移りし、和歌を詠み忘れる
3.和歌を詠まずに帰ってきて定子の機嫌を損ねる
4.その後も和歌を詠もうとするがドタバタに巻き込まれる
5.そのまま、うやむやになり二日後にぶり返される
6.清少納言の和歌に対するコンプレックスが明かされる
7.意地を張って和歌を詠まない清少納言
8.定子の思いやりある策略に、つい和歌を詠んでしまった清少納言
このようになるのですが、長編章段の為、3回に分けてお送りします。
今回ご紹介するのは、赤字1と2の部分。
ホトトギスの声を聴きに行って和歌を詠もうとしたものの、いろんな事に目移りし、結局和歌を詠まずに帰ってきてしまった清少納言の姿が綴られています。
なお前述の通り、かなり長い章段となります。枕草子原文では、ぶっ通しで展開するのですが、便宜上、場面が変わるところで小見出しを付け、簡単な見どころと解説を追記しておくこととします。
ちなみにこちらの記事では、かなり要点をしぼり現代風にして書いてあります。この章段の内容を簡単に把握したい場合は、こちらの記事をオススメします。
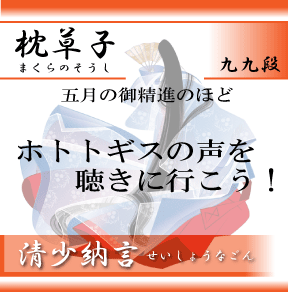
※枕草子の章段には諸説あることをご了承ください。
現代版枕草子 99話その① ~五月の御精進のほど~
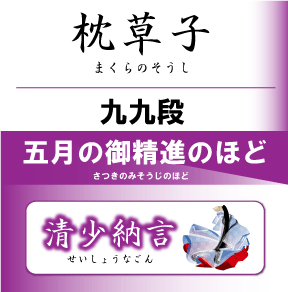
ホトトギスを聴きにお出かけする清少納言
五月の御精進(己の行いを慎み身を清める期間)のころ、中宮(定子)様が職の御曹司(みぞうし)にいらっしゃる時のお話です。
中宮様がいらっしゃるお部屋は、周囲を壁で塗り込めて、御精進のために今の時期だけ仏像などを飾り、仏間になっている。いつもと違う雰囲気が実に面白い!
今月は一日から天気が悪く曇りがち。御精進と月ということもあり、暇なので私(清少納言)は、ひとつの提案をしたのです。
『ホトトギスの声を聴きにいきましょうよ!!』
すると、辺りの女房たちも『私も、私も』とこぞって賛成するので、早速出発することになりました。
賀茂の奥に何々という橋があり、『かささぎの橋』とかいった風情ある名前ではないけれど、その辺りに行けばホトトギスが鳴いていると誰かが言うと、
『それはヒグラシの鳴く声でしょう』
と言う女房もいる。
ともかくも行ってみようということで、五日の朝、役人に牛車を用意していただき、私を含め四人で出かけることになりました。
居残ることになった女房たちは羨ましがって、
『もう一台牛車を用意してください』
などと言っているけれど中宮様が、
『ダメです』
と仰るので、私たちは情け容赦なく出発しました。
途中、馬場(うまば)という所で人が集まって盛り上がっている。
私が『何をしているのですか?』と尋ねると、牛車に従っている男性が、
『これから競射の予行練習が行われるようです。是非ご覧になっていきましょう』
と言って牛車を止めました。
従者の男性は、
『左近の中将様もいらっしゃるようですよ。皆さんもう着席なさっています』
と言っていたが、そのような人の姿は見えず、下級役人がウロウロしているだけなので私は
『あんまり楽しくないですね。ここは見なくても大丈夫』
と言って先を急がせました。
その道中の風情は、賀茂の祭を思い出させ、たいそう風情がある・・・
見どころと解説
この章段はそのタイトルの通り『五月の御精進』期間の出来事が綴られています。
冒頭でも『五月の御精進』のころ、と出てきますがこの『五月の御精進』とは、肉を食べずに自らの行いを慎み身を清める期間です。
現代風に言い換えるなら『御精進期間のお出かけ日記』みたいな感じです。
なお『五月の御精進』の読み方ですが、『サツキノミソウジ』です。『ゴガツノゴショウジン』じゃないので、ご注意ください。
目的地に到着
私たちが目指している場所は『明順の朝臣の家』。
到着した私たちは、
『この家も見物しましょう』
ということで、牛車を降りました。
『明順の朝臣の家』は田舎っぽくて簡単な作り、馬が描いてある衝立の障子に網代の屏風、三稜草(みくり)の簾などで昔っぽく飾り付けてある。建物の雰囲気も、あえて簡素にしてあって狭いのに、たいそう風情を感じる・・・
それにしても、噂通りこの辺りはホトトギスの鳴き声がうるさいほど聞こえてくる。このホトトギスの声を、中宮様にお聞かせ出来ないのは本当に残念。置いてけぼりにした女房たちにも、後ろめたさを感じます。
すると、この家の主 明順(あきのぶ)が、
『このような田舎ですから、こんなのも見て行ってください』
と言って、稲を取り出し、近所の農家の娘を五、六人連れてきて稲の籾を取る作業を見せてくれました。また、二人の娘がクルクル回る挽き臼をひきながら歌を謡っている光景は、実に物珍しく、私たちは、キャーキャー騒ぎながら見物していました。
こんなことしていたら、目的の和歌を詠み忘れてしまいそう・・・
やがて、明順は唐絵が描いてあるような珍しい懸盤(四つ足の食事を乗せる台)でお食事をご馳走してくださいました。
しかし私たちは、食事に目もくれず、そっぽを向いていると明順が、
『お粗末な田舎料理ですが、こういった田舎に来た人は、主人が逃げ出したくなるくらいにおかわりを催促して、お食事を召し上がるのです。全く箸を付けないとは、あなたたちらしくありませんねw』
などと冗談を言う。明順はさらに続けて、
『この下蕨(したわらび、この時出された蕨料理のこと)は私が自ら摘んできたものなんです』
と言って、勧めてきました。
私が、
『でも、こんな下級の女官みたいに並んで食事なんて出来ませんよ』
と言うと、明順は、
『そうでしたね。では懸盤から下して召し上がってください。いつも腹這いの姿勢でいる女房がたですからね』
といって、食事を下におろし、ワイワイ騒いでいると、従者の男性が、
『雲行きが怪しくなってまいりました。雨が降りそうです』
と伝えてきたので、急いで帰り支度を始めました。
その時私は、
『今、ここで和歌を詠んでしまいましょう!』
と言ったのですが、同行していた女房が、
『帰りの道中でも詠めますよ』
と言うので、皆急いで牛車に乗り込みました。
見どころと解説
ここでは、目的地に到着し、無事ホトトギスの鳴き声を聞いて和歌を詠もうとする清少納言の姿が綴られています。
しかし、結局タイミングを逃し、和歌を詠むことなく帰ることになりました。これが、終盤への大きな伏線となってきます。
なお、ここで登場する明順は『高階明順(たかしなのあきのぶ)』という人物で、定子様の母『高階貴子(たかしなのきし)』の兄弟です。
卯の花の垣根になった牛車
帰りの道中、その辺に卯の花が咲き誇っているのを見つけました。私たちは卯の花を折って牛車の簾やその脇、屋根や棟などにも枝を葺いたように挿していったら・・・
牛車が卯の花の垣根のような有様になってしまいました。
これには皆大笑いしながら、
『ここにがまだ足りない、ここも足りない』
などと言いながら、皆で牛車を飾り付けました。
私は、卯の花の垣根になった牛車を誰かに高貴な身分の方に見せて驚かせてやりたいと思ったのですが、そんな時に限って、下級の法師や、一般の人々と時々すれ違うだけで、ちっとも面白くない。
そうこうしている内に、近くまで帰ってきてしまったので私は、
『このまま帰るなんてつまらない!この牛車の有様を誰かに見せつけてやりましょう』
と言って、一条殿に牛車を止めました。※一条殿とは屋敷のこと
見どころと解説
帰りの道中で和歌を詠むはずが、卯の花に目移りしてしまった清少納言の姿が綴られています。
さらには卯の花を牛車に挿して遊んでいたら、牛車が卯の花で埋め尽くされ異様な光景になってしまった・・・そして、彼女のイタズラ心がメラメラと燃え上がり始めます。
おそらく、この時、彼女の頭から和歌のことはすっ飛んでいたことでしょう。
こういった部分から、清少納言の明るくお茶目な性格が窺えます。
この後『五月の御精進のほど』前半最大の見せ場がやってきます!
逃げる牛車!追いかける公信!
一条殿の主は藤原公信。私たちは、
『侍従殿はいらっしゃいますか?ホトトギスの声を聴きに行ってきて今帰るところです』と使いの者を走らせました。※侍従殿とは一条殿の主 藤原公信のこと
やがて使いの者が戻ってきて、
『すぐに伺いますので、少しお待ちください。侍従様は、くつろいでおられたので今大急ぎで着替えております』
とのことでした。
待ちくたびれた私は、車を走らせ土御門へ向うことにしました。
牛車は走りはじめます。すると・・
いつの間にやら着物を着たのか、侍従殿が帯を結びながら追いかけてきたのです!
『お待ちくだされ!お待ちくだされぇぇぇ!』
叫びながら追いかけてくる侍従殿と、その家来3、4人が裸足のまま走ってきます。
この光景に、私は面白くなってしまい、
『もっとスピードを上げでください!!』
と言って、牛車を急がせました。
やがて土御門に到着し、侍従殿とその家来たちも息を切らしながら追いついてきました。
そして、卯の花の垣根になった牛車を見るやいなや、侍従殿はいきなり大笑い!
『正気の人がこの牛車に乗っているとは、到底思えませんねw皆さんも降りて、よくご覧になってくださいw』
と笑いながら言うと、家来たちも一緒になって笑っている。
すると侍従殿が、
『ところで、どんな和歌をお詠みになったのですか?是非お聞かせください』
と言うので、私は、
『それは、後ほど・・まずは中宮様に御覧いただいた後にしましょう』
などと言っていると、いよいよ雨が降ってきました。
『この土御門は何故、他の門のように屋根がないのでしょうか?こんな大雨の時は本当に腹がたちますね』
と侍従殿。さらに続けて、
『これじゃぁ帰れやしない。ここに来る時は無我夢中で人目も気にせず走ってきましたが、この雨の中を帰るとなると、はなはだ面白くありません・・・』
と言うので、私は、
『では、内裏にいらっしゃい』
と言うと、侍従殿は、
『伺うにしても、このような普段用の烏帽子では、それも出来ません』
と仰るので、さらに私は、
『使いの者に取りに行かせましょう』
などと、やりとりしていると、いよいよ雨が本降りになってきました。
すると笠を用意していなかった従者の男性たちが、卯の花の垣根になった牛車を強引に門内に引き入れてしまったのです。
やがて、侍従殿は(一条殿から使いの者が持ってきた)傘をさし、こちらを振り返り振り返り、トボトボと帰っていきました。
その侍従殿が、牛車に挿してあった卯の花を持って帰った行く姿も、投げやりな感じで何となく微笑ましい。
見どころと解説
清少納言のイタズラ心に振り回される藤原公信(侍従)の姿が見どころです。
しかし、清少納言の悪ふざけは少しやりすぎでは・・?という気もします。
ところが、作中にもある通り、藤原公信は怒ることはせず、卯の花の垣根になった牛車を見て一緒になって笑っています。
決して後味の悪い話にはなっていないのです。こういった部分が、枕草子の明るさであり、華やかさなのです。
また、雨の中トボトボ帰る公信の姿も、ちょっと哀愁が漂う感じがして面白いですね。
『五月の御精進のほど』前半のまとめ
以上が『五月の御精進のほど』の前半部分です。
結局、和歌を詠まずに帰ってきた清少納言。この後も面白い話が続きます。
前半のポイントは三つ。
・和歌を詠まなかった清少納言
・明順がご馳走してくれた蕨料理
・公信が持ち帰った卯の花
この3点が再度登場しますので、ちょっと覚えておくとこの後の話が理解しやすくなります。
もっと枕草子の世界を覗いてみたい方は、こちらからお好みの記事をご覧ください。

原文はこの後です。
【原文】 枕草子 九九段『五月の御精進のほど』
五月の御精進のほど、職におはします頃、塗籠の前の二間なる所を、ことにしつらひたれば、例様ならぬもをかし。
朔日より雨がちに曇り過ぐす。
つれづれなるを、「郭公の声、尋ねに行かばや」と言ふを、我も我もと出で立つ。
賀茂の奥に、なにさきとかや、たなばたの渡る橋にはあらで、にくき名ぞ聞えし、そのわたりになむ、郭公鳴くと、人の言えば、「それはひぐらしななり」と言ふ人もあり。
そこへとて、五日の朝に、宮司に車の案内言ひて、北の陣より、五月雨はとがめなきものぞ、とて、さし寄せて、四人ばかり乗りて行く。
羨ましがりて、「なほ今一つして、同じくは」など言へど、「まな」とおほせらるれば、聞き入れず、情けなきさまにて行くに、馬場といふ所にて、人多くて騒ぐ。
「何するぞ」と問へば、「手つがひにてま弓射るなり。しばし御覧じておはしませ」とて、車とどめたり。
「左近の中将、皆着きたまふ」と言へど、さる人も見えず、六位など、立ちさまよへば、「ゆかしからぬことぞ。早く過ぎよ」と言ひて、行きもて行く。
道も祭のころ思ひいでられて、をかし。
かくいふ所は明順の朝臣の家なりけり。
「そこも、いざ見む」と言ひて、車寄せて降りぬ。
田舎だち、ことそぎて、馬の絵描きたる障子、網代屏風、三稜草の簾など、ことさらに昔のことをうつしたり。
屋のさまも、はかなだち、廊めきて、端近にあさはかなれど、をかしきに、げにぞ、かしかましと思ふばかりに鳴きあひたる郭公の声を、くちをしう御前にきこしめしさせず、さばかりしたひつる人びとを、と思ふ。
「所につけては、かかることをなむ見るべき」とて、稲と言ふ物を取り出でて、若き下衆どものきたなげならぬ、そのわたりの家の娘など、率ゐて来て、五、六人してこかせ、また見も知らぬくるべく物、二人して引かせて、歌歌はせなどするを、珍しくて笑ふに、郭公の歌詠まむとしつる、まぎれぬべし。
唐絵に描きたる懸盤して、もの食はせたるを、見入るる人みなければ、家のあるじ、「いとわろくひなびたり。かかる所に来ぬる人は、ようせずは、あるじ逃げぬばかりなど、責め出してこそまゐゐべけれ。むげにかくては、その人ならず」など言ひて、とりはやし、「この下蕨は、手づから摘みつる」など言へば、「いかがでか、さ、女官などのやうに着き並みてはあらむ」など笑へば、「さらば、取りおろして。例の這い臥しにならはせたまへる御前たちなれば」とて、まかなひ騒ぐほどに、「雨降りぬべし」と言へば、急ぎて車に乗るに、「さて、この歌はここにてこそ詠まめ」など言へば、「さはれ、道にても」など言ひて、皆乗りぬ。
卯の花いみじう咲きたるを折りて、車の簾、かたはらなどにさしあまりて、おそひ、棟などに、長き枝を葺きたるやうにさしたれば、ただ卯の花の垣根を牛にかけたるとぞ見ゆる。
供なるをのこどもも、いみじう笑ひつつ、「ここまだし、ここまだし」と、さしあへり。
人もあはなむ、と思ふに、さらに怪しき法師、下衆の言ふかひなきのみ、たまさかに見ゆるに、いとくちをしくて、近く来ぬれど、「いとかくてやまむやは。この車の有様を語らせてこそやまめ」とて、一条殿のほどに止めて、「侍従殿やおはします。郭公の声聞きて、今なむ帰る」と言はせたる使、「ただ今まゐる。しばし。あが君、となむのたまへる。さぶらひにまひろげておはしつる、急ぎ立ちて、指貫たてまつりつ」と言ふ。
待つべきにもあらず、とて、走らせ土御門ざまへやるに、いつの間にか装束きつらむ、帯は道のままに結ひて、「しばし、しばし」と追ひ来る供に、侍三、四人ばかり、物も履かで走るめり。
「とくやれ」と、いとど急がして土御門に行き着きぬるにぞ、あへぎまどひておはして、この車のさまをいみじう笑ひ給ふ。「うつつの人の乗りたるとなむ、さらに見えぬ。なほおりて見よ」など笑ひ給へば、供に走りつる人どもも興じ笑ふ。
「歌はいかが。それ聞かむ」と、のたまへば、「今、御前に御覧ぜさせて後こそ」など言ふほどに、雨まことに降りぬ。
「などか、異聞門御門にやうにもあらず、この土御門しも、かう上もなくしそめけむと、今日こそいとにくけれ」など言ひて、「いかで帰らむとすらむ。こなたざまは、ただ遅れじと思ひつるに人目も知らず走られつるを、奥行かむことこそ、いとすさまじけれ」と、のたまへば、「いざ、たまへかし、内裏へ」と言ふ。
「それも、烏帽子にてはいかでか」「取にやりたまへかし」など言ふに、まめやかに降れば、笠もなきをのこども、ただ引きに引き入れつ。一条殿より笠持て来るをささせて、うち見返りつつ、こたみはゆるゆるともの憂げにて、卯の花ばかりを取りておはするも、をかし。
※読みやすさを考慮し、適宜改行しています。
枕草子を原文と現代語で手軽に楽しみたい方にはコチラがおススメです。
では、今回はこの辺で!ありがとうございました。