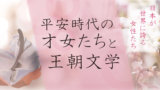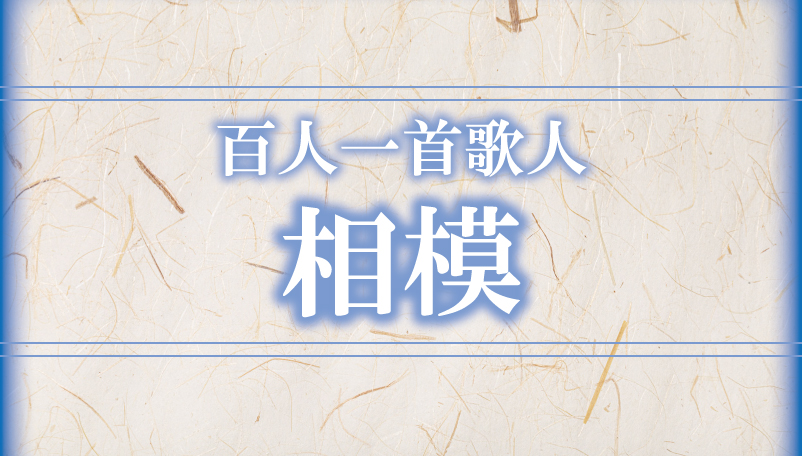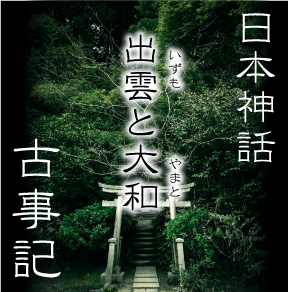平安時代の中期には、百人一首に選出された有名歌人がたくさんいます。
紫式部や清少納言、赤染衛門や和泉式部あたりは、その代表格です。
そんな女流歌人の中に『相模(さがみ)』という女性がおり、彼女の和歌も百人一首に選ばれています。
この相模という女性は一体何者なのか?そして、その和歌の意味とは?さらには、あの有名人との意外な関係とは?
この記事では、百人一首歌人相模についてご紹介します。
百人一首に選ばれた相模の和歌
恨み詫びほさぬ袖たにある物を 恋に朽ちなん名こそおしけれ
(うらみわび ほさぬそでだに あるものを こいにくちなん なこそおしけれ)
【意味】
恨む気力が無くなって、泣きすぎて涙が乾かない着物の袖がボロボロになるのさえ惜しいのに、恋の話で悪い噂が立ち、私の評判も朽ちていくのが本当に惜しいのです。
これは、百人一首に選出された相模の和歌です。
失恋した相模が、自身に妙な噂が立つことを口惜しく思って読んだ和歌です。
相模は和歌の名人としても知られており、和歌名人の女房36人の総称である『女房三十六歌仙(にょうぼうさんじゅうろっかせん)』の一人に数えられています。
『後拾遺和歌集』という歌集に掲載されている和歌も、和泉式部に次いで2番目の多さとなっています。
このことからも、相模が和歌の達人であったことが察せられますね。
『相模』という名前について
次は『相模』という不思議な名前について解説します。
『相模』とは、いわゆる女房名と呼ばれるものです。
相模に限らず、この時代の名前の残っている女性は、ほとんど本名ではありません。
皇后などのかなり高い身分でなければ、本名が分からないのが普通なのです。
そして、『相模』とは神奈川県のことです。
神奈川県の昔の名称は『相模国(さがみのくに)』なので、そこから取られた名前です。
相模の夫『大江公資(おおえのきんすけ)』が、相模国の統治を任されていたため『相模守(さがみのかみ)』という役職名を持っていました。
この夫の役職名(受領名)の『相模守』から拝借した名前が『相模』なのです。
女房名は、夫や父親などの役職名が元になっているものが多く、例えば和泉式部の『和泉』も夫が和泉守だったことに由来しています。
ちなみに大江公資との夫婦仲はあまり良くなかったようで、相模は『藤原定頼』という貴族と恋仲になったりしています。
この藤原定頼ですが、和泉式部の娘『小式部内侍』との間にちょっと情けない逸話が残っているので、興味のある方はコチラの記事もご覧になってみてください。

清少納言との意外な関係
前述の通り、相模の夫は『大江公資』です。
ただし、大江公資は相模にとっては2番目の夫。
大江公資と結婚する前に、ある一人の男性と夫婦の関係があったと言われています。
その男性が『橘則長(たちばなののりなが)』という人物。
則長の父親は『橘則光』、そして母親は枕草子の作者『清少納言』です。
つまり、相模は清少納言の息子と夫婦関係だったということです。
相模についてのまとめ
以上、百人一首歌人『相模』についてでした。
清少納言の息子(橘則長)とも一時期夫婦関係にあったことなどからもわかる通り、相模は清少納言や紫式部、和泉式部といった有名人の娘たちと同世代になります。
紫式部や和泉式部も和歌の名人ですので、彼女らの後を担う有望な女房だったのかもしれませんね。
平安時代の女性たちによる王朝文学、そして個性豊かな女性たち、そんな平安時代の文学作品や女性たちに関してたくさん執筆していますので、↓コチラ↓からぜひご覧になってみてください。