ご来訪ありがとうございます。
『清少納言に恋した男』拓麻呂でございます。
清少納言の随筆集 枕草子に登場する中宮『藤原定子(ふじわらのていし)』。

一条天皇のお后様として、藤原家から嫁いだ女性です。
この定子様の事を知っていると、枕草子を読む楽しさは何倍にも広がります。
平安時代中期、この定子に仕えていた女性の一人が、枕草子の作者である清少納言。枕草子の中には、定子を中心とした王朝サロンの華やかな日常生活が数多く書き記されています。
枕草子を読んでいると、ユーモア溢れる定子様を中心とした女性たちの笑い声が聞こえてきます。
今回は、清少納言が仕えた中宮定子様の人物像と、彼女たちが築いた華やかな王朝サロンを見ていきましょう。
~清少納言も認めた絶世の美女!!藤原定子~

藤原氏の娘『中宮定子』
まずは、定子様の家系について。
定子様は藤原家のご出身です。藤原と言えば、摂関政治で有名な『藤原道長』が思い浮かぶ方も多いでしょう。定子様の父親は道長の兄である『藤原道隆』という人物になります。
そして、定子様には『伊周(これちか)』、『隆家(たかいえ)』という兄弟がいました。特に伊周様は枕草子にも度々登場する人物なので要チェックです。
そして、定子様が嫁いだ帝(みかど)が一条天皇。なおこの一条天皇は後に『彰子(しょうし)』という女性も妻に迎えることとなります。この彰子様は藤原道長の娘です。
なお枕草子現代語訳では、定子様のことを『中宮』と呼んでいます(原文では『宮』)。中宮とは天皇の奥様のこと。なので定子様のことを『中宮定子』と言ったりすることもあります。
この中宮定子様に、女房としてお仕えした女性が清少納言。女房とは、天皇のお后様の身の回りのお世話や、話し相手をする女性たちの総称です。
余談ながら、清少納言が中宮定子様に仕えたわずかな期間の出来事が記されているのが、枕草子という世界最古の女流随筆集です。

絶世の美女!中宮定子様
枕草子の記述によると、定子様は相当お美しい方だったようです。

その美しさは清少納言が絶賛しています。彼女は『この世にこんなにも美しい人がいるのかっ!!』と思ったそうです。
また、平安時代の装束として、宮廷の女性は『十二単(じゅうにひとえ)』を着用しています。その名称の通り、着物を何枚も重ねて着ているので体のラインが分かりづらい、そのため当時の人々は、『手』や『首すじ』など十二単からわずかに見える体のパーツに女性の魅力を見出していたと言われています。
実際、枕草子にも十二単からのぞく、定子様の手に魅了される清少納言の感情が記されています。
お互いを認め合う定子様と清少納言
そんな美貌を持った定子様ですが、意外とユーモアのセンスもあったようで、時折ダジャレを言ったりしています。
また清少納言とは、お互いを認め合う相思相愛な関係だったようです。定子様、清少納言は共に博識で、漢詩に精通していました。
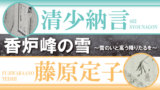
枕草子には、そんな定子様と清少納言の漢詩を通じた絶妙なやり取りが多く書き残され、また共に働く女房仲間たちがそれを絶賛するような、華やかで楽しかった宮廷生活の日常が描き出されています。
清少納言のいたずらで笑い転げる女房たちに呆れる定子様・・
詩を詠まない清少納言と詩を詠ませようとする定子様の根比べ・・
泣きそうなほど緊張していた清少納言に優しく語り掛ける定子様・・
機転を利かせた清少納言にご満悦な定子様と感心する女房たち・・
珍しい楽器をいじくり回している女房たちにダジャレで応える定子様・・
定子様に一番気に入られたい清少納言の感情・・・・・
いつも華やかで楽しかった宮廷生活。その中心には常に中宮定子様の美しいお姿。そして、そんな定子様に、強い憧れと尊敬の念を抱いた清少納言の姿がありました。
今なお輝く定子様の美しき面影
そんな華やかな女性たちの王朝サロンに逆風が吹き始めます。権力を欲する藤原道長が娘の彰子様を一条天皇に嫁がせたことで、定子様や清少納言はじわじわと宮廷の中心から追いやられていくのです。
清少納言は藤原道長と通じているのではないかと疑われます。そして定子様は出産がきっかけで、失意の内にこの世を去ります。
享年わずか二十四・・・あまりにも短い人生でした。
ところが、一条天皇は定子様が旅立たれた後も、彼女の事を忘れられず、残された彰子様は一条天皇の気を引こうと大変な努力をなさったと言われています。父である道長の権力欲に利用された彰子様も、天皇のお后様として・・・いや、一人の女性として一条天皇に愛されようと精一杯の努力をしました。
道長の策謀で追い詰められ失意の内に旅立たれた定子様。しかし、その短い人生は『華やかな王朝サロン』という一瞬の輝きを見せました。

後世に平安時代の宮廷生活を想像させてくれる中宮定子様は、清少納言だけでなく現代人にとっても美しき憧れの女性として、今なお輝き続けています。
~平安時代(中期)の醍醐味とは~
平安時代と言うと貴族たちの優雅な生活を連想する方も多いのではないでしょうか?
主観ですが、これは定子様と清少納言を中心とする女房たちが築き上げた、王朝サロンのイメージが少なからず影響しているように感じます。

このような清少納言や紫式部といった才女が所属した王朝サロンが出現し、国風文化と言う日本らしい文化を形成できたことは、平安時代中期がいかに平和であったかを想像させます。(なお平安前期は蝦夷征討や将門の乱、後期は保元・平治の乱、源平合戦があり結構荒れています。平安時代は400年くらいあって非常に長いです)
この平和こそが平安中期の最大の特徴であり、魅力でもあります。平安中期が平和であるからこそ形作られた文化や暮らしに着目することで、荒々しい時代では発見できない日本の姿が見えてくるのです。
日本史は戦国時代や幕末と言った荒々しい時代に人気が集中しています。しかしながら、こういった平和な時代でしか味わえない日本を探究することも、歴史の醍醐味ではないでしょうか。
もっと枕草子の世界を覗いてみたい方は、こちらからお好みの記事をご覧ください。

では今回はこの辺で!ありがとうございました。







