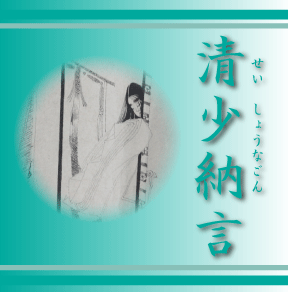春はあけぼので有名な清少納言の枕草子。
その始まりは『春はあけぼの』、とても有名な冒頭部分ですよね。
春は曙。やうやう白くなりゆく、山ぎはすこし明かりて、紫だちたる雲のほそくたなびきたる
ところでこの冒頭部分の後に、清少納言は夏、秋・冬と趣ある情景を綴っていくのですが、その内容はどうなっているのかご存じでしょうか?
意外と知られていない『春はあけぼの』の秋の情景を見て行くことにしましょう。
秋は夕暮れ
では早速、秋はどうなっているのか見ていきましょう。まずは枕草子の原文から。
秋は夕暮れ。夕日のさして、山の端いと近こうなりたるに、烏の寝どころへ行くとて、三つ四つ二つなど、飛び急ぐさへ、あはれなり。まいて、雁などのつらねたるが、いと小さく見ゆるは、いとをかし。日入り果てて、風の音、虫の音など、はた、言ふべきにあらず
原文の最初にもある通り、清少納言は秋は夕暮れに趣を感じています。では、秋の夕暮れはどのように趣があるのでしょうか?現代の言葉に置き換えて内容を見てみましょう。

秋の夕暮れが素敵です。
遠くに見える山の稜線に日が沈みかけていて、夕日に染まった空を飛ぶのは、寝床に帰るカラスの姿、実に趣がありますね。
空を飛ぶ雁(かり)の群れが小さくなっていくのも、また趣があります。
日が沈み、風の音や虫の音が聞こえるのも良いですね。
清少納言は、以上のように『秋の夕暮れ』に趣を感じています。
現代でも、秋の夕暮れには何となく切ない雰囲気を感じますよね。
夕日が沈みかけ、辺りがオレンジ色に染まる中、カラスの鳴き声が聞こえる風景。車のエンジン音などの人工音が無かった平安時代は、現代よりもずっと趣を感じられてのかもしれませんね。
これが清少納言の感じた秋の素敵なワンシーンなのでした。
清少納言の着眼点
以上が、枕草子の『秋』の情景です。
一般的に四季の情景を感じるのは、『春は桜』、『夏は海』、『秋は紅葉』、『冬は雪』・・・こんな感じではないでしょうか。
しかし清少納言は違いました。『春は明け方』、『夏は夜』、『秋は夕暮れ』、『冬は寒い日』といったように、彼女独特の感性で四季の情景を切り取っています。
それぞれの季節が見せる一瞬の情景に四季の風情を見出す。
こういった独特の着眼点が、枕草子の面白さであり、清少納言の豊かな感受性なのかなと感じますね。
最後までお読みいただきありがとうございました。
↓さらにしっかりとした学びを手に入れたいあなたには、コチラがおすすめ↓
古文も日本史も学べる!中学生&高校生向け!通い放題、時間制限なしで勉強し放題の学習塾が登場。
①いつでもリアルタイム質問可能
②オンラインだから自宅で勉強可能
③どんなに利用しても定額制
↓詳しくはコチラ↓
【参考にした主な書籍】
【初めての枕草子はコチラがおすすめ】