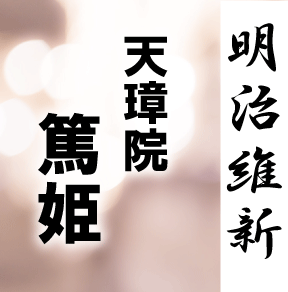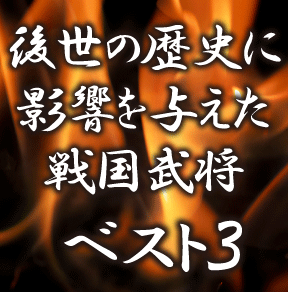『春はあけぼの』で有名な清少納言の枕草子。
その始まりは、『春はあけぼの』から始まる、清少納言が感じた趣ある春の情景から筆を起こしています。
春は曙。やうやう白くなりゆく、山ぎはすこし明かりて、紫だちたる雲のほそくたなびきたる
有名な枕草子の冒頭部分ですね。
この後に、清少納言は夏の趣ある情景を綴っていくのですが、その内容はどうなっているのでしょうか?意外と知られていない『春はあけぼの』の次に書かれた夏の情景を見て行くことにしましょう。
『枕草子』夏の情景
清少納言が趣を感じた春の情景が『春はあけぼの』。これは『春の明け方は趣がある』という意味です。
では、夏はどうなっているのでしょうか。枕草子の原文を見てみましょう。
夏は夜。月のころはさらなり、闇もなほ、蛍の多く飛びちがいたる。また、ただ一つ二つなど、ほのかにうち光て行くも、をかし。雨など降るも、をかし
清少納言は春の明け方に趣を感じましたが、夏は夜に趣を感じました。では、夏の夜はどのように趣があるのでしょうか?現代風に意訳した内容を見てみましょう。

夏は夜が趣がある。
月が浮かぶ夜は当然風情がある。
しかし、月明かりもなく闇に閉ざされた夜も良い。
漆黒の闇に見えるのは飛び交う蛍の光。
沢山飛び交っている光も良いし、一匹、二匹だけの光も趣がある。
雨など降っている時も、また風情がある。
このように『夏の夜』に趣を感じています。
月明かりに照らされる夜の情景。月明かりが無くとも、目の前に飛び交う蛍の光。雨音が聞こえてくる、ちょっと蒸し暑い夏の夜。
電気なんて無かった平安時代の夜には、とっても幻想的な夜だったに違いありません。
これが清少納言の感じた夏の趣あるワンシーンなのでした。
秋と冬は?
なお、この後に秋と冬の情景が書かれています。春、夏、秋、冬の四季の情景を綴ったものをひっくるめて、枕草子一段になります。
せっかくなので秋と冬の情景も見てみましょう。まずは秋の原文から。
秋は夕暮れ。夕日のさして、山の端いと近こうなりたるに、烏の寝どころへ行くとて、三つ四つ二つなど、飛び急ぐさへ、あはれなり。まいて、雁などのつらねたるが、いと小さく見ゆるは、いとをかし。日入り果てて、風の音、虫の音など、はた、言ふべきにあらず
以下、現代語です。

秋は夕暮れが趣がある。
遠くに見える山の稜線に日が沈みかけている。
夕日に染まった空を飛ぶのは、寝床に帰る烏の姿。
実に趣がある。
空を飛ぶ雁(かり)の群れが小さくなっていくのも、また趣がある。
日が沈み、風の音や虫の鳴き声が聞こえるのも良い。
続いて冬の情景。
冬はつとめて。雪の降りたるは、言ふべきにもあらず、霜のいと白きも、またさらでも、いと寒きに、火など急ぎおこして、炭持てわたるも、いとつきづきし。昼になりて、ぬるくゆるびもていけば、炭櫃火桶の火も白き灰がちになりて、わろし
冬の現代語です。

冬は早朝が趣がある。
雪の降る日はもちろん風情がある。
白い霜が降りている日ももちろんのこと。
とっても寒い日の朝。
火を起こすため、大急ぎで炭を運んでいる光景も趣がある。
でも、昼間になって燃え尽きた白い炭がほったらかしになっているのは、ちょっとだらしない。
なお、秋と冬に関しての詳しい解説もしていますので、以下からご覧になってみてください。


清少納言の着眼点
以上が、枕草子の『夏(秋、冬)』の情景です。
一般的に四季の情景を感じるのは、『春は桜』、『夏は海』、『秋は紅葉』、『冬は雪』・・・こんな感じではないでしょうか。
しかし清少納言は違いました。
それぞれの季節が見せる一瞬の情景に四季の風情を見出す。
こういった独特の着眼点が、枕草子の面白さであり、清少納言の豊かな感受性なのかなと感じますね。
↓さらにしっかりとした学びを手に入れたいあなたには、コチラがおすすめ↓
古文も日本史も学べる!中学生&高校生向け!通い放題、時間制限なしで勉強し放題の学習塾が登場。
①いつでもリアルタイム質問可能
②オンラインだから自宅で勉強可能
③どんなに利用しても定額制
↓詳しくはコチラ↓
【参考にした主な書籍】
【初めての枕草子はコチラがおすすめ】