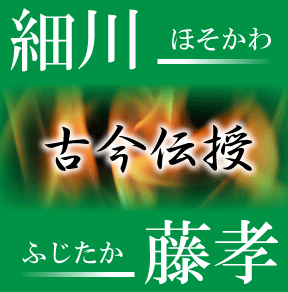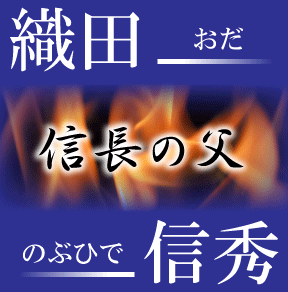ご来訪ありがとうございます。
拓麻呂です。
細川藤孝という武将をご存知でしょうか?
後年は出家して『細川幽斎(ほそかわ ゆうさい)』と名乗っていたので、コチラの名前の方が有名かもしれません。
明智光秀らとも交流があった武将として名前が残る一方、戦国時代随一の文化人としても知られる細川藤孝。
そんな藤孝の特別な能力や人物像、そして明智光秀との関係などをお伝えしていきます。
古今伝授の名将!細川藤孝
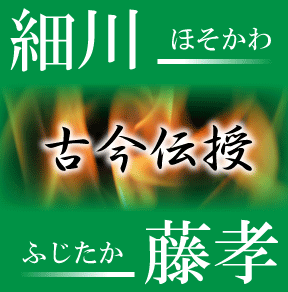
古今伝授とは?
細川藤孝を語る上で、まず抑えておきたいことがあります。
それは『古今伝授』という言葉です。
古今伝授とは、平安時代に編纂された和歌集『古今和歌集』の中身を理解し、和歌の内容や解釈を人に伝えることを言います。
この古今伝授を極めた男が細川藤孝です。
つまり、藤孝は『歩く古今和歌集』とでも言うような文化人だったわけです。
藤孝の教養深さは古今伝授だけに留まらず、古典文学の読み解きにも大きな足跡を残しました。
その中でも藤孝の代表作とされているのが『闕疑抄(けつぎしょう)』です。
闕疑抄は、平安時代初期に書かれた『伊勢物語』を読み解き、解釈を整理した書物で、現在の伊勢物語研究における史料の決定版と言われています。
また、紫式部の源氏物語にも嗜みがあり、写本を残しています。
細川藤孝は、戦国武将である一方で、後世に名を遺すほど和歌や古典文学に精通した文化人でもあったのです。
朝廷にも惜しまれた細川藤孝
そんな藤孝が、いかに凄い文化人であったかを示すエピソードが残っています。
徳川家康と石田三成(総大将は毛利輝元)が激突した『関ヶ原の戦い』。
この時、藤孝は東軍に属し、徳川家康に味方していました。
藤孝は田辺城に籠城していましたが、敵である西軍の大軍勢に包囲されました。
このままでは田辺城は落城、城主である藤孝は討死するか、あるいは捕らえられて切腹となってしまいます。
つまり、古今伝授の担い手である藤孝を失うことで、文化の伝統が絶える可能性があります。
この大ピンチに朝廷が動きました。
時の天皇である『後陽成天皇(ごようぜいてんのう)』の勅命(ちょくめい)により、西軍は田辺城の包囲を解除することになりました。
『勅命』とは、天皇が直々に下す命令のことです。
古今伝授の断絶を憂いた天皇の命令により、藤孝は救われました。
藤孝は朝廷を動かすほどの文化人であり、その名が世に轟いていたことの証です。
天皇にもその能力を惜しまれる武将。
それが、細川藤孝なのです。
明智光秀との関係
このように文化人としての能力に優れた藤孝ですが、武人としても名を残しています。
最も藤孝と関りが深かった戦国武将と言えば、やはり『明智光秀』です。
藤孝はもともと足利将軍家の家臣です。
後に15代将軍となる足利義昭を擁立するために、織田信長を頼りますが、その際に明智光秀と出会い親交を深めていきました。
明智光秀が本能寺の変を起こした際に、最も頼りにしていたのが藤孝でした。
光秀の娘である『玉』は、藤孝の嫡男『忠興』に嫁いでおり、明智家と細川家は親戚関係にありました。
この『玉』が、後の『細川ガラシャ』です。
また、藤孝と光秀は多くの合戦でも共闘し、苦楽を共にした間柄でした。
このような関係から、光秀としては藤孝は味方してくれるだろうと計算していました。
しかし、藤孝は光秀に味方しませんでした。
これは、もともと藤孝の方が光秀より立場が上だったので、光秀の配下になることを嫌ったためだと言われています。
この時に藤孝は出家し『幽斎(ゆうさい)』を名乗りました。
その後、天下人となる秀吉にも重用されることになります。
この藤孝の判断をどう捉えるかは難かしいところですが、ともかくも、藤孝のしたたかさが垣間見える逸話ではないでしょうか。
一見すると裏切り者のようにも感じますが、見方を変えれば時局の判断に優れた武将と捉えることも出来るのではないかと思います。
まとめ
以上、細川藤孝の逸話や人物像でした。
藤孝は文化人でもありましたが、基本的には戦国武将です。
もし、藤孝が公家あたりに生まれていたら、文化人としてもっと活躍して有名になっていたかもしれません。
戦国武将でありながら、文化人でもあり、そして時局を見るしたたかさも併せ持った細川藤孝。
戦国武将多しと言えども、ここまで多芸な人物は少ないのではないかと思います。
他の戦国武将の家臣団に関して知りたい方は、コチラをご覧ください。

戦国武将個人を記事にしたまとめはコチラ。
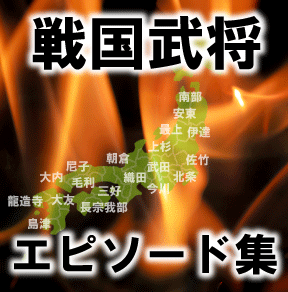
戦国武将を様々な角度でランキングにしてみた記事はコチラ。
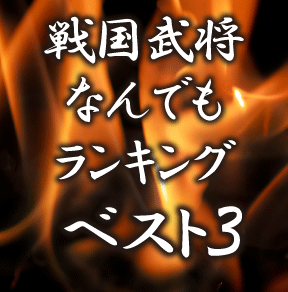
では、今回はこの辺で!
ありがとうございました。