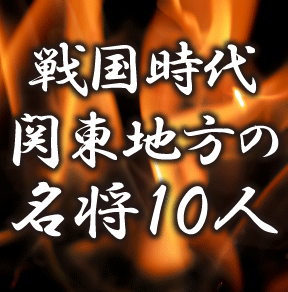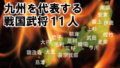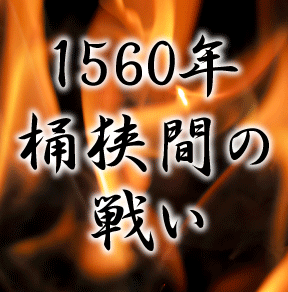ご来訪ありがとうございます。
拓麻呂です。
多くの戦国武将が活躍し、日本の歴史の中でも人気の高い戦国時代。
全国各地で名将と呼べる人物が登場した、特異な時代でもあります。
そんな戦国時代の『関東』で活躍した名将10人を選んでみました。
なお、戦国時代の範囲には諸説あるため、今回は明応2年(1493年)~慶長20年(1615年)の間に生存していた人物に限らせていただきます。(この範囲に1年でも被っていればOK)
順番は50音順とします。
戦国武将ランキング!関東編
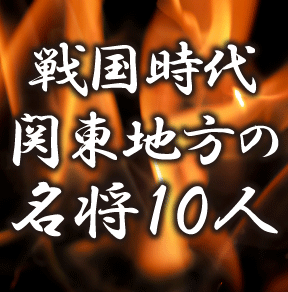
足利成氏(あしかが しげうじ)
永享10年(1438年)~明応6年(1497年)
足利将軍家の一族で、関東地方の統治を委任されていた鎌倉公方(かまくらくぼう)『持氏(もちうじ)』の四男。
関東管領の上杉憲忠と争い、憲忠を倒すも、上杉家の訴えによっ室町幕府が動き、成氏討伐軍を差し向けました。
これにより、成氏は鎌倉を追われ、現在の茨城県古河市へと拠点を移し、古河公方(こがくぼう)と称されるようになりました。
以降も、成氏の古河公方と、関東管領上杉氏争いは続き、関東を二分する大乱となりました。
これを『享徳の乱(きょうとくのらん)』と言い、京都で勃発した応仁の乱に先立ち、関東地方は戦国時代へと突入していきました。
関東が戦国時代へと突入する契機をもたらした中心人物であり、関東戦国時代の幕開けを語る上では、絶対に外せない人物です。
太田資正(おおた すけまさ)
大永2年(1522年)~天正19年(1591年)
現在の埼玉県さいたま市出身の武将。
名門 扇谷上杉氏(おおぎがやつうえすぎし)として、川越夜戦に参戦するも、主君の上杉朝定(おおぎがやつ うえすぎ ともさだ)が討死。
以降、扇谷上杉氏は一気に没落してきましたが、それでも北条氏に抵抗し続けました。
しかしながら、抗し切れず一時、北条に恭順していましたが、越後の上杉謙信と北条氏康の戦いが本格化すると、好機とばかりに再び打倒北条を掲げ『国府台の戦い(第二次)』に参戦。
またもや敗北し、北条との協調路線を主張する息子と対立し、居城から追放されてしまいました。
その後は、常陸(ひたち、現在の茨城県)の大名 佐竹氏に仕え、北条氏と戦い続けました。
そして天正10年(1590年)、豊臣秀吉の小田原征伐にて、北条氏が滅亡してから程なくして、亡くなりました。
その生涯を、打倒北条に捧げた人生でした。
佐竹義重(さたけ よししげ)
天文16年(1547年)~慶長17年(1612年)
常陸(ひたち、現在の茨城県)の戦国大名。
20代で、那須家や小田家などの周辺勢力を倒し、常陸の大部分を勢力下に治め『鬼義重』と恐れられました。
現在の茨城県のほぼ全域を支配していたため、領地の隣接する関東の大勢力 北条氏や、現在の福島県会津付近を領有していた蘆名氏とも争うことになります。
蘆名家には後に次男の義広を送り込み、家督を相続させ実質的に乗っ取ることに成功。
勢力を広げ南下してきていた『伊達政宗』とも激突。
知名度こそ低いが、北条、伊達、蘆名といった強豪相手に互角に渡り合った名将。
豊臣秀吉の小田原征伐では、いち早く秀吉に臣従し立場を明確にしました。
関ヶ原の戦いでは、嫡男の義宜は西軍へ、義重は東軍へ味方するべきと意見が割れてしまい、戦後に減俸され現在の秋田県に領地替えとなりました。
里見義堯(さとみ よしたか)
永正4年(1507年)~天正2年(1574年)
安房(あわ、現在の千葉県南部)の戦国大名。
家督相続後に関東に勢力を広げつつあった『北条氏綱』と敵対。
同じく北条氏と敵対していた『足利義明』に味方し、第1次国府台の戦いで北条氏綱と激突。
この戦で義明が討死し敗北するも、北条氏が『武田信玄』や『今川義元』と揉めている間隙をついて房総半島に勢力を拡大しました。
氏綱の後を継いだ『北条氏康』が武田と今川と同盟(甲相駿三国同盟)を結ぶと、里見vs北条が本格化。
義堯は『上杉謙信』と結びこれに対抗。
北条氏との戦いに生涯をかけた武将でした。
長尾景春(ながお かげはる)
嘉吉3年(1443年)~永正11年(1514年)
戦国時代の初期の武将。
『太田道灌』のライバルとして、生涯に渡り不屈の闘志を燃やし続けた武将であり、『北条早雲』と並び下剋上の先駆者と言われた武将でもあります。
関東管領(かんとうかんれい)の山内上杉家の家宰(かさい)であった景春は『五十子(いらこ)の戦い』で、主君である山内上杉家を蹴散らし、下克上の先駆者として、名を馳せました。
その他にも『長尾景春の乱』や『長享の乱』と言った戦国初期の関東の争乱には、ほとんど関わっている、まさに関東の戦国時代の幕開けに、大きな影響を与えた人物。
何度負けても蘇る不屈の闘志で、反乱を続けた人生でした。
長野業正(ながの なりまさ)
延徳3年(1491年)~永禄4年(1561年)
上野(こうずけ、現在の群馬県)の箕輪城(みのわじょう)を本拠とした豪族。
通称『上州の黄班(じょうしゅうのとら)』。
多くの娘に恵まれ、巧みな婚姻政策で、周辺の有力な豪族と結束し、上野に攻め込んできた武田信玄と幾度となく激突。
巧みな戦術で、計6回に渡り武田軍を退け、信玄に『業正がいる限り上野には手が出せぬ』と唸らせた猛将と伝わります。
西から攻めてくる信玄だけでなく、南からの圧力であった北条氏とも対立し、上野を守り抜きました。
最期は病に倒れましたが、残された息子に対し『武田や北条に抗し切れないと悟ったならば、城を枕に討死せよ』と強烈な遺言を残し、この世を去りました。
一説には、『ちはやぶる~』の和歌で知られる平安時代のイケメン歌人『在原業平(ありわらのなりひら)』の末裔と言われています。
北条氏綱(ほうじょう うじつな)
長享元年(1487年)~天文10年(1541年)
早雲の嫡男で、北条氏二代当主。
実は『北条』を名乗ったのは氏綱からで、もともとの氏は『伊勢』。
関東地方の正当な支配者という意味を込め、鎌倉時代の執権北条氏にあやかり、氏綱から『北条』を名乗りました。
父 早雲の後を継ぎ勢力を拡大。
さらには、現在鎌倉の観光名所ともなっている『鶴岡八幡宮』の再建にも尽力するなど、北条家の威信を高めました。
初代の早雲、三代目の氏康の個性が強烈なため影に隠れがちですか、北条家の勢力を大きく伸ばした名将であることは間違いありません。
北条氏康(ほうじょう うじやす)
永正12年(1515年)~元亀2年(1571年)
北条早雲、北条氏綱に続く、後北条氏の三代目。
武田信玄、上杉謙信、今川義元ら強豪と凌ぎを削った名君で通称『相模の獅子』。
当時に関東の権力者たち、足利公方家、山内上杉家、扇谷上杉家を川越夜戦では、圧倒的不利な状況でありながら、敵の油断を誘い大勝利したと言われいます(川越野戦)。
『川越夜戦』と呼ばれるこの戦いは、戦国三大奇襲戦のひとつに数えられています。
また、上杉謙信や武田信玄に、居城である小田原城を包囲されるも、籠城で乗り切ったことでも有名。
後に、城下町を丸まる堀や塀で囲んだ『総構え(そうがまえ)』と呼ばれる堅固な城に改修された小田原城。
小田原城は、戦国時代でも有数の堅固な城でした。
氏康自身が内政や防衛戦で活躍したこと、また上杉謙信、武田信玄が有名過ぎることで、ちょっと地味で知名度が劣りますが、強敵たちと凌ぎを削り、一歩も引けを取らなかった氏康は、間違いなく戦国時代を代表する名将であったことは間違いありません。
北条早雲(ほうじょう そううん)
康正2年(1456年)~永正16年(1519年)
戦国時代の扉をこじ開けた人物で、関東に一大勢力を築いた北条氏5代の祖。
『北条早雲』という名前は後世に付けられたもので、実名は『伊勢盛時』とされています。
もともとは室町幕府に仕える幕臣でしたが、今川家に嫁いでいた姉(妹とも)の縁を頼りに駿河(するが、現在の静岡県東部)へと移住。
その後、『今川氏親』の擁立に尽力し、興国寺城主に任命されました。
以降も今川家に属し、伊豆地方に攻め入り足利茶々丸を討伐、伊豆を平定。
この伊豆乱入事件は、中央で起こった『明応の政変』と連動したものだと言われています。
さらに早雲の勢いは止まらず、箱根の峠を越え、相模(さがみ、現在の神奈川県)の小田原城を奪取。
ここに戦国北条氏が誕生することになったのです。
民政家としても著名で、早雲の政治方針は後の北条家当主たちにも受け継がれていきました。
北条綱成(ほうじょう つなしげ)
永正12年(1515年)~天正15年(1587年)
3代目 氏康の家臣を代表する人物。
元々は今川の家臣『福島(くしま)氏』の出身でしたが、氏康の父『氏綱』の娘を娶って北条一門になりました。
『地黄八幡』の旗印を掲げて数々の戦場に臨み、氏康の覇道を助けた猛将。
『勝った!!勝った!』と叫びながら突撃してくる綱成の部隊は何しろ強く、『地黄八幡』の旗印を目にした敵は恐れおののいたと伝わっています。
川越城の城将としても知られ、川越夜戦では敵の軍勢に囲まれピンチに陥るも、援軍の氏康本体を呼応し、城外へ打って出て敵を挟撃。
川越夜戦の大勝利にも貢献しました。
No.1は誰だ?
以上、戦国時代の関東地方を代表する名将を10人選んでみました。
では、この中でNo.1はだれなのか?と問われれば、個人的には『北条氏康』かなと思います。
正直、北条早雲と甲乙つけ難いのですが、上杉謙信や武田信玄といった超大物と互角に渡り合った氏康の実力は見過ごすわけにはいかないと思います。
どちらにしても、初代 早雲、二代目 氏綱、三代目 氏康のトップ3は揺るがないかなという感じです。
ということで、北条氏3代は実力がかなり拮抗している印象ですが、関東地方のNo.1武将は北条氏康とさせていただきます。
まとめ
以上、関東地方の名将10人でした。
ちなみに、順番をつけるとしたら・・・
- 北条氏康
- 北条早雲
- 北条氏綱
- 佐竹義重
- 北条綱成
- 里見義堯
- 長尾景春
- 長野業正
- 足利成氏
- 太田資正
という感じです。
ついでに、候補にあがったけど、惜しくも外れた武将は・・・
- 上泉信綱
- 佐竹義宜
- 北条幻庵
の3名でした。
あと、本来であれば『太田道灌』はランクインさせるべき武将ですが、没年が文明18年(1486年)なので、今回の対象範囲から外れているため、残念ながら圏外とさせていただきました。
関東となると、やっぱり北条氏(後北条氏)が多く入ってしまいますね・・・。
他にも、戦国武将をいろいろな角度でランキングにしてみました。
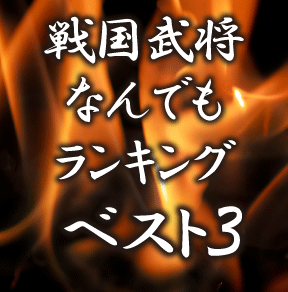
絶対に覚えておきたい戦国武将100人はコチラ。
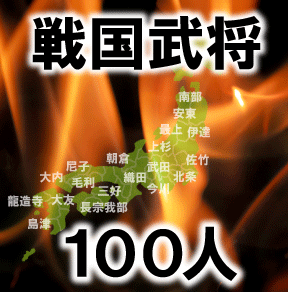
では、今回はこの辺で!
ありがとうございました。