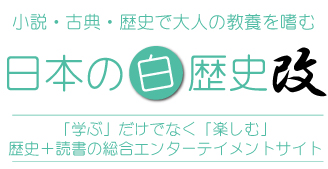平安時代中期に書かれた枕草子。作者は清少納言。
今回は、清少納言が初めて宮廷に出仕した頃のことが綴られている章段。
右も左も分からず泣きそうになる清少納言の意外な心情と、中宮定子との出会い、そして優しさが記されている大変興味深い章段となっています。
なお、かなり長い章段となります。枕草子原文では、ぶっ通しで展開するのですが、便宜上、場面が変わるところで小見出しを付け、簡単な見どころを追記しておくこととします。
ちなみに原文は一番下に掲載しています。
※枕草子の章段には諸説あることをご了承ください。
枕草子 184話その① ~初めての宮廷出仕~

緊張しまくる清少納言
中宮定子様にお仕えする為、宮廷出仕を始めたばかりの頃・・・。
何もかもわからないことだらけで、もう涙が出そう・・・。なので、毎日夜な夜な出仕して、三尺の几帳の後ろに隠れていました。
すると中宮様(定子)が絵などを取り出し、私(清少納言)にお見せくださる。
完全に恐縮している私に中宮様は、
『この絵は、こうなのよ、ああなのよ。この場面はね・・・』
などと絵の説明をしてくださる。
高坏に灯した明かりで、私の髪はハッキリと見え本当に恥ずかしかったけれど、何とか我慢して、その絵を拝見いたしました。
ひどく寒い時期だったのですが、中宮様の手がお召し物の袖からチラッと見える。艶やかな薄紅梅色で実に美しい。高貴なお方を目にしたことのない世間知らずな私のような者にとっては、『これほど美しいお方が現実世界にいらっしゃるのか!!』と驚きながら、恐る恐る顔を見上げたのです。
【見どころ】
明確な記述はありませんが、おそらく清少納言と中宮定子の初接触の場面と思われます。僕は枕草子が定子に捧げるために書かれたものだと推測していますので、ここの内容は枕草子執筆の出発点となる、たいへん重要なワンシーンと言う事ができるでしょう。

逃げようとする清少納言
明け方、私は早く局に下がりたくて(帰りたくて)、そわそわした気持ちでおりました。
すると、そんな私の様子をご覧になっていた中宮様は
『もうしばらく、ここに居なさいよ』
と、仰せになる。
しかし、私は顔を見られないようにして下を向いていたので、中宮様は(清少納言に気を使って)お部屋の格子をお上げにならない。
やがて、女官たちがやってきて、『早く格子を上げてください』などと言うので、女房たちが格子を上げようとする。
すると中宮様は、『おやめなさい』と女房たちを制しました。
事情(清少納言が恥ずかしがっていること)を知った女房たちは、笑いながら帰って行きました。
中宮様といろいろお話していると、だいぶ時間が経っておりました。すると中宮様は、
『そろそろ局にお下がりなさい。夜になったらまたいらっしゃい』
と仰せになる。
私が、そそくさと姿を隠すや否や、女房たちがバタバタと格子をあげると、外は雪が降っておりました。
登花殿(とうかでん、定子と清少納言がいた建物のこと)の庭は、立蔀(たてじとみ、衝立のような板のこと)が近くに巡らしてあって狭い。
本当に綺麗な雪・・・。
【見どころ】
ここは定子の優しさが顕著に表れている内容です。しかし、最も着目すべきは、清少納言が目にした雪景色の風景でしょう。
緊張して気を張り続けていた清少納言が、ようやく解放された後に見た風景。この雪景色の表現こそが、緊張から解放された彼女の心情を大きく物語っています。
定子に呼び出される清少納言
昼頃、中宮様が『今日は雪が降っていて空も曇っているから、顔もよく見えないので大丈夫ですよ』と私を何度もお呼び出しになりました。
古参の女房なども、
『参上しないとかえって失礼ですよ。隠れてばかりいないで行ってきなさい。こんな簡単にお呼び出しがかかるなんて、中宮様はよほどあたながお気に召したのでしょう。中宮様のご好意を無視するのは良くありませんよ』
と、有無を言わさず急き立てるので、何がなんだか分からない内に仕方なく参上したけど、どうにも気分が晴れない。
しかし、中宮様に参上する途中で目にした、火焼屋の屋根に雪が降り積もっている光景は、物珍しく大変面白い。
【見どころ】
相変わらず気分が晴れない清少納言。先輩女房に急き立てられる形で定子の元へ向かいます。ここでも屋根に積もった雪に目がいっており、前述の雪景色同様、定子の前に出ていない時は、少なからず心のゆとりが生まれていたことが想像できます。
先行き不安な清少納言
中宮様がいらっしゃる近くには、いつものように炭櫃に火をおこしてあるけど、そこにはあえて女房たちも近づきません。
中宮様は、豪華な火桶に向って座り暖をとっており、上級の女房が中宮様のお世話をするため、側近くにいらっしゃる。
その次の間の長炭櫃の周りには、沢山の女房たちが所せましと座っていらっしゃる。その女房たちが豪華な唐衣を垂らし、のびのびと振舞っている姿は、何とも羨ましい。
女房たちの手紙の取り次ぎ、すれ違う様子、立ったり座ったりする所作は気後れする様子もなく、楽しそうに話し、笑っていらっしゃる。
私はいつになったら、あのようにお勤め出来るのだろうかと想像すると、『私には無理かも』と委縮してしまう。
奥の方では、三、四人の女房が集まって絵などを見て楽しんでいる。
【見どころ】
先輩女房たちのやり取りを見て、さらに自信を無くす清少納言の心情が現れており、読む者に彼女の心境をより一層強く印象付けます。散文家としての彼女の才能が現れていると言えるでしょう。
藤原伊周現る
しばらくすると、人払いする大声が聞こえてくる。
『道隆様がこちらにいらっしゃるようです!!』 ※道隆は中宮定子の父親。
女房たちは大慌てで散らかった物を片付けているので、私はその隙に逃げ出したかったのですが、そうもいかないので、奥の方に引っ込んでいました。
しかしながら、自分でも不思議なのですが、好奇心が湧き几帳の隙間から覗いてみると、いらっしゃったのは道隆様ではなく伊周様でした。※伊周(これちか)とは大納言 藤原伊周。中宮定子の兄
伊周様のお召し物は、紫色の直衣、指貫。その紫が真っ白な雪に映えてたいそう美しい。
伊周様は柱の所にお座りになり、
『昨日と今日は物忌みで外出してはならなかったのですが、たいそう雪が降ったので中宮様の身辺が気になり、こうして参上してまいりました』
と仰る。
すると中宮様は、
『雪で道も無いと思っていたのに、どうやってここまでいらっしゃったのですか?』
と、問う。
伊周様は微笑んで、
『中宮様が私のことを哀れんでくれるかと思いましてね』
とお答えになった。
この気の利いたお二人の会話は、たいそう素晴らしく、伊周様は物語に登場する貴公子のようで、この現実世界に物語の世界が再現されたかのような感覚でした。
【見どころ】
作中では触れていませんが、この中宮定子と伊周のやり取りは、平兼盛という人が詠んだ和歌
『山里は 雪降り積みて 道も無し 今日来む人を 哀れとは見む』
が前提となっています。
上記赤字部分を会話の中に取り入れている二人の姿は、博識な清少納言にとって知的で魅力的に映ったようです。
伊周に見つかってしまった清少納言
中宮様は、白いお召し物を幾つも重ねた上に、美しい紅の唐綾をお召しになっていらっしゃる。そこに長い黒髪がかかっていらっしゃるお姿は実に美しい。絵に描かれたものは見た事あるけれど、現実としてお目にかかれるとは、まるで夢を見ているかのよう。
伊周様は、女房たちとお話しになり、冗談を言ったりしている。そんな伊周様と、気後れすることもなく言い返している女房たちの姿は、目もくらむほどで、聞いていただけの私の顔まで火照ってくる。
やがて果物が運ばれてきて、伊周様がお召し上がりになり、中宮様にも勧めていらっしゃる。
すると、突然伊周様が、
『几帳の後ろに隠れているのはどなたですか?』
と、女房に尋ねているご様子。
どうやら女房の誰かが、私のことを大げさに紹介してしまったらしい。
こちらに向ってくる伊周様。
しかし私は『まさか自分の所に来るわけではないでしょう』と楽観的に考えていたのですが、伊周様は私の目の前にお座りになり、話しかけてきたのです。
【見どころ】
清少納言は歌詠みの家系に生まれており、曾祖父(深養父)と父(元輔)が世に聞こえる有名な歌人でした。伊周や女房たちもそのことは知っていたようで、宮仕え初期段階から清少納言の存在はある程度有名であった思われます。
清少納言に興味津々の伊周
目の前にお座りになった伊周様は、まだ私が宮廷出仕する前の噂話を聞きつけて、
『あなたの噂は以前から聞き及んでおりますよ。あの清原元輔様の娘さんなのでしょう。あの話は本当なのですか?』
などと仰る。
几帳を隔てて遠くから覗いていただけでも恐れ多いのに、突然面と向かってお話することになり、まるで夢でも見ているような思いでした。
私は、宮廷出仕する前に帝(天皇)の行幸を拝見したことがあるのですが、その際、帝に同行していた伊周様が私たちの方をご覧になる時には、乗っている牛車の簾を閉め、姿が見えてはいけないと扇で顔を隠したりしていたのに、今こうして、伊周様と面と向かってお話している。
我ながら身のほど知らずで、『なんで宮廷出仕など始めてしまったのだろうか』と思い、冷汗が流れ、気が動転してしまいました。
あまりに恥ずかしく扇で顔を隠しておりましたが、その頼れる扇さえも伊周様に取り上げられてしまい、自分の髪の毛で顔を隠そうとしましたが、
『私の髪の毛は、人様に見せられるような美しい髪ではないのに』
と思うと
『もうダメだ。美しくない私の髪も顔もすべて伊周様に見られてしまう。恥ずかしがっている私の心の内もバレてしまう』
そう思い、早く向こうに行っていただきたかったが、伊周様は私から取り上げた扇をもて遊びながら、興味深そうに、
『この扇に描いてある絵は誰が書いたのですか?』
などと仰って、一行に扇を返してくれず立ち去る気配をみせない。
私は、もうお仕舞だと思い着物の袖を顔に当て、突っ伏していましたが、きっと顔に塗った白粉(おしろい)が袖についてしまい、汗ばんだ私の顔はひどい事になっていたでしょう。
【見どころ】
伊周のおもちゃにされる清少納言の姿が書かれています。
ここで注目したいのは、彼女の髪に対するコンプレックス。当時の宮廷女性は身長より長いロングヘアーで、その髪は美しさの象徴でした。しかし彼女は定子との出会いでも、髪に自信が無いような事を言っており、髪の毛に相当なコンプレックスを抱いていたことが分かります。
別の章段では、清少納言が現代で言うところのウィッグを装着していたような描写があることから、彼女は癖毛だったのではないかと思われます。
中宮定子の助け舟
いつまでたっても私の側から離れない伊周様を見て、中宮様は私の心中を察してくれたのだろうか?
『伊周様、これをご覧下さい。これは誰の手で書かれたものですか?』
と申し上げると、伊周様は、
『こちらで拝見するので渡してください』
と仰る。
すると中宮様は、
『いや、こちらにいらっしゃい』
と仰るが伊周様は、
『彼女(清少納言)が私を捕まえて離さないのですよ』
と冗談を仰る。
このような冗談を即座に思いつく伊周様は、いかにも若々しく、私のような身分の釣り合わない年増には相応しくなく、どうにもいたたまれない。
どうやら中宮様は、誰かの草仮名が書かれた本をご覧になっているご様子。すると伊周さまは、
『これは誰が書いた物でしょうね?博識で噂の少納言ならば知っているかもしれませんよ』
などと、とんでもない無茶振りをしてきたのでした。
【見どころ】
ここでは清少納言が自身の事を、年増(おばさん)と言っています。彼女が宮仕えを始めたのは28か29歳くらいと言われており、現代ではおばさんと言う程の年齢ではありません。しかし、今より寿命が短かった当時のアラサーは十分おばさんだったようです。
今だから思う初めての宮仕え
伊周様お一人の相手もままならないのに、同じような直衣姿の方がもう一人参上なさった。
この方は、もう少し朗らかな印象で冗談を言い、女房たちも面白がって笑っている。
女房たちが、誰々がこうでした、ああでしたなどと殿上人の噂話をしている姿を見ていると、まるで変化の者か天人がこの地上に降りてきたのか思い、ただただ驚くばかりでしたが、勤めに馴れ、何日も経ってみると、何という事もなく、ごく普通のやりとりだったと気づいたのです。
私がまだ宮廷に馴れない頃に驚嘆と羨望の眼差しで見ていた女房たちも、始めて宮仕えに出てきた時は同じような心境だったに違いない。
それが分かり、私も知らぬ内に、自然と宮仕えに馴れていったようです。
清少納言の意外な一面
以上が、枕草子 一七九段『宮にはじめてまゐりたるころ』、つまり清少納言が宮仕えを始めたばかりの回顧録となります。
この章段は、枕草子の中でもかなり長い章段となっており、それだけ宮仕え初期の清少納言が強い負い目を感じていたことが伺えます。
そして、なんと言ってもこの章段の見どころは、一貫して弱気な清少納言の姿。
枕草子の中で、かなり強気な発言が目立つ彼女ですが、この章段では打って変わって、ず~っと弱気な女性。全三〇〇段から成る章段の中でも異彩を放つ内容となっています。
これこそが、清少納言の人間味を感じさせ、僕が彼女に可愛らしさを感じる一番の要因なのです。
清少納言は意外と自らの失敗談なども大っぴらに書き残しており、同時代の才女である紫式部や和泉式部より、朗らかで明るい性格の持ち主だったように感じます。
それが、清少納言への親しみやすさであり、また、枕草子への親しみやすさなのかもしれませんね。
正確には、この後も定子との『くしゃみ』を巡るちょっと面白い話が続くのですが、記事が長くなりすぎる事と、清少納言の初出仕という内容とは、少々異なるエピソードなので、別の記事にしてみました。

もっと枕草子の世界を覗いてみたい方は、こちらからお好みの記事をご覧ください。

枕草子 一八四段『宮にはじめてまゐりたるころ』の原文は、この後をご確認ください。
【原文】 枕草子 一八四段① ~宮にはじめてまゐりたるころ~
宮にはじめてまゐりたるころ、物のはづかしきことの数知らず、涙も落ちぬべければ、夜々まゐりて、三尺の御几帳に後ろにさぶらうに、絵など取り出でて見せさせ給ふを、手にてもえさし出づまじう、わりなし。
『これは、とあり、かかり。それか、かれか』など、のたまはす。
高坏にまゐらせたる御殿油なれば、髪の節なども、なかなか昼よりもけそうに見えて、まばゆけれど、念じて、見などす。
いとつめたきころなれば、さし出でさせたまへる御手のはつかに見ゆるが、いみじうにほひたる薄紅梅なるは、限りなくめでたしと、見知らぬ里人ごこちには、かかる人こそは世におはしましけれど、驚かるるまでぞ、まもりまゐらする。
暁にはとく下りなむと急がるる『葛城の神も、しばし』など、おほせらるるを、いかでかは筋かひ御覧ぜられむとて、なほ臥したれば、御格子もまゐらず。
女官どもまゐりて、『これ放たせたまへ』など言ふを聞きて、女房の放つを、『まな』とおほせらるれば、笑ひて帰りぬ。
ものなど問はせたまひ、のたまはするに、久しうなりぬれば、『下りまほしうなりにたらむ。さらば早、夜さりは、とく』と、おほせらる。
ゐざり隠るるや遅きと上げ散らしたるに、雪降りにけり。登花殿の御前は立蔀近くて狭し。
雪いとをかし。
昼つ方、『今日は、なほまゐれ。雪に曇りて、あらはにもあるまじ』など、たびたび召せば、この局の主も、『見苦し。さのみやは籠りたらむとする。あへなきまで御前許されたるは、さおぼしめすやうこそあらめ。
思ふに違ふは、にくきものぞ』と、ただ急がしに出だし立つなれば、あれにもあらぬここちすれど、まゐるぞ、いと苦しき。
火焼屋の上に降り積みたるも、珍しうをかし。
御前近くは、例の炭櫃に火こちたくおこして、それには、わざと人もいず。
上臈、御まかなひにさぶらひたまひけるままに、近う居たまへり。
沈の御火桶の梨絵したるにおはします。
次の間に、長炭櫃にひまなく居たる人々、唐衣脱ぎたれるほどなど、馴れやすらかなるを見るも、いとうらやまし。
御文取り次ぎ、立つ居、行き違ふさまなどの、つつましげならず、もの言ひ、ゑ笑ふ。
いつの世にかさやうにまじらひならむち思ふさへぞ、つつましき。奥寄りて、三、四人さし集ひて、絵など見るもあめり。
しばしありて、前駆高う追ふ声すれば、『殿なゐらせたまふなり』とて、散りたる物取りやりなどするに、いかで下りなむと思へど、さらにえふともみじろかねば、今少し奥に引い入りて、さすがにゆかしきなめり、御几帳のほころびよりはつかに見入れたり。
大納言殿のまゐりたまへるなりけり。御直衣、指貫の紫の色、雪に映えていみじうをかし。
柱もとに居たまひて、『昨日、今日、物忌にはべりつれど、雪のいたく降りはべりつれば、おぼつかなさになむ』と申したまふ。
『道もなしと思ひつるに、いかで』とぞ御答へある。
うち笑ひたまひて『あれはともや御覧ずるとて』などのたまふ御有様ども、これより何事かはまさらむ、物語にいみじう口にまかせて言ひたるに違はざめりと、おぼゆ。
宮は、白き御衣どもに紅の唐綾をぞ上にたてまつりたる。
御髪のかからせたまへるなど、絵に描きたるをこそ、かかることは見しに、うつつにはまだ知らぬを、夢のここちぞする。
女房ともの言ひ、たまぶれ言などしたまふ御答へを、いささかはづかしとも思ひたらず、きこえ返し、そら言などのたまふは、あらがひ論じなどきこゆるは、目もあやに、あさましきまで、あいなう面ぞ赤むや。
御くだものまゐりなど、とりはやして、御前にもまゐらせたまふ。
『御几帳の後なるはたれぞ』問ひたまふなるべし。
さかすにこそはあらめ、立ちておはするを、なほほかへにやと思ふに、いと近う居たまひて、ものなどのたまふ。
まだまゐらざりしより聞きおきたまひけることなど、『まことにや、さありし』など、のたまふに、御几帳隔てて、よそに見やりたてまつりつるだに、はづかしかりつるに、いとあさましう、さし向ひきこえたるここち、うつつともおぼえず。
行幸など見るをり、車の方にいささかも見おこせたまへば、下簾引きふたぎて、透影もやと、扇をさし隠すに、なほひとわが心ながらもおほけなく、いかで立ち出でしにかと、汗あえていみじきには、何ごとをかは答へもきこえむ。
かしこき陰とささげたる扇をさへ取りたまへるに、振り掛くべき髪のおぼえさへあやしからむと思ふに、すべてさるけしきもこそは見ゆらめ、とく立ちたまはなむと思へど、扇を手まさぐりにして、絵のこと、『誰が描かせたるぞ』など、のたまひて、とみにも賜はねば、袖をおしあててうつぶしゐたるも、唐衣に白いものうつりて、まだらならむかし。
久しく居たまへるを、心なう、苦しと思ひたらむと心得させたまへるにや、『これ見たまへ。これは誰が手ぞ』と、きこえさせたまふを、『賜はりて見はべらむ』と申したまふを、『なほ、ここへ』と、のたまはす。
『人をとらへて立てはべらぬなり』と、のたまふも、いと今めかしく、身のほどに合はず、かたはらいたし。人の草仮名書きたる草子など取り出でて御覧ず。
『たれがにかあらむ。かれに見させたまへ。それぞ、世にある人の手は皆見知りてはべらむ』なそ、ただ答えさせむと、あやしきことどもをのたまふ。
一ところだにあるに、また前駆うち追はせて、同じ直衣の人まゐりたまひて、これは今すこしはなやぎ、猿楽言などしたまふを、笑ひ興じ、我も、なにがしがとあること、など、殿上人の上など申したまふを聞くくは、なほ、変化の者、天人などの下り来たるにやとおぼえしを、さぶらひ馴れ、日頃過ぐれば、いとさしもあらぬわざにこそはありけれ。
かく見る人々も皆、家の内出でそめけむほどは、さこそはおぼえけめなど、観じもてゆくに、おのづから面馴れぬべし。
※読みやすさを考慮し、適宜改行しています。
枕草子を原文と現代語で手軽に楽しみたい方にはコチラがおススメです。
では、今回はこの辺で!ありがとうございました。