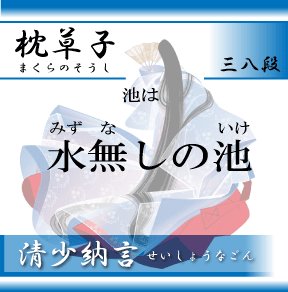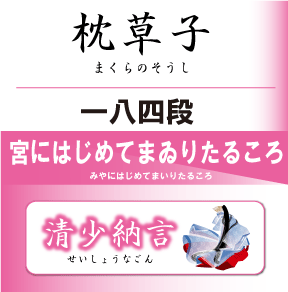春はあけぼの、やうやう白くなりゆく・・・で始まる冒頭部分はとても有名ですね。
ところで、枕草子の二段、つまり『春はあけぼの』の後って、どんな内容なのかご存知ですか?
今回は、意外と知られていない枕草子 二段の内容をお伝えします。
※枕草子の章段数は底本によって違うため、今回ご紹介している内容を細分化し2段~5段としている場合もあります。本記事では比較的入手しやすい「角川ソフィア文庫 新版枕草子」に準拠しています。
枕草子 二段の内容とは?
結論から言いますと、枕草子 二段には1月から12月の中で、清少納言が風情を感じる『月』の事が書かれています。
二段の冒頭部分の原文は以下の通りです。
ころは、正月、三月、四月、五月、七、八月、九月、十一、二月、すべて、をりにつけつつ、一年(ひととせ)ながら、をかし
内容を現代風にしてみると、このようになります。

一年の中で私の好きな月、それは一月、三月、四月、五月、七月、八月、九月、十一月、十二月・・・なんだかんだで、全部好き!!
つまり、『それぞれの月ごとに良さがある』ということです。
そして、この後に清少納言は各月の良い部分について詳しく言及しています。
それぞれの月に風情がある
それぞれの月ごとの良さに触れている二段ですが、具体的にはどのような部分に清少納言は良さを感じていたのでしょうか?
実は、二段の内容を見てみると、1月に行われる賑やかなイベントの風景にほとんど紙幅を費やしており、後半の方で3月に咲く桃の花の素晴らしさや、4月に行われる賀茂の祭(葵祭)について言及しています。
逆に言えば2月、5月~12月については何も書いていません。
なので、二段の主な内容は『1月に行われるイベント、3月の風景、4月のお祭りに対する清少納言の所感』となっているのです。
原文はかなり長いので、要約してお伝えすると以下のようになります。

一月一日(元旦)は空の空気がうららかで、衣装や化粧も入念にして、普段と様子が違っていておもしろいものです。

一月七日は、雪から顔を出している若菜を、みんなで大騒ぎしながら摘んでいくのも楽しいもです。また、宮中行事を見物しようと宮廷に出仕していない一般の女性たちも牛車を飾って見物に来るの様子も面白いですね。

一月八日は、女房や女官たちの人事異動が発表されます。昇進した者たちが大喜びで御礼してまわっている姿はもちろん、牛車が通る音にも喜びが感じられ、普段と違って面白いものです。

一月十五日は、餅粥の節句が行われます。この日、貴族にお仕えしている女房などが、お粥を作る時に使ったかき混ぜ棒で主君の隙を見つけて腰をひっぱたくのです。この日ばかりは無礼講で、叩かれないように用心している姿も、叩かれて悔しがっている姿も、見事にひっぱたいて大笑いしている様子もとても面白いものです。
※これは餅粥の節句に行われていた風習で、腰を叩かれた人には福がやってきたり、子宝に恵まれると言われていた。叩かれないように用心したり、見事に叩かれて笑いに包まれたりと、1月15日に行われる一種のイベントとして皆で盛り上がっている様子が、枕草子に描かれています。

三月三日になると、うららかな日差しを浴びて桃の花が咲き始めます。きちんと芽吹ききらずに、つぼみが咲き始めたくらいの時が一番素晴らしいです。

四月になると賀茂の祭(現在の葵祭)が行われます。この時期は、木々の新緑が鮮やかで、空気が澄んでいて空の景色も素晴らしく、私がとても好きな季節です。
2月と6月と10月が無い・・・
ところで、冒頭にあげた清少納言が好きな『月』を、もういちど確認してみましょう。

一年の中で私の好きな月、それは一月、三月、四月、五月、七月、八月、九月、十一月、十二月・・・なんだかんだで、全部好き!!
ちょっと疑問に思った方もいるのではないでしょうか?
よく見てみると、二月と六月、そして十月が入っていないのです。
これには様々な解釈があるので少し解説してみます。
まず前提として、平安時代は旧暦(昔の暦)なので、現代とはちょっと季節がズレています。
では旧暦を現代の暦に当てはめてみましょう。
二月は春の真っただ中。
六月は夏の終わり。
十月は冬の始まり。
おおよそこのような季節に当たり、清少納言がこの時期を中途半端と感じていたため、あまり魅力を感じていなかったのではないかという見方をしている書籍もあります。
また、単純な月の列挙では面白くないので、あえて二月、六月、十月を外しているといった説もあります。
清少納言の散文家としての才能から考えると確かに頷けますね。
個人的にはこちらの説を支持しています。
しかし、この辺も深く考えすぎない方が『枕草子』を純粋に楽しめると思いますので、あまり気にしなくても大丈夫かなと感じます。
枕草子 二段まとめ
以上が枕草子の二段のおおまかな内容になります。
まとめると、一段『春はあけぼの』が季節を切り取った情景であるのに対し、二段は暦である『月』を切り取った情景と言えるのです。
なお、枕草子の章段数は参考にする底本によってバラつきがあり、今回紹介している内容を二段と三段に分割する場合もあります。
しかし、単純に枕草子の中身を楽しむのであれば、この辺は読み手の解釈で問題ありませし、深く考えなくても良いでしょう。
今回は要点をかいつまんでのご紹介でしたが、二段の中身を全て読んでみたい方は、ぜひ枕草子を手に取る清少納言の直の言葉に触れてみてください。
枕草子の他の章段の解説も記事にしているので、ぜひご覧になってみてください。

↓さらにしっかりとした学びを手に入れたいあなたには、コチラがおすすめ↓
古文も日本史も学べる!中学生&高校生向け!通い放題、時間制限なしで勉強し放題の学習塾が登場。
①いつでもリアルタイム質問可能
②オンラインだから自宅で勉強可能
③どんなに利用しても定額制
↓詳しくはコチラ↓