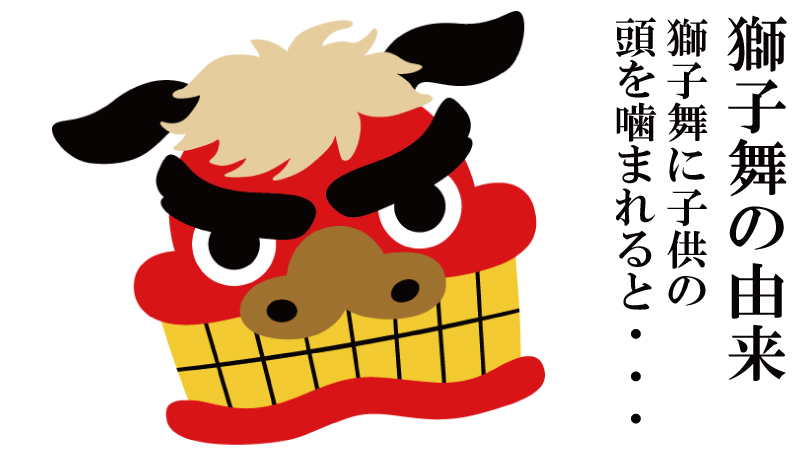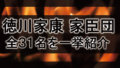正月になるとよく見かける『獅子舞』。
この獅子舞って、一体何者なんでしょうか?
この記事では、獅子舞の起源をたどってみたいと思います。
獅子舞の起源
獅子舞は基本的に正月の風物詩となっていますが、その起源はどこにあるのでしょうか?
その起源には諸説あり、中国の舞獅(横浜中華街などで見ることが出来る)という踊りが起源であると言われたり、あるいはインドの遊牧民が信仰していたいたライオンを偶像化したといった説があります。
また、インドネシアのバリ島にも、バロンという獅子舞に似た聖獣と、ランダという魔女が戦う『バロンダンス』なる信仰もあり、ハッキリとした起源はわかっていません。
それらの説の中には日本発祥と考えられているものもあり、古来日本から伝わる『鹿踊(ししおどり)』が起源だとも言われています。
獅子とはライオンのことあり、ライオンは『百獣の王』と言われるように強さの象徴でもあるため、多くの地域で信仰の対象とされていたのかもしれません。
例えば、沖縄の『シーサー』も獅子を模したものですし、神社の『狛犬』も『犬』となっていますが、本来は獅子を偶像化したものです。
このように主に東アジア、東南アジア圏の各地で発祥した獅子信仰が、それぞれ独自の形で発展したり融合したりしながら、現在の獅子舞の姿になっていったと考えられているのです。
獅子舞には噛まれるのがオススメ
正月になると神社などで舞い踊っている獅子舞をよく見かけます。
なんですが、獅子舞は踊りを披露しているだけではなくて、もうひとつ大切な意味を持ってるのをご存じでしょうか?
実は、『獅子舞に子供の頭を噛んでもらうと御利益がある』という風習があるのです。
『噛みつく』という行為をしてもらうことで、『神憑く(かみつく)』つまり『幸福の神が憑く』という、一種のゲン担ぎの意味があります。獅子舞は『邪気』を食べる神獣とされているので、年始にあたる正月に、一年の幸福を願って獅子舞に頭を噛んでもらうわけです。
また、子供が健やかに成長することを願う意味も込められています。
獅子舞の由来まとめ
以上、獅子舞の起源でした。
現在の日本の獅子舞は、各地の獅子信仰が発展、融合しながら今の形になっていったと思われます。
獅子舞は、その名の通り獅子を模したもです。なので、見た目も若干恐ろしい感じがします。
ですが、獅子舞をはじめ、沖縄のシーサー、神社の狛犬、バリ島の聖獣バロンなど、獅子は神聖な守り神とされる側面があります。
ちょっと恐ろしいですが、ぜひ正月には獅子舞に頭を噛んでもらって、一年の福を呼び込んでみてください。
その他、古来から伝わる日本の風習や伝承についても記事にしています。ぜひコチラもご覧になってみてください。