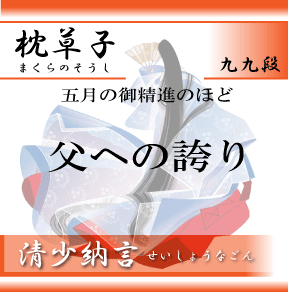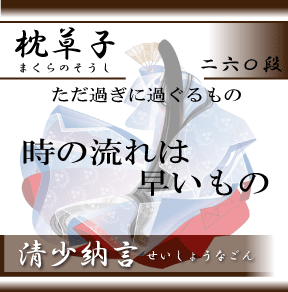平安時代中期に書かれた枕草子。作者は清少納言。
今回は、枕草子 二六段『たゆまるるもの』の現代語と原文、そしてこの章段の見どころを解説いたします。
なお『たゆまるるもの』とは現代風に言いますと、『怠けてしまうもの』と言った意味になります。
今からおよそ千年前の平安時代中期、清少納言は一体何を怠けていたのでしょうか?
なお原文から確認したい方は、下の方にスクロールをお願い致します。
※枕草子の章段には諸説あることをご了承ください。
現代版枕草子 26話 ~怠けがちになるもの~

わたくし、清少納言が思う『怠けがちになるもの』。
①精進の日のお勤め
②期日まで余裕がある準備期間。
③長期間、寺に籠っている時
枕草子 二四段の個人的解釈
この二四段は非常に短い章段となっています。ですが、その内容は現代人でも納得できる面白い章段です。では、ひとつずつ見ていきましょう。
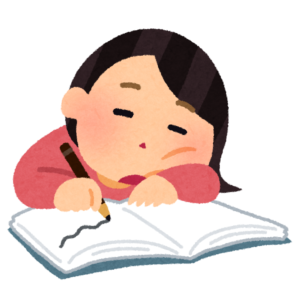
①精進の日のお勤め
まずは『精進の日のお勤め』。
ここで清少納言が言っている『精進』とは『仏道修行』のこと。つまり清少納言は、お寺で修行していると、ついつい気が緩んで怠ける事があると言っています。
清少納言の言わんとしている事を代弁してみましょう。
『仏様のありがたい教えに従い精進している時は、常に緊張感を持って臨んでいる。しかし、緊張しすぎたことが逆効果となり、すぐに緊張の糸が切れてしまう』
現代でも、気合が入り過ぎると、その熱がすぐに冷めてしまうことってありますよね。
『よし!!頑張るぞ!!』と、事に臨んだものの、すぐに飽きてしまった。
清少納言は、このように言っているのです。
②期日まで余裕のある準備期間
次は『期日まで余裕のある準備期間』。これは、もう説明不要なくらい現代人でも納得の内容ですね。
夏休みの宿題、テスト勉強、会社の提出書類・・・
『まだ一か月先か・・後でいいや』などと余裕をこいていたら、いつの間にやら期日ギリギリ。
誰でも一度は経験したことがあるのではないでしょうか?
なお、清少納言は一体何の準備を怠けていたのか?ちょっと考えてみた記事がこちらになります。
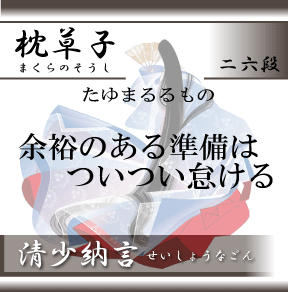
③長期間、寺に籠っている時
最後は、これ。
清少納言は、『寺に籠る』という表現を使っているのでちょっと分かりにくいのですが、実はものすごく単純なことを言っています。
長時間にわたる出来事は、人間だれしも途中で嫌になりますね。
清少納言は、何かをするとき長時間すぎると、途中で気が緩んで怠けてしまうと言っているんですね。

まとめ
いかがだったしょうか。これが枕草子 二四段『たゆまるるもの』です。
清少納言は三つのことを挙げていますが、どれも理解できるような気がしませんか?
今も昔も、人間の心理は何も変わっていないんですね。
もっと枕草子の世界を覗いてみたい方は、こちらからお好みの記事をご覧ください。

以下、『たゆまるるもの』の原文です。一行しかありませんけどね。
では今回はこの辺で。ありがとうございました。
【原文】 枕草子 二六段『たゆまるるもの』
精進の日の行ひ。遠き急ぎ。寺に久しく籠りたる。