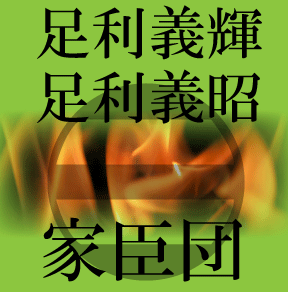室町幕府の頂点に君臨していた「足利将軍家」
応仁の乱、明応の政変を経て突入した戦国時代は、室町幕府の力が最も弱まっていた時代と言われています。確かにそういった側面もあるのですが、実際はまだまだ現役で、戦国時代中期あたりまでは大きな存在感を発揮していました。
とくに織田信長と同じ時代に活躍した『足利義輝』、『足利義昭』の兄弟は有名です。
戦国時代後期の将軍、第13代 足利義輝、そして第15代 足利義昭に仕えた主要な家臣一覧です。
将軍と家臣たち

室町幕府の将軍
足利義輝 あしかが よしてる

室町幕府第13代将軍「足利義輝」
生年:天文5年(1536年)
没年:永禄8年(1565年)
室町幕府13代将軍。
刀の扱いに長け『剣豪将軍』の異名を持つ武闘派将軍です。
11歳で将軍になりましたが、幕臣ながら幕府を牛耳っていた『細川晴元』、そして細川氏の後に実権を握った『三好長慶』らと対立し、たびたび京都から追い出されるという屈辱を味わっています。
後に長慶と和睦し京都に復帰し、諸大名の争いを調停しようと将軍としての職務をこなしていきます。
しかし、長慶亡きあと三好家を牛耳っていた『松永久秀』と『三好三人衆』と不和になり、松永らが放った刺客に襲撃され、壮絶な最期を迎えます(永禄の変)。
義輝は自ら刀を振るい大奮戦するも、最後は襖で押しつぶされ、その上から刀で串刺しにされて亡くなったと言われています。

足利義昭 あしかが よしあき

室町幕府第15代将軍「足利義昭」
生年:天文6年(1537年)
没年:慶長2年(1597年)
室町幕府15代将軍。
出家の身だったが、兄の義輝が松永久秀や三好三人衆に暗殺され、義昭も軟禁状態になりましたが、幕臣であった『細川藤孝(幽斎)』らに救出されました。
その後、織田信長や明智光秀、細川藤孝の尽力もあり15代将軍に就任。
しかし、織田家の勢力拡大とともに不和となり、『武田信玄』『浅井長政』『朝倉義景』『本願寺顕如』らとともに信長包囲網を形成するが、信玄が急逝したり、義景の腰が重かったりで失敗に終わりました。
その後も、抵抗を続けたがことごとく失敗し、しまいには京都から追放されてしまいました。
義昭の追放により、室町幕府は滅亡。室町時代が終わり、安土桃山時代へと突入していきます。
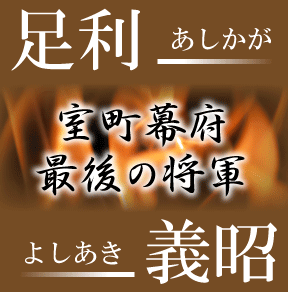
足利義栄 あしかが よしひで
生年:天文7年(1538年)?
没年:永禄11年(1568年)
義輝が13代、義昭が15代、じゃあ14代目は?という疑問を持つ方もいらっしゃるかもしれないので、彼の名も挙げておきます。
永禄の変で義輝を亡き者にした三好三人衆らによって擁立された、室町幕府14代将軍。血縁的には、義輝、義昭との いとこにあたる人物。一応、将軍ということになってはいますが、一度も入京できなかった珍しい将軍。
三好三人衆が松永久秀と不和になってゴタゴタやっている内に、織田信長が足利義昭を奉じて上洛。三好三人衆は信長に抵抗しますが、あっけなく敗れ去り第15代将軍に義昭が就任。そうこうしている内に、義栄は背中にできた腫物が悪化し、若くして亡くなってしまいました。
室町幕府の幕臣
細川藤孝(細川幽斎) ほそかわ ふじたか

細川幽斎(細川藤孝)
生年:天文3年(1534年)
没年:慶長15年(1610年)
第13代将軍 足利義輝に仕えていた幕臣。
義輝が『松永久秀』らによる凶刃に倒れた後は、『足利義昭』の将軍擁立に尽力し協力者を求めて諸国を流浪。その最中で『明智光秀』と出会い義昭の将軍就任に尽力、二人は盟友となりました。
しかし、本能寺の変後は時世を読み、光秀に味方することはありませんでした。光秀としては、藤孝が味方になってくれることを期待してたので、変後の計画が大きく狂うことになりました。
和歌の秘伝を極めた人物としても知られており、多くの文化・教養・グルメに精通した戦国随一のインテリ武将としても有名です。
関ヶ原の戦いで居城が包囲され絶体絶命の危機に瀕した際、幽斎を失うことで文化継承が断絶することを惜しんだ朝廷によって停戦命令が発布されたほどの文化人でした。
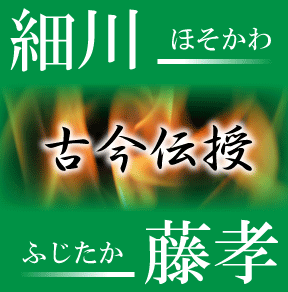
三淵藤英 みつぶち ふじひで
生年:不明
没年:天正2年(1574年)
細川藤孝の腹違いの兄。
永禄の変で13代将軍 足利義輝が亡くなった後、細川藤孝や和田惟政らとともに、軟禁されていた義昭を救い出し、将軍擁立に奔走。織田信長の尽力もあり、晴れて義昭は第15代将軍となり、藤英も義昭の重臣となりました。
やがて信長が勢力を増してくると、義昭と不和になり、弟の藤孝が信長に味方すると、藤英が大激怒。ここに兄弟間の争いが勃発しました。
しかし、義昭陣営は徐々に追い詰められていき、二条城に籠り奮戦するも抗しきれずに降伏しました。
以降は、信長の家臣となりましたが・・・。
↓その後の詳細はコチラの記事へ↓
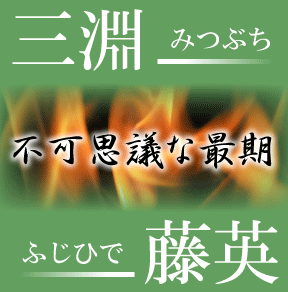
三淵晴員 みつぶち はるかず
生年:明応9年(1500年)
没年:永禄13年(1570年)
三淵藤英、細川藤孝の父親。第12代将軍 足利義晴の時代から幕臣として仕えており、その後も13代義輝、15代義昭の三代に仕えました。
和田惟政 わだ これまさ(1532~1571)

和田惟政
生年:享禄3年(1530年)?
没年:元亀2年(1571年)
13代将軍 義輝に仕えた人物。
永禄の変で義輝が亡くなると、足利義昭を次期将軍とするために尽力。細川藤孝、三淵藤英たちとともに、変の後に監禁されていた義昭を救出しました。
義昭が15代将軍となった後も幕臣として仕え、摂津の支配を任され『摂津の三守護』の一人に名を連ねました。(摂津の三守護とは、和田惟政、池田勝正、伊丹親興)
その後も有能な幕臣として活躍しましたが、荒木村重と戦った白井河原の戦いで討死しました。キリスト教を熱心に保護したことでも知られ、イエズス会宣教師から『都の副王』と称えられました。
松井康之 まつい やすゆき

松井康之
生年:天文19年(1550年)
没年:慶長17年(1612年)
義輝、義昭の二代に仕えた幕臣。永禄の変で義輝が討たれた後は、細川藤孝らと義昭を将軍とするために尽力しました。以降、細川家に付き従い、藤孝とともに織田信長の傘下となりました。
本能寺の変後、藤孝が息子の忠興に家督を譲った後も細川家に仕え、小田原征伐や文禄・慶長の役にも参陣しています。
また、千利休に師事し、茶の湯も嗜む文化人でした。
秀吉亡きあとも、細川とともに徳川政権の家臣となり活躍。細川藤孝、忠興とともに歩み続けた人生でした。
柳沢元政 やなぎさわ もとまさ

柳沢元政
生年:天文5年(1536年)
没年:慶長18年(1613年)
平安時代の藤原道長の一族『藤原北家(ふじわらほっけ)』の末裔。12代義晴、13代義輝、15代義昭の三代に仕えました。
義昭が織田信長と不和になり京都を追放され、毛利領の鞆(とも)で庇護されていた時も義昭に付き従っています。この時に、毛利輝元から領地を与えられ、さらに朝鮮出兵の際には秀吉に大抜擢され豊臣の家臣となっています。
秀吉亡きあとは、毛利氏の家臣として生涯を終えました。
一色藤長 いっしき ふじなが
生年:不明
没年:慶長元年(1596年)?
一色家は室町幕府に最高クラスの家柄『三管四職(さんかんししき)』の中の『四職』の中の一家(三管領:細川、畠山、斯波の三家。四職:一色、赤松、京極、山名の四家)。つまり家格の高い家柄で、藤長はその中の一色家の人物です。
永禄の変で義輝が亡くなると、足利義昭を次期将軍とするために尽力。細川藤孝、三淵藤英、和田惟政らとともに、変の後に監禁されていた義昭を救出しました。
織田信長によって義昭が京を追われ毛利領の鞆に庇護された際、今日に残って連絡役を勤めるよう命じられましたが、無視して鞆まで追いかけてきてしまったため、義昭からの信用を失いました。それ以降は、細川藤孝を頼りました。
蜷川親長 にながわ ちかなが
生年:天文2年(1533年)
没年:慶長15年(1610年)
13代将軍 義輝に仕えた人物。
永禄の変で義輝が討たれると、蜷川家も没落し、土佐へ逃れ長宗我部元親に仕えました。
関ヶ原の戦い後、西軍だった長宗我部家の所領は没収、その際に残った財務処理に手腕を発揮したことが家康の目に留まり、以降は徳川家に仕えることになりました。
真木島昭光 まきしま あきみつ(??~??)
生年:不明
没年:正保3年(1646年)
第15代将軍 足利義昭の側近。
義昭が織田信長と不和になったあとも、幕臣として織田と戦い、義昭が京を追われ毛利領に庇護されていた時も、それに付き従いました。
将軍家の幕臣たち
以上、足利義輝、義昭の主要家臣団一覧でした。
戦国時代の室町幕府はかなり弱体化していたイメージがありますが、実際はそうではありません。全国各地の大名たちがその権威を頼り、幕府の権威を借りることで合戦の大義名分にしていました。
そんな室町幕府が最後に輝いた時の将軍が、足利義輝であり足利義昭だったのです。
他の戦国武将の家臣団に関して知りたい方は、コチラをご覧ください。

戦国武将個人を記事にしたまとめはコチラ。
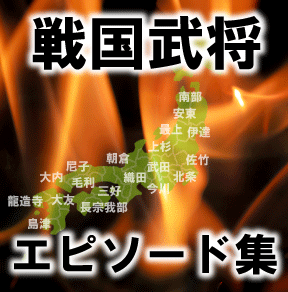
戦国武将を様々な角度でランキングにしてみた記事はコチラ。
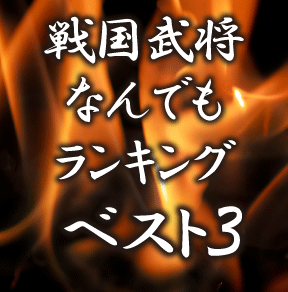
では、今回はこの辺で!
ありがとうございました。