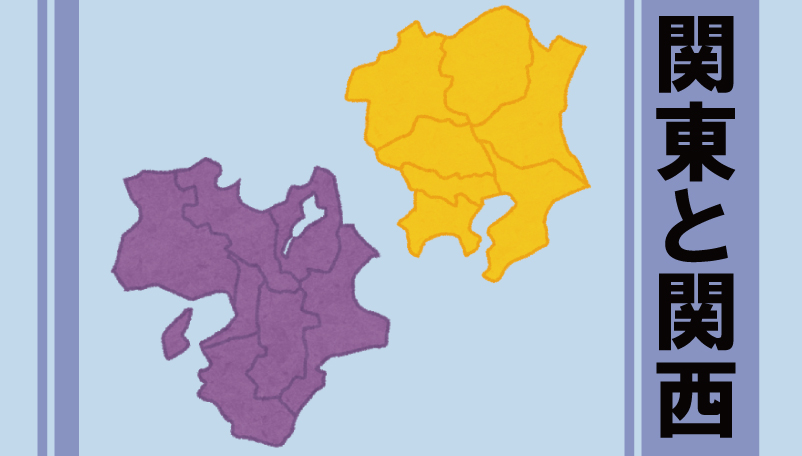関東地方と関西地方の名前の由来ってご存知ですか?
関東は東にあるから、そして関西は西にあるからなのかな?と思うかもしれませんが、実はもう少し深い意味が隠れています。
その鍵を握るのが『関』の一文字。

今回は『関東』と『関西』の地名の由来についてサクッと解説します。
関東と関西
関東とは?
『関東』と『関西』の由来を紐解くには、まず『関東』の意味を知っていると理解が早いです。
結論から言ってしまうと、
関東の『関』とは、『関所の東側にある地域』という意味です。
現在の関東地方に属する地域と言えば、
東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬の一都六県。
この一都六県が関東地方という括りになったのは江戸時代頃とされています。
江戸時代には『箱根の関所』、『小仏の関所』、『碓氷の関所』という3つの関所がありました。
- 箱根は現在の『神奈川県』と『静岡県』との県境。
- 小仏は現在の『神奈川県』『東京都』と『山梨県』の県境。
- 碓氷は現在の『群馬県』と『長野県』の県境。
これらの関所から見て東側の地域が『関東』。
『関所』の『東』だから『関東』と呼ばれているわけですね。
江戸時代より前は?
なお、今から遡ることおよそ1000年前の平安時代。
この時の関東は、今の関東よりずっと広い地域を指していました。
平安時代は『不破の関所(岐阜県)』『鈴鹿の関所(三重県)』『愛発の関所(福井県)』より東が全て関東でした。
なので、現在の長野県、山梨県、愛知県なども全て関東地方に含まれていました。

今よりかなり広い範囲が関東だったんですね。
そして、時代が下って行くに従い、室町時代の鎌倉公方が治める国が関東と呼ばれるようになり、関東の範囲は狭まっていき、江戸時代にはおおむね現在の関東と同じ範囲を『関東』と呼ぶようになりました。
関西とは?
では、一方の『関西』の由来はどうなのでしょうか?
昔は京都南部を中心とした一部の地域が『畿内(きない)』と呼ばれており、関西という言葉は浸透していなかったようです。
畿内とは、現在でいう所の、京都府の一部、兵庫県の一部、大阪府の大半、奈良県の全域を指します。現在も関西のことを『近畿』と言ったりしますが、これは明治時代に定着した言葉で『畿内に近い地域』だから『近畿』と言います。
また、関西という言葉が浸透したのも明治以降で、それ以前は基本的に『畿内』が一般的でした。
現在、『近畿』は京都府、大阪府、奈良県、兵庫県、滋賀県、和歌山県、奈良県の2府5県を指し、『関西』は近畿とほぼ同地域を指しますが明確な定義は無いようです。
なお広辞苑によると、『関西』の定義は「近江逢坂関以西の地」、「鎌倉時代以降は鈴鹿・不破・愛発(あらち)の三関以西の諸国」、「箱根関以西の地」となっており、おおむね中部地方と近畿の境目あたりにあった関所を基準とし、そこより西側を指す(箱根関以西の地は関東南東部)言葉となっています。

ちなみに関西と近畿の違いは以下の記事で詳しく解説しています。

なぜ昔は『畿内』だったかと言うと、かつての行政区分が『五畿七道(ごきしちどう)』だったことに由来します。

なお、五畿七道の詳細はコチラの記事をご覧ください。ここに北海道が『県』や『府』ではなく『道』である理由が隠されています。

まとめ
以上、関東と関西の由来でした。
まとめると・・
関所の東が関東。
関西の定義は明確になっていない。しかし昔は京都南部周辺の限られた地域を畿内、さらにその周囲の地域を近畿と呼んでいた。
という感じです。
現在の関東、関西以外の各地域にも、それぞれ由来があります。
気になる方は、コチラをご覧ください。





ありがとうございました。