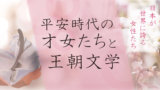平安時代中期の女流歌人 和泉式部の娘『小式部内侍』。母と同じく、恋に生きた女性として知られています。
しかし、母の名前が偉大過ぎて小式部内侍には、あまりスポットライトがあたらず、どんな人物だったのか知らない方もおおいのではないでしょうか?
恋に生き、儚く終わった小式部内侍の人生。そんな彼女の和歌を通じ、小式部内侍の性格や人物像に迫ってみたいと思います。
母 和泉式部と一緒に宮仕え
小式部内侍は、母親の和泉式部と同じタイミングで宮仕えをしていました。そのため、母と区別するために『小式部』と名付けられています。
仕えていた主は、母子ともに『中宮彰子』です。
小式部内侍は西暦999年頃の生まれとされていますので、紫式部の娘『大弐三位(だにのさんみ)』とほぼ同年代だったと思われます。(大弐三位も999年頃の生まれとされている)
ついでながら、清少納言の娘『小馬命婦(こまのみょうぶ)』も彰子の女房だったと伝わっています。和泉式部、紫式部、清少納言という有名人の娘たちが彰子の元で一堂に会していたと思うと、なんだか感慨深いものがありますね。
百人一首に選ばれた小式部内侍の和歌
小式部は母と同じく恋多き女性だったようで、藤原教通、藤原頼宗、藤原範永、藤原定頼といった複数の男性貴族との交際がありました。
藤原教通との間には『静円』という子供を授かっていますし、特に藤原定頼との逸話は有名です。
小式部内侍は、またもや母親同様、和歌の名人としても知られ、あまりに和歌上手なので和泉式部が和歌を代作しているのではないかと噂されてしまうほどだったと伝わっています。
「和泉式部が和歌を代作しているのでは」という疑惑を恋人の藤原定頼がからかったのですが、小式部内侍は見事な和歌で切り返しました。
大江山 いく野の道の 遠ければ まだふみもみず 天の橋立
大江山を越えて、生野へ向かう道のりですら行ったことがありませんので、母がいる天の橋立の地を踏んでいませんし、母からの手紙もまだ見ていません。
この和歌を見た藤原定頼は返歌をすることも出来ず、小式部内侍にやり込められてしまったのです。つまり小式部内侍は、
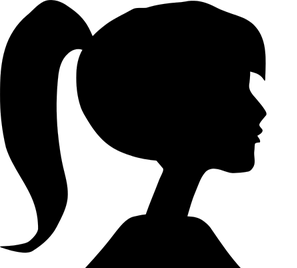
母に会える状況ではなかったし、母から手紙も来ていないのに和歌の代作なんて頼めるわけないでしょうが!!
と切り返したわけですね。
これが百人一首に選ばれた小式部内侍の和歌です。
悲しみに暮れる和泉式部
そんな小式部内侍ですが、残念ながら20代半ばという若さで亡くなってしました。病死と言う説もありますが、一般的には出産が原因とされています。
娘に先立たれた和泉式部の悲しみは相当なものだったようで、多くの哀傷歌が残されています。その中でも、一番有名なのが以下の和歌です。
とどめおきて 誰をあはれと 思ふらむ 子はまさるらむ 子はまさりけり
小式部は死ぬ間際に何を思ったのだろうか・・・?きっと自分の子供(静円)のことに違いないでしょう。私も親を亡くした時よりも、子供に先立たれた今のほうが辛い・・・。
和泉の深い悲しみが伝わってくる和歌ですね・・・。
また、和泉式部があまりに悲しむので、主の彰子が絹をプレゼントして慰めていたりもします。
他にも、和泉式部に小式部内侍が生前に来ていた服を差し出させ、その服を使って冥福を祈る経文の表紙にしようとしていたとも言われています。
ともかくも和泉式部の悲しみっぷりに彰子もかなり心を砕いていたようです。和泉式部の悲しみとともに、彰子の優しさも伝わってくるエピソードですね。
彰子にとっても、和泉式部と小式部内侍の母子は、かなりのお気に入りだったのかもしれません。
小式部内侍まとめ
以上、小式部内侍についてでした。
彼女は母の和泉と同じく情熱的な女性で、異性からの人気も高かったのでしょう。
この時代の女性と言うと、和泉式部はもちろんのこと、紫式部や清少納言が有名ですが、小式部内侍のような次世代の女性たちに注目してみるのも、また面白いものですよ。
平安時代の女性たちによる王朝文学、そして個性豊かな女性たち、そんな平安時代の文学作品や女性たちに関してたくさん執筆していますので、↓コチラ↓からぜひご覧になってみてください。