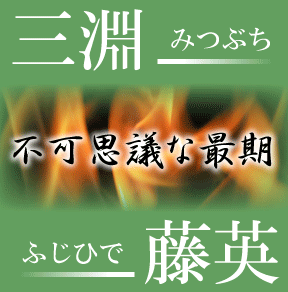赤染衛門(あかぞめえもん)は、平安時代中期に活躍した女性です。
平安時代中期は、宮廷で働く『女房』と呼ばれる数多くの女性たちが活躍しました。
赤染衛門も当然その中の一人です。
赤染衛門は、清少納言、紫式部、和泉式部といった有名女房とも同時代の人物。赤染衛門と彼女たち三人とは、一体どんな関係だったのでしょうか?
この記事では、それぞれの関係をご紹介ていきます。
紫式部との関係
まずは、源氏物語の作者『紫式部』との関係を見ていきたいと思います。

紫式部/出典:Wikipedia
赤染衛門と紫式部は、現代で言うところの職場の同僚にあたります。
赤染衛門と紫式部はともに宮仕えをしており、一条天皇の中宮(天皇の正妻のこと)である彰子(しょうし/あきこ)に仕えていました。
ちなみに、紫式部が自身の日記(紫式部日記)で赤染衛門の人柄について触れている、非常に興味深い内容があるので、現代風の言葉に置き換えてご紹介します。
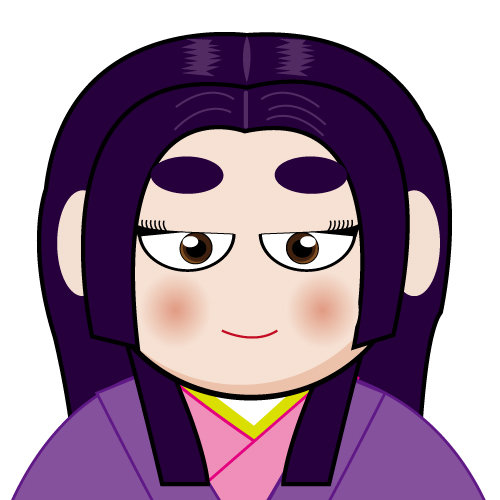
赤染衛門さんのことを、中宮様(藤原彰子)や殿(藤原道長)の周りでは『匡衡衛門(まさひらえもん)』というあだ名で呼んでいます。
最高級というわけではありませんが、彼女の和歌は本格派で、下手に読み散らしたりもしません。ちょっとした時に詠んだ和歌ですら、頭の下がる詠みっぷりです。
紫式部によると、赤染衛門は『匡衡衛門』というあだ名で呼ばれていたとのことですが、これには理由があります。
赤染衛門の夫は『大江匡衡(おおえのまさひら)』という貴族で、夫婦仲がとても良かったと言われています。また、赤染衛門は夫の出世にも尽力しており、宮廷内で匡衡のことを猛アピールするなどしていました。
こういったオシドリ夫婦ぶりが目立っていたため、『匡衡衛門』というあだ名がつけられ、周囲からもそう呼ばれていたようです。
そして紫式部に曰く、
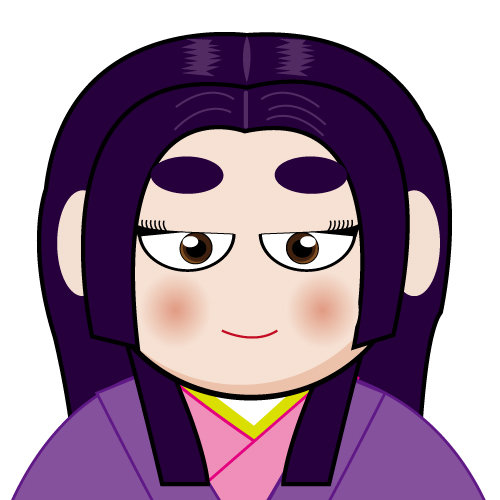
和歌の作風も本格的だった
と言っています。
もう少しかみ砕いた表現をするならば、上品で落ち着いた雰囲気の和歌といった感じだったのではないでしょうか。
和泉式部のところで後述しますが、情熱的な恋多き女性として名高い和泉式部とは、赤染衛門は正反対の女性だったのです。
立場的には赤染衛門が職場の先輩にあたるので、紫式部からは一目置かれた存在だったのでしょう。
ちなみに、この日記では清少納言や和泉式部に対しても批評しているので、興味のある方はご覧になってみてください。
【↓清少納言評↓】
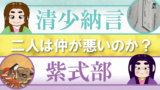
【↓和泉式部評↓】

清少納言との関係
次に、枕草子の作者『清少納言』との関係を見てみましょう。
赤染衛門と清少納言は一見すると関わり合いはなさそうなのですが、実際は交流があったと見られています。
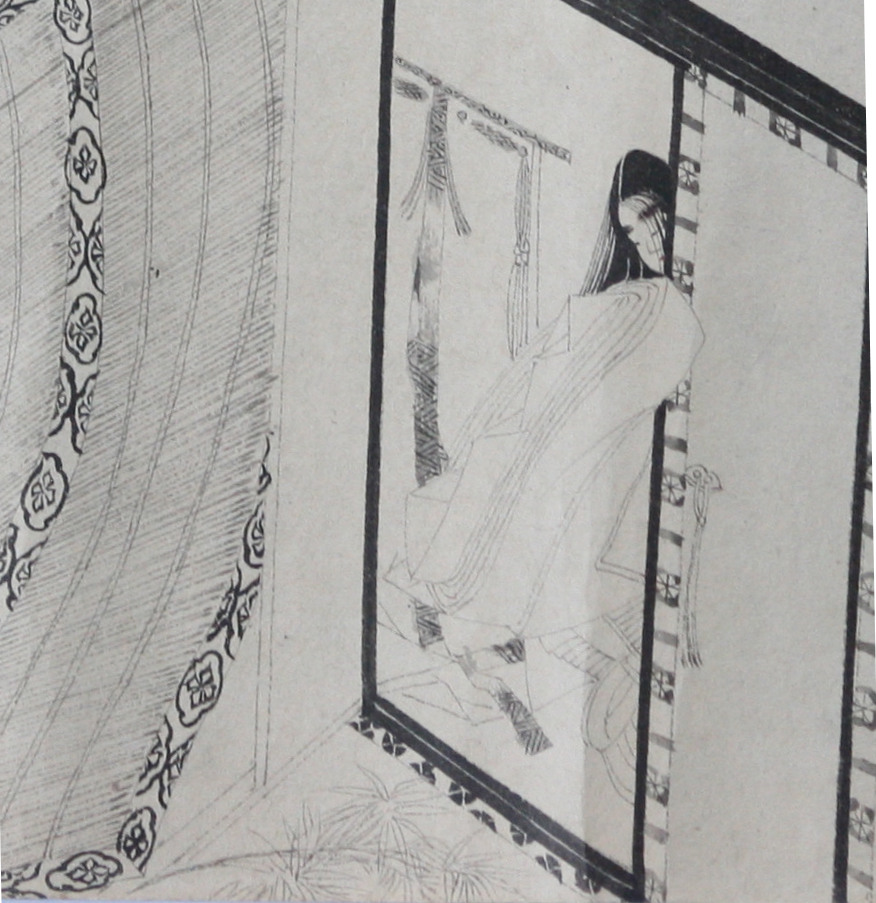
清少納言/出典:Wikipedia
前述の通り、赤染衛門は藤原道長の妻である倫子、あるいは彰子に仕えていたわけですが、清少納言は『定子』という女性に仕えていました。
今回ご紹介している4人では、唯一彰子の女房ではないのが清少納言です。

他の3名は彰子様にお仕えしていましたが、私は定子様に誠心誠意お仕えしておりました。
現代の感覚で言うと、働いている職場は同じでしたが上司が違う感じですね。
そして、今回の4人の中では、清少納言が最も早く宮仕えを辞めてしまいました。
しかし、宮廷との縁が全く無くなってしまったわけではなく、一部の女房たちとの交流は続けていたと見られています。
その中の一人が赤染衛門でした。
赤染衛門の和歌に、宮廷を離れた清少納言の動向を詠んだ作品があり、2人は何らかの交流はあったと考えられるのです。
その和歌は以下の通りです。
元輔が昔住みける家の傍らに、清少納言住し頃、雪のつみしく降りて、隔ての垣もなく倒れて見わたされしに
跡もなく 雪ふるさとの 荒れたるを いづれ昔の 垣根とか見る
黄色のマーカーで示した箇所は「詞書(ことばがき)」と言われる部分で、和歌の前書きみたいなものです。この詞書の中に「清少納言」の名前が確認できますね。
上記の和歌を現代の言葉に意訳すると、
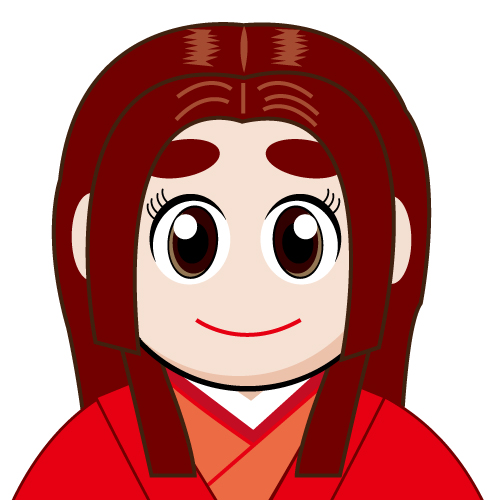
清原元輔(清少納言の父親)が昔住んでいた家のそばに清少納言が住んでいた頃、雪がひどく降って家屋敷を仕切る囲いが倒れていたので知らせてあげました。
となるので、赤染衛門と清少納言は少なくとも顔見知りではあったと考えられています。
和泉式部との関係
最後に、和泉式部日記の作者『和泉式部』との関係を見ていきます。

和泉式部/出典:Wikipedia
和泉式部は紫式部と同じく、彰子に仕える女房だったので、赤染衛門と和泉式部は職場の同僚です。
なお、4人の中では赤染衛門が最年長で、和泉式部が最年少となります。
赤染衛門の生年が天暦10年(956年)頃とされていて、和泉式部の生年が天元元年(978年)頃です。
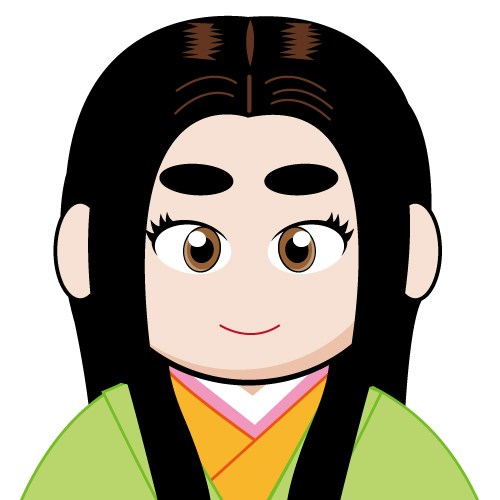
私と赤染衛門さんは、20歳以上の年齢差がありました。
職場の同僚とは言えこれだけの年齢差があると、仲の良い友人みたいな関係とはいかなかったのではないかも考えられます。
現代で言うところの、上司と部下のような関係だったのではないかと思われます。
ちなみに、赤染衛門と和泉式部は、性格や和歌の作風が真逆で、しばしば対照的な人物として比較されます。
赤染衛門が落ち着いた大人の女性で、一方の和泉式部が恋多き情熱的な女性、という感じです。
世渡り上手な赤染衛門
このように、紫式部、清少納言、和泉式部らと、満遍なく付き合いがあった赤染衛門。
夫の出世にために宮廷で根回しをしたり、子供を立派に育て上げたり、それでいて紫式部らとの人付き合いもそつなくこなしており、まさに良妻賢母といったイメージがピッタリな女性です。
そんな赤染衛門は、彰子に仕える前には『倫子』という女性に仕えていました。
『倫子』は藤原道長の妻、つまり『彰子』は藤原道長と倫子の娘です。
このように、時の権力者であった道長とも相当近い立場にあり、彼からの信頼も厚かったのではないでしょうか。
さらに、赤染衛門は紫式部、清少納言、和泉式部の3名よりも年上です。
和泉式部とは前述の通り20歳近く年上、清少納言と紫式部よりも10歳以上年長であったと思われます。
そして、最も長生きしています。
人付き合いも上手で、良妻賢母で、時の権力者にも信頼されて、4人の中では最も長寿だった赤染衛門。
正直なところ、紫式部、清少納言、和泉式部の中では一番地味で、知名度も圧倒的に低いのですが、実は彼女が一番穏やかな生涯だったような気がしてなりません。
ですが目立たない人物にこそ、幸せな人生を送る秘訣が隠されているのかもしれませんね。
まとめ
以上、赤染衛門は、紫式部、清少納言、和泉式部とどんな関係だったのか?でした。
- 紫式部とは職場の同僚で一目置かれていた。
- 清少納言とは友人か少なくとも顔見知り。
- 和泉式部とは職場の同僚だけど、年齢差が大きいので上司と部下のような感じだったかも。
と、なるのでした。
平安時代の女性たちによる王朝文学、そして個性豊かな女性たち、そんな平安時代の文学作品や女性たちに関してたくさん執筆していますので、↓コチラ↓からぜひご覧になってみてください。
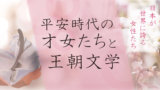
最後までお読みいただきありがとうございました。
【参考にした主な書籍】