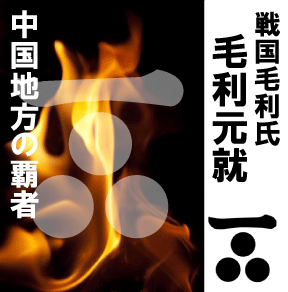ご来訪ありがとうございます。
『毛利家の大ファン』拓麻呂です!
早速ですが、戦国時代には名将と呼ばれる人物が、キラ星の如く登場します。織田信長、武田信玄、北条早雲、などなど・・・
今回はそんな戦国大名たちの中でも、屈指の実力者であろう男に登場していただきます。
その男は、中国地方の覇者『毛利元就』
彼はわずか一代で、安芸国(あきのくに、現在の広島県あたり)の小さな豪族から、中国地方全土を支配する大大名へとのし上がりました。
織田信長や武田信玄は、先代から受け継いだ一定の地盤があった事を考えると、元就はずっと不利な状況からのスタートです。
では何故元就は、わずか一代でこれほどまでの巨大勢力を築き上げることができたのでしょうか?
それは元就の切れ味鋭い謀略に他なりません。
戦国時代きっての名将は、恐ろしき謀略家でもあったのです。
今回は、そんな謀略家の毛利元就が大躍進するきっかけとなった『厳島の戦い』に注目してみます。
この戦いは、元就が張り巡らせた謀略の数々がハマりにハマり、圧倒的不利な状況をひっくり返した戦いです。
謀略と言うと聞こえが悪いですが、元就は不利な戦に臨むため事前準備を抜かりなく実施し、奇跡の大逆転勝利を演じるのです。
『謀多きは勝ち、少なきは負ける』
元就が残したこの名言こそ、彼の人生そのものであり、事前準備の大切さを教えてくれます。
では、元就の恐ろしき謀略の数々を見ていくことにしましょう。
※厳島の合戦には様々な説があり、今回紹介する内容は軍記物を参考にしている部分もあり必ずしも史実としての共通見解ではないことをご了承ください。
~中国地方の覇者『毛利元就』~
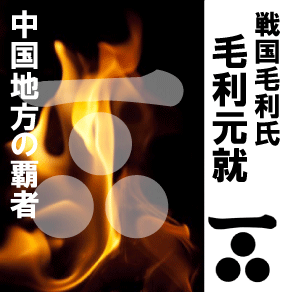
~厳島の戦いに至る経緯~
まず厳島の戦いに至る経緯を簡単に説明しておきます。
毛利家は非常に小さな勢力で、北に尼子氏、西に大内氏という巨大勢力に挟まれていました。この巨大勢力に従属することで、毛利家は何とか生き延びてきたのです。
当時、毛利家が従属していたのが大内氏。当主は大内義隆。
しかし、大内義隆は配下の謀反により世を去ります。
この謀反を起こした人物が『陶晴賢(すえはるかた)』。
この謀反人『陶晴賢』を倒すことを大義名分として、元就は決起するのです。
また、当時の厳島は海上交通の重要拠点であり、湾港都市としても栄えていた為、経済的観点からも厳島は非常に重要な拠点となり得ます。
つまり、『厳島の戦い』とは厳島争奪戦という意味合いが強い合戦と言えます。
そして1555年10月1日。戦いの火ぶたは切って落とされました。
毛利軍約4000vs陶軍約20000。元就にとって圧倒的に不利な戦いでした。
しかし、この戦力差をひっくり返して勝利するのが、戦国三大奇襲戦の一つに数えられる『厳島の戦い』です。(他の二つは信長の桶狭間の戦いと、北条氏康の川越夜戦)
この不利な戦いに勝利する為、元就の恐るべき謀略が張り巡らされていくのです。
~元就の謀略① 尼子家の内部崩壊~
まず元就の目は山陰地方に広大な領土を誇る尼子家に向けられます。
元就は陶晴賢との戦いにあたり、まずは背後の脅威を取り除く必要がありました。
と言うのも、毛利家の北には尼子家と言う強敵が控えており、陶軍と戦っている間に尼子家が攻めてきたら身も蓋もありません。
この時の尼子家の当主は『尼子晴久(あまごはるひさ)』。
彼の配下には新宮党と呼ばれる勇猛な一門衆がいたのですが、晴久と新宮党の間には軋轢(あつれき)が生じているという噂がありました。
新宮党は尼子家中でも勇猛でその武勇を誇り、横柄な態度が目に余る状態。当然、晴久もこの新宮党の態度には不満を持っていました。
元就はそこに漬け込みます。
元就は『新宮党が毛利家に内通している』との偽情報を尼子家領内に流布させ、新宮党の裏切りを示す偽文書が晴久の元に渡るよう仕向けます。
この偽文書を目にした晴久は、新宮党の裏切りを信じてしまい、尼子家の最強軍団『新宮党』を手打ちにしてしまったのです。
こうして元就は、背後の脅威である尼子家内部の混乱を誘い、強力な新宮党を消し去ることに成功しました。
なお、この新宮党粛清は、尼子家内部の所領問題が原因であり、元就の関与は無いとする説もあります。
ともかくも、元就は陶晴賢との戦いに集中できる状況になりました。
~元就の謀略② 『江良房栄』の引き抜き工作~
後顧の憂いを断った元就の謀略は、陶晴賢に向けられます。陶軍のNo.2とも言える『江良房栄(えらふさひで)』の引き抜き工作です。
元就は領土の一部(300貫)を与えることを条件に、房栄の引き抜きに成功します。
しかし、房栄は『もっと領土が欲しい』と要求してきました。
ちなみ元就が提示した300貫という数字は、当時の毛利家の重臣たちに与えていた所領と同じくらいで、かなりの好待遇であったと言われています。
元就は欲をかいた房栄の獲得を諦め、寝返った房栄の立場を利用し陶氏の周辺に『房栄が毛利に寝返った』ことを流布させました。
この情報を知った陶晴賢は、弘中隆兼(ひろなかたかかね)という部下に命じ、房栄を討ち果たします。
房栄の引き抜きには失敗しましたが、元就の機転の利いた謀略により、陶晴賢は自らの行動で重臣を失ってしまいました。
~元就の謀略③ 重臣『桂元澄』偽の裏切り~
さらに元就は自身の過去を利用した謀略で、陶晴賢を翻弄していきます。
元就には『桂元澄(かつらもとずみ)』という重臣がいます。
この桂元澄の父親(広澄)は過去に元就との因縁がありました。
元就の家督相続に対して、桂家の一族から反対者が出て元就を亡き者にしようとした経緯から、元澄の父は責任を取り自害しているのです。
この過去を元就は利用します。
元就は、陶晴賢に偽の手紙を送りつけます。手紙の差出人は桂元澄。
その内容はこうです
『私(桂元澄)は父の代より元就に積年の恨みがある。(陶晴賢が)元就との合戦に臨むのならば、その隙を突いて吉田郡山城(元就の本拠)に攻め込みましょう』
という物でした。
しかもこの偽の手紙は桂元澄の筆跡を、徹底的に真似て書かれていました。
陶晴賢はこの偽の裏切りを信じ、元就との決戦する意思を強めていきます。
~元就の謀略④ 厳島に城を築く~
厳島の戦いは、現在世界遺産にも指定されている『安芸の宮島』で行われた合戦です。
重要拠点であるこの宮島(厳島)をめぐる戦いが厳島の戦いですが、厳島が決戦の地に選ばれた理由にはもう一つの説があります。
この戦いに臨む元就の兵力は約4000人。一方の陶晴賢は約20000人。元就にとっては圧倒的に不利な戦いです。
まともに戦えば元就の敗北は必至。兵力で劣る元就が勝利するために選んだ地、それが厳島なのです。
この『島』という限られた範囲に20000という大軍を閉じ込めることで、身動きを封じる。つまり、閉鎖的な『島』という限られた範囲で戦う事で、大軍である陶軍にとってはマイナスに働くのです。
しかし、この『島』という限られた範囲内で決戦を行うには、陶軍を宮島に誘い出す必要があります。
そこで元就は、厳島に宮尾城という囮の城を築くのです。
この宮尾城は宮島を防衛する機能と、陶軍をおびきだす『餌』としての役割も持っていました。
陶晴賢としては、重要拠点である厳島に毛利の拠点があることは好ましくありません。当然この宮尾城を攻め落とす必要があります。実際、陶晴賢は宮尾城を攻めていますが、毛利側は何とか凌ぎきっています。
この宮尾城、一説には攻め落としやすいように、簡素な城であったとも言われています。
このような事も功を奏し、晴賢は宮尾城という『餌』に食いついたのです。
~元就の謀略⑤ 偽の情報操作~
決戦の地を厳島とする為、元就はダメ押しとも言える最後の謀略を繰り出します。
それは、実に鮮やかな情報操作でした。
戦国時代といえば数多くの間者(かんじゃ)が暗躍した時代でもあります。間者とは忍、現代のイメージ的には忍者という言葉が当てはまるでしょう。

※ちなみに当時の忍者はこんな格好していません。こんな格好してたら逆に目立ちます・・
多くの戦国武将は、情報を探る為に間者を敵の領地に潜り込ませています。
当然、毛利家領内にも陶晴賢の間者が入り込んでいます。
元就は、この陶晴賢の間者を逆に利用し、偽の情報を領内に流布します。
『厳島に築いた宮尾城は失敗であった。今、宮尾城に攻め込まれたらひとたまりもない。陶との戦いを選んだことを本当に後悔している』
このような弱気な発言をあえて流すことで、陶の間者はこの情報を陶晴賢に持って帰ります。この偽情報を掴んだことで陶晴賢は、今こそ宮尾城を陥落させるチャンスとばかりに厳島での決戦に向けて動き始めます。
元就が仕向けた数々の謀略にハマり勝利を確信した陶晴賢は、滅亡への道を歩み始めてしまったのです・・・
遅咲きの名将!毛利元就
こうして、毛利元就は万全の態勢で決戦に臨み、見事勝利します。
戦国時代は幾多の謀略が渦巻いていた時代でもありますが、その中でも元就の謀略家としてのイメージは飛びぬけています。
なお厳島の戦いは毛利元就が中国地方の覇者にまで上り詰める、その第一歩となる戦いです。元就この時五十八歳!
遅咲きの名将元就は大器晩成型の代表のような存在です。
これが元就の老獪な謀略家としてのイメージをより強調しているのではないでしょうか。
五十八歳で中国地方制覇という偉業の第一歩を歩み始めた毛利元就。
厳島の戦いにおける元就の一歩、それは後に日本を大きく動かした大革命『明治維新』へと繋がる第一歩とも言える重要な戦いなのです。
『謀多きは勝ち、少なきは負ける』
毛利元就は戦国時代を最も代表する名将であり、そして恐ろしい謀略家として今なお歴史ファンの心を掴み続けています。
~いろいろと怪しい厳島の戦い~
ここまで見てきたように、厳島の戦いは元就の謀略によって陶晴賢の大軍を破った合戦として語り継がれています。
しかしながら、この元就の謀略は『吉田物語』という後世に書かれた軍記物(物語風の合戦譚)を元にしており、史実としての厳島の戦いを描いていない可能性もあります。
新宮党の粛清は単なる尼子家の内輪もめなのではないか?とか、宮尾城は厳島の戦い以前から築城されていたとか・・・
極めつけは、決戦に臨む陶軍武将の遺言書が現存していることから、陶軍有利な状況では無く、両軍拮抗した合戦だったのではないか?なんて言う説もあります。
戦国時代の合戦譚は、軍記物が元となっているケースが多く、史実であるか不明なことが珍しくありません。
しかしながら、軍記物に描かれた合戦譚は戦国武将たちが躍動し、現代人の胸を熱くさせてくれることも事実です。
このような軍記物も一つの説として楽しむことが重要であり、他の一級史料などから違った説に触れてみることも、歴史を楽しむコツではないかと僕は考えています。
なお、厳島の戦いに参戦する村上水軍に関してはこちらをご覧ください。

厳島の戦いの経過はこちらをご覧ください。
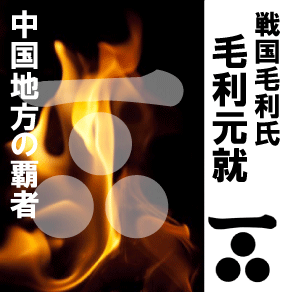
毛利元就の有名な逸話『三本の矢』の真実に迫った記事はコチラ
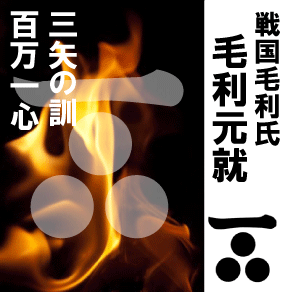
他にも、カッコイイ戦国武将は沢山います。あなた好みの男前を是非探してみてください。
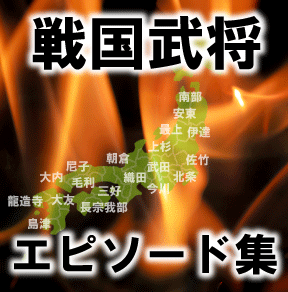
では、今回はこの辺で!ありがとうございました。