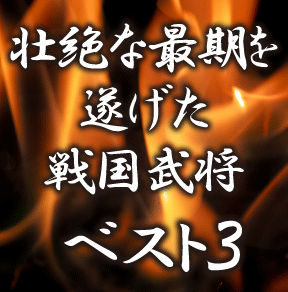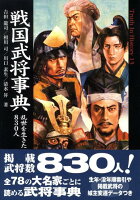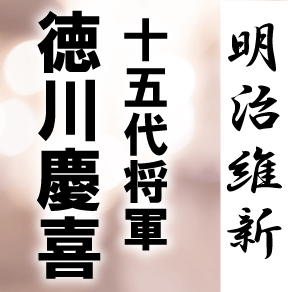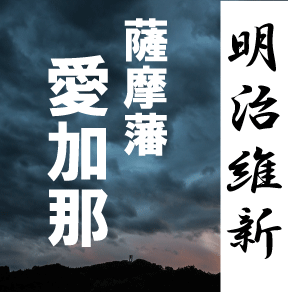戦国武将ランキング壮絶な最期を遂げたベスト3は誰だ!
日本全国が戦乱の世となった戦国時代。
中央政府が機能しなくなった為、この時代には全国各地で魅力的な人物が誕生し、多くの人物が戦場に散っていきました。
今回は、そんな戦国時代でも、特に壮絶な最期を迎えた人物を、独断と偏見で3人選び、ランキング形式でご紹介してみようと思います。
※今回ご紹介するランキングは個人的な見解になります。また、その最後は諸説あることも、ご了承ください。
壮絶な最期を遂げた戦国武将ベスト3
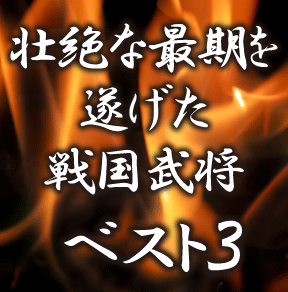
第3位 松永久秀
3位はこの人、松永久秀です。

「太平記英勇伝十四:松永弾正久秀」(落合芳幾1867年作)
その最期には諸説あるものの、やはり天守閣で大爆死を遂げたというインパクトは強烈なのではないでしょうか。
元々は三好長慶の家臣でしたが、長慶亡き後に三好家の主導権を握り、後に上洛してきた織田信長に屈します。
しかし、後に信長に背いた為、久秀の居城『信貴山城』を包囲されてしまいます。
信貴山城に立てこもっていた久秀の傍らには、『平蜘蛛(ひらぐも)』と呼ばれた茶釜がありました。
平蜘蛛は、当代きっての名器とされ、茶器愛好家でもあった信長は、平蜘蛛を城外へ出し、自信の手渡すよう命じます。
しかし、久秀は応じませんでした。
自身の頭にお灸をすえ、平蜘蛛に大量の火薬を詰めこんだ久秀は天守に火を放ちます。
するともはや爆薬と化した平蜘蛛は大爆発。
久秀は名器 平蜘蛛とともに、信貴山城の天守閣もろとも吹っ飛んだのでした。

第2位 足利義輝
2位はこの人、室町幕府13代将軍 足利義輝です。

足利義輝像(国立歴史民俗博物館蔵)
彼は将軍でありながら暗殺されるという、悲運を遂げた人物です。
室町幕府の権威を復活させたい足利義輝。
一方、畿内での主権を確固たるものにしたい三好三人衆+松永久通(松永久秀の息子)。
三好三人衆+松永久通にしてみれば、幕府権威が復活されては自分たちが主導権を握れなくなるので、義輝は目の上のたんこぶです。
三好三人衆+松永久通は、軍勢を義輝の居る二条御所に差し向けます。
強襲された二条御所。
大勢の兵士が義輝に襲い掛かります。
しかし、義輝は『塚原卜伝(つかはら ぼくでん)』から剣術を学んだ剣豪将軍。
襲い来る松永軍を次々を切り伏せて行きます。
床に何本もの刀を突き刺し、血や油で刀の切れ味が落ちる度、床から刀を抜いて応戦し、驚異的な強さを発揮したと伝わっています。
鬼のような強さを見せる義輝の剣技に対し、松永軍は畳と盾にして義輝に突撃。
押し倒された義輝は畳の下敷きにり、松永軍は畳の上から義輝を四方八方から串刺しにされてしまいました。
なお、足利義輝の詳細記事はコチラをご覧ください。

第1位 山県昌景
そして1位はこの人、武田信玄を支えた猛将 山県昌景景です。

甲越勇将傳武田家廾四将:山縣三郎兵衛昌景(歌川国芳作)
武田随一の猛将としても名高い山県昌景は、長篠の戦いで壮絶な最期を迎えることとなります。
以下、伝説的なエピソードも含みますのでご了承ください。
山県昌景を始め、武田信玄と共に幾多の戦場を駆け巡ってきた歴戦の勇士たち。
彼らはこの戦いの危うさを感じ取り、主君である勝頼に戦を回避するよう説得したと言われています。
しかし、勝頼には受け入れられませんでした。
やむなく昌景率いる真紅の部隊は突撃を開始。
ところが織田、徳川連合軍は馬防柵(ばぼうさく)を自軍の前に張り巡らし迎え撃ちます。
この時織田軍が繰り出した戦法が、世に名高い三段撃ちです。
間断なく浴びせられる一斉射撃の前に次々と倒れていく武田軍。
止むことのない三段撃ち。次々と倒れていく歴戦の勇士たち。
昌景率いる真紅の部隊も例外ではありませんでした。
鬼の形相で采配を振るう馬上の昌景。
その時、一斉射撃が昌景を襲います。・・・彼の両腕は被弾し、満足に動かせなくなっていました。
しかし、昌景は最後の気力を振り絞り、采配を口にくわえ指揮を取り始めました。
その瞬間、織田徳川連合軍の一斉射撃が、再び昌景を襲いました。
赤備えの名将 山県昌景・・・真紅の鎧に身を包んだ歴戦の勇士は戦場の露と消えました。
なお、山県昌景の詳細はコチラをご覧ください。
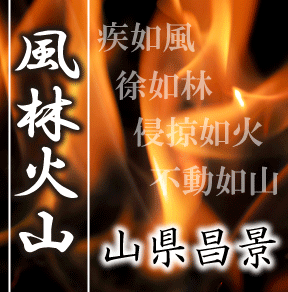
壮絶な最期を遂げた3人の武将たち
以上、壮絶な最期を迎えた戦国武将ベスト3でした。
多くの武将たちが志半ばで散っていった戦国時代。
そんな中でも、特に凄まじい最期を迎えた三人の人物。
1位 山県昌景
2位 足利義輝
3位 松永久秀
ちなみに・・4位以降は
4位 高橋紹運
5位 大谷吉継
です。
高橋紹運と大谷吉継も候補に挙がっており、かなり迷いました。
きっと戦国ファンそれぞれの想いもあることと思います。
『壮絶な最期を迎えた戦国武将』
あなたは、誰を選びますか?
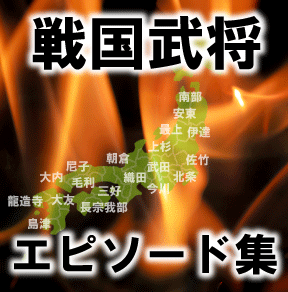
戦国武将をいろいろな角度でランキングにしてみました。
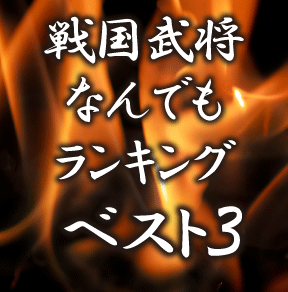
では、今回はこの辺で!
ありがとうございました。
【主な参考資料】