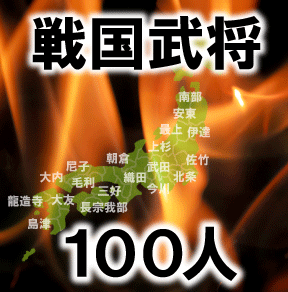平安時代中期を代表する文学の中に『蜻蛉日記(かげろうにっき)』があります。
枕草子や和泉式部日記に先駆けて執筆された作品で、後に隆盛する女流文学に大きな影響を与えました。
蜻蛉日記は、作者の女性が夫の浮気に嫉妬して、ヘソを曲げたり悲しんだりする非常に個性的な作品です。
そんな蜻蛉日記の中身や基本情報をご紹介していきます。
蜻蛉日記の作者は誰?
蜻蛉日記の作者は『藤原道綱母(ふじわらのみちつなのはは)』と呼ばれる女性です。
その名が示す通り、藤原道綱という人物のお母さんで、百人一首に和歌が選出されている女性でもあり『右大将道綱母』とも呼ばれています。
なお、藤原道綱(右大将道綱)は、摂関政治で有名な藤原道長の腹違いの兄弟です。
『藤原道綱母』にしろ『右大将道綱母』にしろ、ともに彼女の実名ではなく、残念ながら本当の名前は分かっていません。
昔の女性は一部の高貴な人物を除き、名前が残らないのが普通なのです。
藤原道綱母よりほんの少しあとの時代に登場してくる『紫式部』や『清少納言』も本名ではありません。
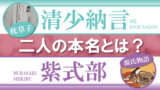
ただ、紫式部や清少納言らは、宮廷で働いていたのに対し、藤原道綱母はずっと家にいる専業主婦のような感じでした。
美人だったうえに、染め物や裁縫が得意で夫の兼家からもその腕を認められています。
ちなみに藤原道綱母は、更級日記の作者 菅原孝標女(すがわらたかすえのむすめ)の叔母にあたります。
夫『藤原兼家』と蜻蛉日記の概要
そして、藤原道綱母の夫が『藤原兼家(ふじわら の かねいえ)』という人物。
藤原兼家は出世街道を爆進中、豪胆な性格で細かいことは気にもぜず、すぐに軽口をたたくイケメン貴公子。
和歌にも精通していて女性にもモテモテで、当時は一夫多妻制だったこともあり二股、三股は当たり前。
そんな藤原兼家の妻が、蜻蛉日記の作者 藤原道綱母です。
当時の結婚生活は、現代のように夫婦が同居するわけではありません。
夜な夜な夫が妻の家にやってきて、一晩を過ごす『通い婚』という結婚形態が普通でした。
藤原道綱母は、兼家にベタ惚れ。
しかし、兼家は他の女性にも手を出して、自分以外のところにも通っている。
そんな状況に苛立ったり、いじけたり、文句を言ったり、あるいは兼家の浮気相手に対し恨みつらみを吐き出したり・・・
平安時代の一女性の切ない想い。あるいは、妻として母親としての息子への想い。兼家に対する愛が深すぎるからこその、藤原道綱母の凄まじい嫉妬心が綴られた作品。
それが蜻蛉日記という作品なのです。
蜻蛉日記にはどんなことが書いてある?
では、蜻蛉日記には具体的にどのようなことが書いてあるのでしょうか?
特に印象的な部分を抽出して、わかりやすく意訳していくつかご紹介します。
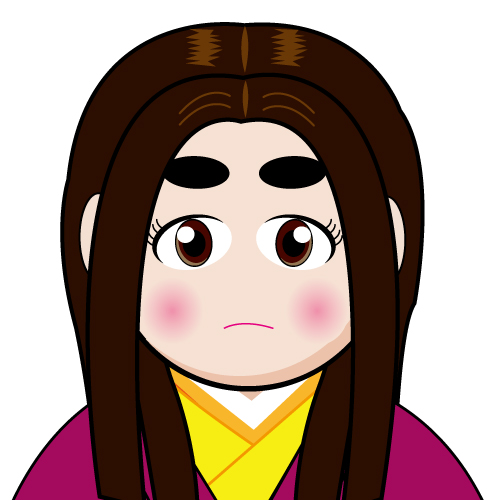
夫の兼家が外出中に、彼の手紙が入った箱をこっそり開けてみた。すると、他の女に送ろうとしていた手紙を発見してしまった。
【解説・所感】
これって現代で言うところの、奥さんにスマホを見られて浮気がバレたのと同じような状況ではないでしょうか・・・。
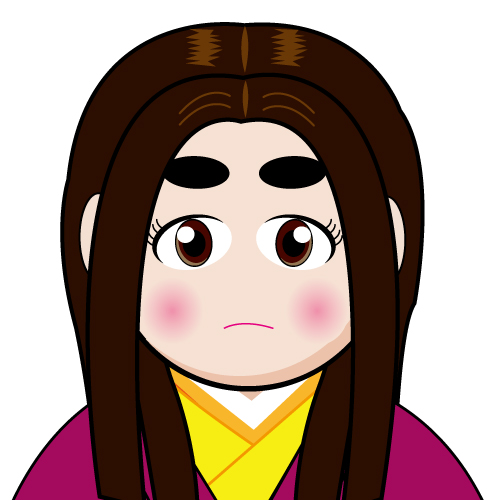
何気ないある日、兼家とささいなことで口論になり、私が言わなくてもいいことまで言ってしまったので、兼家は怒って帰ってしまった。
もう私のところには来てくれないかもしれない・・・。
【解説・所感】
夫婦にしろカップルにしろ、こういう状況って今でもよくありませんか?好きだからこそカッとなって余計なことまで口走ってしまい、後で後悔する作者の姿からも兼家への愛が感じられます。
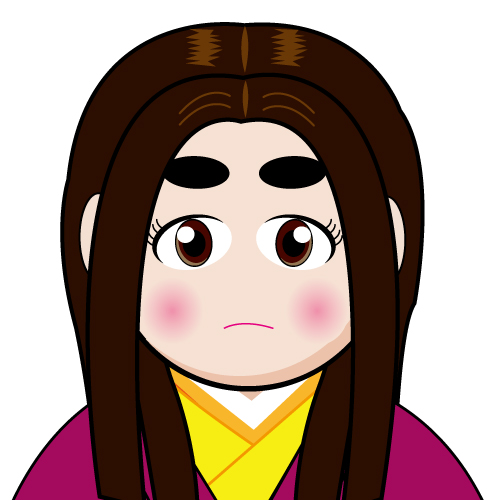
兼家と別の女が乗った牛車が騒がしく私の屋敷に近づいてくる。そして、牛車は屋敷の前を通り過ぎて行ってしまった。
【解説・所感】
この当時は一夫多妻制ではあるのですが、それにしたって、他の女性とオッ所にわざわざ道綱母の屋敷の前を通り過ぎていくというのは、さすがに酷ですね。
ちなみに、この時の女性は「町の小路の女」と言い、出産間近という状況でした。
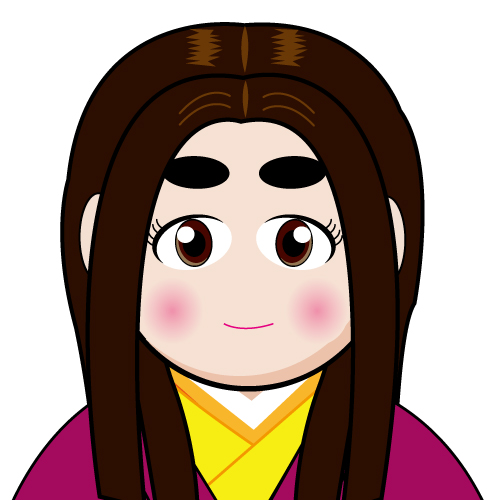
病気になった兼家から手紙が届いた。
『ようやく意識がはっきりしてきて、まだ具合は悪いけど、君に会いたい。今夜僕の家にきてくれないか?』
病状が気になって仕方なかった私は、恥を忍んで兼家邸へ赴いた。
【解説・所感】
当時は通い婚が当たり前ですし、貴族女性が顔を見られるというのは恥ずかしいことでした。なので専業主婦の貴族女性は、基本的に屋敷内に引きこもっています。
それなのに、作者はわざわざ兼家の屋敷に会いに行っています。これは当時としては異例なことで、作者がいかに藤原兼家を愛し、病気を心配していたかが分かるエピソードです。
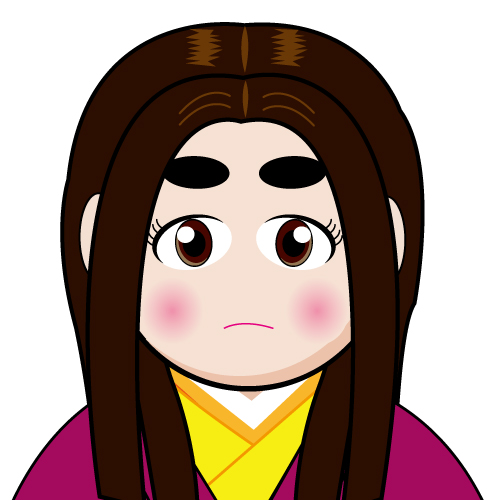
源高明様が流罪になった。世間は騒然となり、しばらくはこの話題で持ちきりだった。
本来、日記に書くことではないけれど、この事件を切なく想うので、あえて書き記すことにした。
【解説・所感】
これは安和2年(969年)に起こった『安和の変』と呼ばれる事件について触れた部分です。何気ない日常を記す女流文学の中に、こういった一節があることで、彼女たちも時代のうねりの中で生きていた女性たちなんだなと実感できます。
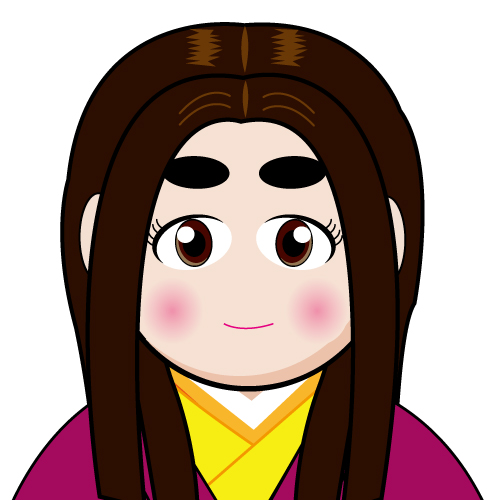
息子の道綱が、天皇がご覧になる弓の競技に出場する。兼家もやってきて、道綱の衣装を整えるなどしてくれた。私は祈るような気持ちで道綱と兼家を送り出した。
前評判では、全く勝ち目がないと言われていた道綱だったが、大健闘して引き分けにまで持ち込んだらしい。兼家は涙を流しながら道綱の活躍を振り返り、私に伝えてくれた。
それから数日間、私の屋敷には道綱の活躍を祝いに様々な人がやってきた。どうしたらいいのか分からないくらい嬉しかった。
【解説・所感】
これは兼家の妻としてよりも、道綱の母としての面が強く出ているエピソードです。息子を想い誇りに思う母親の心は、今も昔も変わらないことが分かります。
また、兼家も父親として息子を想っている描写があり、ここだけ見ると幸せな家族ですね。
激しく共感できる蜻蛉日記
このように、蜻蛉日記とは藤原道綱母が妻としての立場から見た夫婦関係の悩みや嫉妬、また道綱の母親としての息子を想う気持ちが綴られた作品です。
この時代の女流文学はたくさんありますが、その中でも『妻』として、あるいは『母親』として、作者の立場が明確であり、書かれている内容も『嫉妬』や『母性』といった感じで、割とストレートで分かりやすいです。
なので、平安時代の女性の文学の中でも共感しやすい作品なのではないかと思います。
とくに旦那さんや彼氏に不満を持っている方は必見ですよ。
蜻蛉日記まとめ
以上、蜻蛉日記についてでした。
妻としての嫉妬、母親としての想いを綴った蜻蛉日記。いつの時代も人の心は変わらない、そして男女の関係は難しいものだということを、今に伝えてくれています。
他の平安時代の女流文学についても記事にしています。興味のある方はコチラをご覧ください。
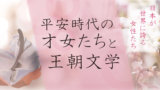
最後までお読みいただきありがとうございました。
【参考にした主な書籍】