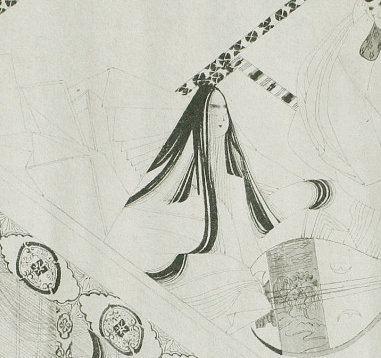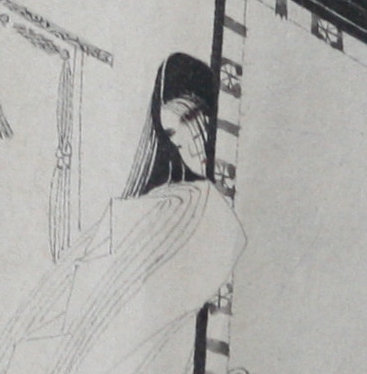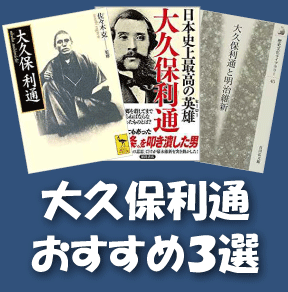清少納言が書いた『枕草子』。
よくよく考えてみると『枕草子』っていう題名、よく意味がよく分かりませんよね。とくに『枕』の意味がよく分かりません。
実はこの『枕』の意味には、様々な説があるのです。
今回は様々な説の中から、『枕草子』という題名に込められたひとつの説をご紹介するとともに、清少納言とその主 藤原定子(ふじわらのていし)の間にあったやりとりと想いをお伝えしていきます。
『枕草子』という作品名の意味
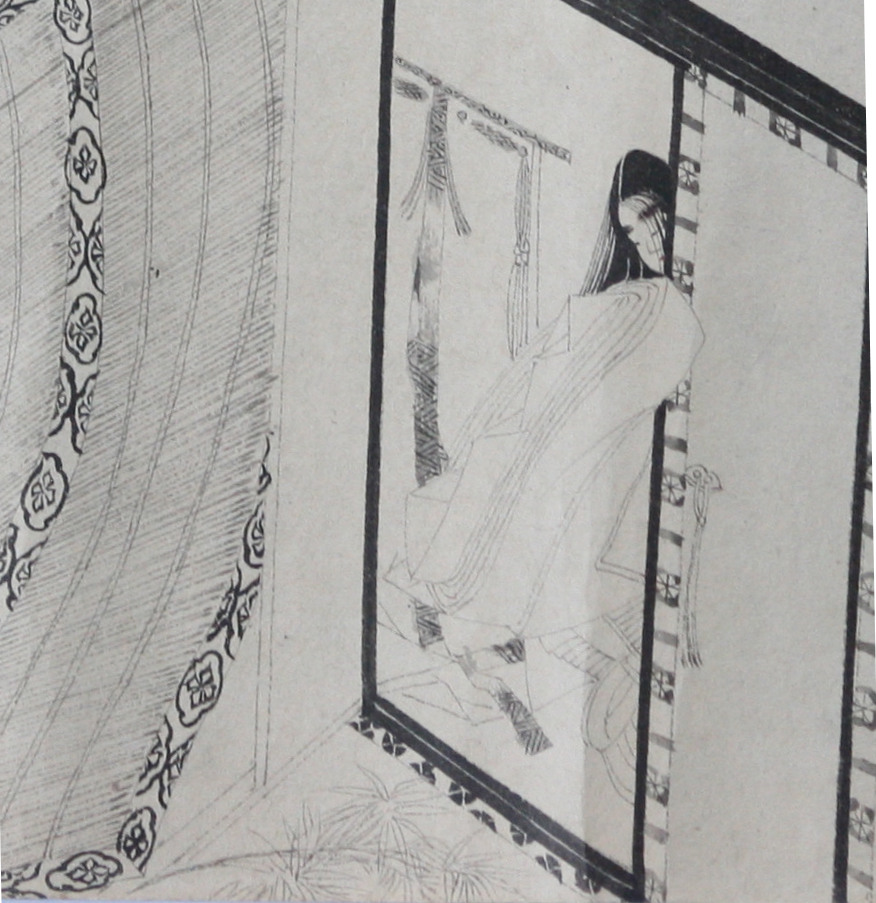
枕草子の作者 清少納言/出典:Wikipedia
『枕草子』という題名は、ざっくり言うと『枕』と『草子』にそれぞれの意味があります。『草子』に関しては、現代風に言い換えると『冊子』とか『本』といった意味なので分かりやすいのですが、意味が分からないは『枕』です。
この『枕』な何を指すのかというと、いつも寝る時に使っているあの『枕』です。でも、なぜ『枕』なのでしょうか?
枕草子執筆のキッカケと『枕』の意味
この『枕』には、清少納言が枕草子を書き始めたキッカケが関係しています。執筆のキッカケは、清少納言自身が枕草子に書き残しています。現代の言葉に置き換えて見て行きましょう。
ある日、定子(ていし、一条天皇の后で清少納言が仕えた女性)が、何も書かれていない真っ白な冊子を持っていました。定子は清少納言に問いかけます。
この冊子に何を書こうか迷っています。一条天皇のところでは史記(中国の歴史書)を書き写しているようですが・・。
すると清少納言がこう答えました。
それならば枕にしましょう!
よく意味がわからない回ですが(この後に解説します)、これが『枕草子』という題名のキッカケとなる清少納言と定子のやりとりです。
このやりとりの結果、定子は何も書かれていない冊子を清少納言に託し、その冊子に枕草子は書かれていくことになります。
これだけ見ると清少納言が頓珍漢なことを言って、会話が成立していない感じがしますが、これにはきちんとした意味があるのです。
気転の利いた清少納言の回答
実は、このやりとりの解釈には諸説あるのですが、一説には清少納言と定子だからこそ分かる知的な表現が含まれているとも言われています。
簡単にいうと、清少納言の回答は中国の詩人『白居易(はくきょい)』の詩文集『白氏文集(はくしもんじゅう)』にある一節『書を枕にして眠る』という一文を引用したものなのです。
『書を枕にして眠る』とはどういうことかというと・・・
枕は毎日寝る時に使う身近なもの。
そんな枕元にいつもこの冊子を置いておき、その日に気が付いたこと、感じたことを常に書き留めておくと良いですよ。
という意味になります。
これを定子の問いかけに照らしわせると・・・
ある日、定子(ていし、一条天皇の后で清少納言が仕えた女性)が、何も書かれていない真っ白な冊子を持っていました。
定子は清少納言に問いかけます。
この冊子に何を書こうか迷っています。一条天皇のところでは史記(中国の歴史書)を書き写しているようですが・・
すると清少納言がこう答えました。
枕元にいつもこの冊子を置いておき、その日に気が付いたこと、感じたことを常に書き留めておくと良いですよ!
となります。
定子は清少納言が言いたかったことを瞬時にくみ取り、機転の利いた回答に感心し『それならばぜひ清少納言に書いてもらいたい』となり、定子はその冊子を清少納言にプレゼントしたのです。
紙というのは、現代でこそ手軽に入手できますが、この時代はまだまだ貴重なものです。そんな貴重な紙を主の定子から賜ったことは、清少納言にとってはとても名誉なことであり、非常に嬉しいことでした。
このやりとりがキッカケとなり、清少納言は日々の宮廷での出来事、定子との想い出、嬉しかったことや気に入らなかったことを綴っていくことになります。
以上が『枕草子』という作品名の由来なのです。
清少納言と定子
この当時、漢詩は男性の教養とされていました。しかし、男性貴族が頻繁に出入りする宮廷にいた女性たちには、漢詩の教養が必要でした。もちろん、天皇に嫁いだ女性も漢詩に精通する必要があります。
一条天皇に嫁いだ定子、そして定子に仕え宮廷で働いていた清少納言。二人はともに漢詩の教養を持ち、普段のやり取りの中で知的なやり取りが行われ、それを楽しんでいました。
枕草子の中でも有名なエピソード『香炉峰の雪』にも、そんな環境が見て取れます。
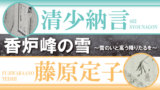
また、定子は天皇の后という高貴な立場ではあったのものの、少し軽いところがあったようで、ちょっとしたダジャレで周囲を和ませたりもしています。
こういった知的な女性たちが漢詩の知識を恥ずかしげもなく披露する環境、そして定子と清少納言が織りなす笑いに包まれた和やかな空間が、華やかな女性たちのサロンを形成していきました。
そして、男性貴族たちは居心地の良さを覚え、宮廷女性たちとの会話を楽しんでいました。
『枕草子』という作品名は、このような知的空間が生み出したものだったのです。
枕草子を読むと、清少納言がいかに定子を慕っていたかが分かります。また、定子が清少納言を信頼していたことも分かります。
そんな定子から、貴重な紙を賜ったことは、清少納言にとって大きな喜びであったことは想像に難くありません。そう考えると、二人の間に強固な信頼関係があったからこそ枕草子は誕生したと言えるのかもしれません。
定子は政争に巻き込まれ、失意の内に若くして亡くなります。なので、定子が枕草子を読んだかどうかは、よく分かっていません。ですが、枕草子には清少納言と定子の煌びやかな想い出がたくさん綴られています。
定子から賜った大事な紙に書いた定子との想い出。清少納言は、枕草子を定子に捧げるために書いていたのかもしれません。ここに、枕草子に秘めた清少納言の想いが隠されているような気がしてならないのです。
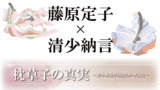
枕草子の由来まとめ
以上、枕草子の題名の意味でした。
- 『草子』は冊子とか本という意味。
- 『枕』は、中国の漢詩を元にした、清少納言と定子のやりとりの中から名付けられたもの。
だから『枕草子』という名前になりました。
枕草子に作品名に関しては、いろいろな説がありますが、結局のところよく分かっていないのですが、今回は筆者が最も支持している説をご紹介させて頂きました。
その他の枕草子に関する情報は、コチラをご覧ください。

最後までお読み頂きありがとうございました。
【参考にした主な書籍】
【初心者向けの枕草子】