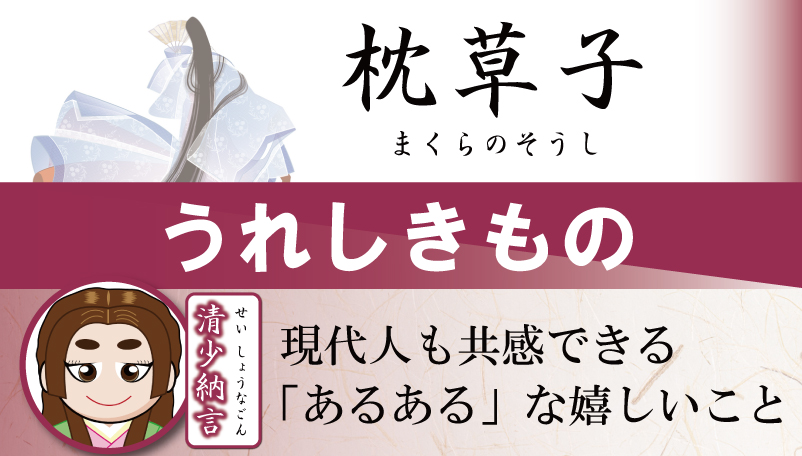枕草子『うれしきもの』。ここには、清少納言が感じた様々な幸せが列挙されています。
この記事では、そんな「うれしきもの」の中から、現代人でも同じように幸せを感じるものをピックアップしてご紹介します。当時の人々も現代人と変わらない喜びを感じていたことに、共感していただけるはずです。
清少納言のように、あなたも小さな喜びや幸せを大切にしながら、毎日を過ごしていただければ嬉しいです。
①物語の続きが読めた時は嬉しい
まだ見ぬ物語の一を見て、いみじうゆかしとのみ思ふが、残り見いでたる
現代風に言い換えるとこうなります。

初見の物語の1巻を読んで、続きが気になっていたところ、2巻を手に入れることが出来た時
最近でこそ、電子書籍なんかでマンガの続きとか、動画配信サービスで映画の続編をすぐに観ることができますが、千年前はそうは行きません。
電子書籍や動画配信サービスが登場する以前は、本屋に2巻を買いに行ったら売ってなかったとか、レンタルビデオ屋に行ったら続編がレンタル中だったとかで、なかなか続きが観られないなんてことは普通にあったものです。
そして、清少納言はこんなことも言っています。
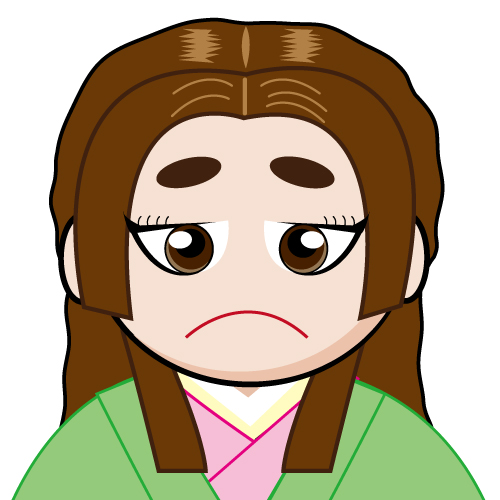
期待して続きを読んでみたけど、そこまで面白くないこともある
現在の映画でも、一作目を超える続編ってなかなか存在しなかったりしませんか?続編を観たけれど、ガッカリした経験がある方も多いのではないでしょうか。
これは現代でも感じる「あるある」ですね。
②尊敬している先輩からのメッセージが嬉しい
よき人の御前に人々あまたさぶらふをり、昔ありけることにもあれ、今きこしめし、世に言ひけることにもあれ、語らせたまふを、我に御覧じあはせてのたまはせたる、いとうれし
現代風に言い換えるとこうなります。

高貴な人の前に大勢が集まっている時、どんな内容であれ、自分の目をしっかり見てメッセージを伝えてくれた時は、とても嬉しい
これを現代に当てはめてみると、尊敬する会社の上司とか、憧れの先輩とかが、部下を集めて話している時に『自分に対してのメッセージを言ってくれているのかも』と感じた時のケースに近いのではないでしょうか。
目をかけてくれている先輩など、立場は自分より上で尊敬できる人からのメッセージ、しかも大勢に向けて話している中で自分に向けて発してくれたメッセージ。
やっぱり嬉しいものです。
清少納言の場合、彼女が仕えていた『定子』というお后様から、上記のような待遇を受けたことがあるのかもしれませんね。
③病気の人が回復した時は嬉しい
遠き所はさらなり、同じ都の内ながらも隔たりて、身にやむごとなく思ふ人のなやむを聞きて、いかにいかにと、おぼつかなきことを嘆くに、おこたりたるよし、消息聞くも、いとうれし
現代風に言い換えるとこうなります。

遠くにいても近くにいても、大切な人が病気だと聞いたのに見舞いにも行けずモヤモヤしている中で、回復したという話を聞いた時は、とても嬉しい。
今も昔も、大切な人が入院すれば心配するのは誰でも同じですし、例えば仕事なんかで手術後の見舞いにも行けなければ、心が落ち着かないのも同じです。
そんな中で手術が無時に成功したと言う報告を受ければ、やっぱり嬉しいものですね。
④好きな人が褒められた時は嬉しい
思ふ人の、人にほめられ、やむごとなき人などの、くちをしからぬものにおぼしのたまふ
現代風に言い換えるとこうなります。

好きな人が人に褒められ、さらに高貴な人が『彼(彼女)はしっかり者だ』と褒めてくれた時。
清少納言は宮廷に仕えていたので『高貴な人』と言っていますが、現代で当てはめるなら先輩とか上司とか『自分より立場が上の人が、好きな人を褒めてくれた時』と捉えて良いと思います。
自分が褒められるよりも、好きな人、彼氏、彼女が褒められた方が嬉しいっていう感覚も、なんとなく分かる気がします。
⑤探し物を見つけた時は嬉しい
とみにて求むる物、見いでたる
現代風に言い換えるとこうなります。

急に必要になった探し物を、すぐに見つけた時
これもよく分かりますね。
余談ですが、清少納言ってちょっと抜けてるところがあった節があり、他の章段にはこんな記述があります。
・誰かに呼ばれたと思って返事をしたら、自分が呼ばれたんじゃなかった
・裁縫の時に、糸のお尻を結ぶのを忘れた
・同じく裁縫の時、表と裏を逆に縫い合わせていた
誰にでもあることなのかなとも思うのですが、清少納言は片付けなんかも苦手で、よく無くし物をしていたのかもしれませんね。
⑥傲慢な人をギャフンと言わせた時は嬉しい
我はなど思ひてしたり顔なる人、はかり得たる
現代風に言い換えるとこうなります。

傲慢で偉そうにしている人をギャフンと言わせた時
これは、かなりスカッとするかもしれませんね。いつの時代も、傲慢な人はいたんですね。
嬉しかったことを素直に喜ぶ清少納言
以上、清少納言の『うれしきもの』でした。
枕草子では他にもいくつか挙げているのですが、今回は現代人でも共感できそうなものを選んで紹介しました。
枕草子からは、いつも明るい雰囲気が伝わってきます。
清少納言の明るい部分が全面に押し出されていて、今回扱った『うれしきもの』も、その明るい部分の一つです。
この明るさが枕草子の執筆方針であり真骨頂なのですが、その背景にはとても辛く苦しい現実があったことは、あまり知られていません。
なぜ枕草子が、これほどまでに明るく彩られているのか?その要因も記事にしてみましたので、コチラもぜひご覧になってみてください。
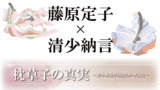
清少納言のように、日々の嬉しかったことに目を向けて生きていくことで、人生は幸せなものになっていくのかもしれませんね。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
↓さらにしっかりとした学びを手に入れたいあなたには、コチラがおすすめ↓
古文も日本史も学べる!中学生&高校生向け!通い放題、時間制限なしで勉強し放題の学習塾が登場。
①いつでもリアルタイム質問可能
②オンラインだから自宅で勉強可能
③どんなに利用しても定額制
↓詳しくはコチラ↓
【参考にした主な書籍】