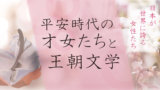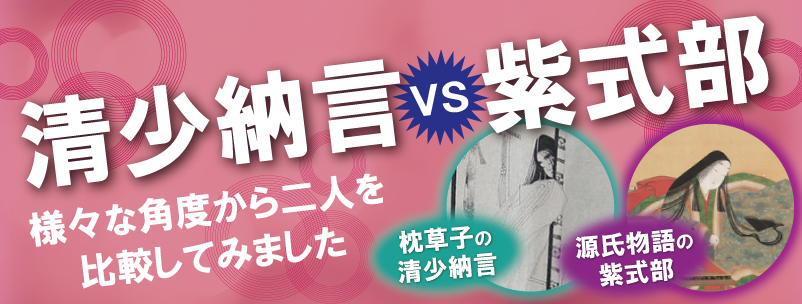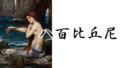枕草子の作者 清少納言。
枕草子には、清少納言が宮廷で華やかな毎日を送っていたことが記されていますが、彼女が宮廷を去った後は一体どうなったのでしょうか?
清少納言は后妃である『定子(ていし)』に仕えていました。しかし、定子が若くして亡くなってから程なくして女房を辞めたと言われています。長保3年(1001年)頃のことです。(定子崩御後も宮廷にいたという説もありますが、本記事では定説に従います)
宮仕えを辞めた後の清少納言については、ハッキリした記録がないのですが、断片的な逸話が伝わっています。意外と知られていない清少納言のその後。この記事では、清少納言が宮廷を去った後の動向や晩年についてご紹介します。
定子の埋葬地近くで静かに暮らした晩年
定子崩御をきっかけに宮仕えを辞めた清少納言は、再婚相手である『藤原棟世(ふじわらのむねよ)』の任国である摂津(現在の大阪北部あたり)に引っ越したと言われています。ですが、棟世は清少納言より20歳以上年上だったとされているので、晩年の清少納言は未亡人になっていたのではないでしょうか。
諸説あるものの、最終的には父親の『清原元輔(きよはらのもとすけ)』にゆかりのある京都の東山月輪という場所でひっそりと暮らしていたようです。実は東山月輪は、定子の埋葬地(京都市東山区今熊野泉山町にある鳥辺野陵)の近くと推定されています。
定子に対して誠心誠意お仕えしていた清少納言は、最後まで定子への哀悼の意を表していたのかもしれませんね。

定子が埋葬された鳥辺野陵(撮影:拓まろ)
赤染衛門の証言でわかる清少納言の晩年
清少納言と同時代の人物 『赤染衛門』の和歌に、宮廷を離れた清少納言の動向を詠んだ作品があります。
その和歌は以下の通りです。
元輔が昔住みける家の傍らに、清少納言住し頃、雪のつみしく降りて、隔ての垣もなく倒れて見わたされしに
跡もなく 雪ふるさとの 荒れたるを いづれ昔の 垣根とか見る
黄色のマーカーで示した箇所は「詞書(ことばがき)」と言われる部分で、和歌の前書きみたいなものです。この詞書の中に「清少納言」の名前が確認できます。
この和歌の意味は以下の通りです。
清原元輔(清少納言の父親)が昔住んでいた家のそばに清少納言が住んでいた頃、雪がひどく降って屋敷を仕切る囲いが倒れていたので知らせてあげました。
この赤染衛門の和歌が、清少納言が父親の住んでいた場所で暮らしていた根拠となっているのですが、その場所がどこだったかはハッキリしていません。
一説には、その場所が京都の東山月輪とされており、近くに泉涌寺(せんにゅうじ)というお寺があります。そして、泉涌寺には清少納言の供養塔や歌碑が残されているのです。

泉涌寺にある清少納言の歌碑(撮影:拓まろ)
清少納言と和泉式部の交流
宮仕えを辞めた後の清少納言は、和泉式部とも交流がありました。
和泉式部の和歌を集録した『和泉式部集』によると、引退した清少納言と和泉式部による数度の和歌のやりとりが確認できます。
稀にても 君が口より伝へずば 説きける法(のり)に いつかあふべき
この和歌は、引退した清少納言から海苔をプレゼントされた和泉式部からのお礼の返歌で、2人はそれなりの仲だったと見られています。
また、和泉式部の和歌には「稀にても」といった表現があることから、和泉式部は清少納言と気軽に会える状態ではなかったと推測できます。引退した清少納言は夫(藤原棟世)が赴任地である摂津国(せっつのくに)に同行していたため、和泉式部のいる京都からは離れていたのでしょう。
摂津国は現在の大阪府と兵庫県に跨るあたりで海に面しています。なので、宮廷を去った清少納言は一時、夫と一緒に摂津国の海沿いで暮らしていて、そこで採れた海苔を和泉式部にプレゼントしたのではないかと考えられているのです。
年老いても元気な清少納言
清少納言の晩年に関するエピソードもいくつか残っているのでご紹介します。
ある日、年老いた清少納言が暮らしていた庵の前を若者たちが通りかかりました。若者は『清少納言も落ちぶれたもんだ』と噂話をしています。
すると、庵から清少納言が飛び出してきて・・・
駿馬は骨でも価値がある!!
と怒鳴り散らしました。
清少納言の言っている意味が分からないかもしれませんが、要約すると『素晴らしい馬は骨になっても価値がある』という中国の故事に由来したセリフです。
つまり・・・
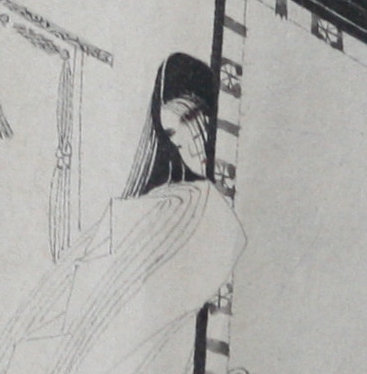
『年老いたからってバカにするんじゃないよ!』
という意味です。
この逸話が史実かは分かりませんが、枕草子からも伝わる気の強さと、中国の故事や漢詩に精通していた清少納言らしいエピソードだと感じますね。
たたっ斬られそうになった清少納言
さらにもうひ一つ、清少納言が晩年に経験した鬼気迫るエピソードをご紹介します。
清少納言には『清原致信(きよはらのむねのぶ)』という兄がいたのですが、清少納言が兄と一緒にいた時、突然刺客に襲われたのです。
この時、清少納言は出家していたため髪の毛が無く男と間違われてしまい、兄とともに斬り付けられそうになりました。
命の危険を感じた清少納言は下半身を露わにし、性器を見せつけ女性であることを証明。このとっさの判断により、清少納言は一命をとりとめたという伝説が残っています。
この事件は、寛仁元年(1017年)頃の出来事とされており、斬られた兄の致信は亡くなっています。清少納言も危なかったのですが、とっさの機転で何とか切り抜けたのでした。
清少納言の晩年は落ちぶれていたのか?
一説によると、晩年の清少納言は落ちぶれていたと言われています。
ここからは筆者の想像も含まれるのですが、確かに裕福な生活はしていなかったでしょう。しかし、個人的にはそこまで落ちぶれていたわけではなかっと思っています。
歴史的に見れば、清少納言は敗者です。清少納言が仕えた定子とその一族は没落し、立場的にライバルだった藤原道長が権力を手にしたからです。
定子と清少納言の没落の件に関しては↓コチラ↓の記事で詳しく解説しています。
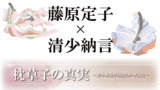
ですが、藤原道長が権力を握った後に、清少納言の娘『小馬命婦(こまのみょうぶ)』が彰子(定子の後を継いだ道長の娘)に仕えています。
また、清少納言自身も、彰子に仕えていた『和泉式部(いずみしきぶ)』や『赤染衛門(あかぞめえもん)』とも交流がありました。
清少納言は定子の女房でしたから、藤原道長からしてみたら後ろめたい存在ではあったはず。ですが、娘(小馬命婦)が彰子に仕えたり、彰子の女房(赤染衛門や和泉式部)たちと交流があったりと、清少納言と宮廷との縁が切れたわけではなかったようです。
なので、宮仕えを辞めた後も静かに暮らしていただけのように感じます。
また、清少納言は枕草子の中でこんなことを言っています。
『女性が一人暮らしをする場所は、ちょっと草が生えているような質素な感じが良い』
きっと自身が理想とする環境で、質素に暮らしていたのではないでしょうか?
宮廷とは正反対な静かな庵で・・・
春のあけぼのに趣を感じながら・・・
定子の埋葬地近くで・・・
定子を弔いながら・・・
ひっそりと余生を送っていた。
それが清少納言の晩年なのかなと思っています。
清少納言の晩年まとめ
以上、清少納言の晩年についてでした。
清少納言が宮仕えを辞めた後の逸話は、ほとんどが伝説の類でハッキリはしていません。彼女のお墓も全国にあります。ですが、定子を慕っていた彼女のことを考えると、やっぱり定子の近くで最期を迎えたのかなと想像してしまいます。
決して落ちぶれたわけではなく、定子を弔いながら静かな余生を過ごしていたのではないでしょうか。
清少納言と枕草子の情報を家系図や年表を交え、わかりやすくまとめました。ここを読んでおけば、清少納言のことはほぼわかる内容になっています。じっくり知りたい方はぜひコチラをご覧になってみてください。

最後までお読みいただきありがとうございました。
【参考にした主な書籍】
清少納言だけじゃない!平安時代に活躍した才女たちの情報はコチラから。