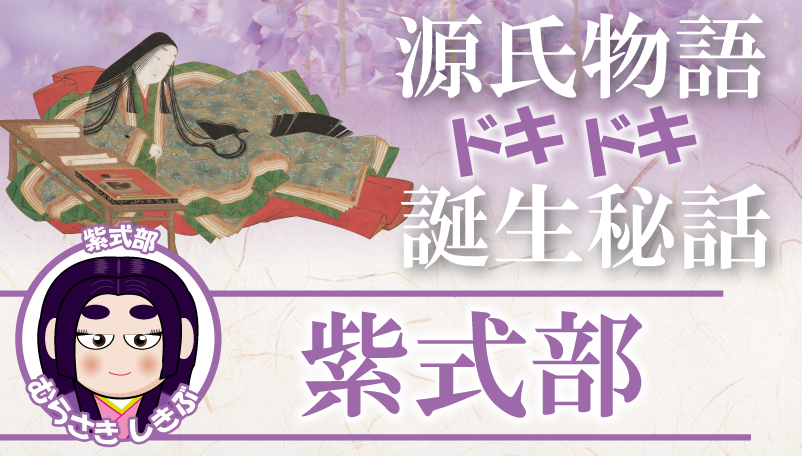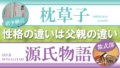今からおよそ千年前に書かれた源氏物語。
千年経った今でも、毎年のように翻訳されたりマンガになったりして、新しい出版物が刊行されるほどの人気を誇る文学作品です。
ところで・・・
今では様々な言語に翻訳され世界中の人々に愛される、世界最古の女流長編小説『源氏物語』。そんな源氏物語の誕生秘話をお届けします。
源氏物語の執筆動機は音声でも解説しています。本文を読むのが面倒な方や、他のことをしながら聴き流したい方はぜひご活用ください。
源氏物語の執筆動機

紫式部/Wikipediaより
実は、源氏物語は紫式部が宮廷出仕を始める前から書き始められています。
源氏物語が書かれた理由に関しては、不明な点も多く様々な説がありますが、よく言われる説としては、
だったと言われています。
また、紫式部には読んだ物語について語らう友人もおり、もともと物語に興味があったようです。
ゆえに、物語の世界に没頭することで、現実の不安を和らげていたのかもしれません。
一説によると、最初は『枡型本(ますがたぼん)』と言われるものに書き始めたと言われています。
なお、当時の紙はとても貴重なものだったので、そう簡単には手に入りませんでした。
最初は書きあげた物語を友人などに読んでもらうような、趣味の一環として書いたようです。
源氏物語と言えば、とんでもない長編作品ですが、最初は『空蝉編』『夕顔編』のように、読切作品のような形で書いていたと考えられています。
評判になっていく源氏物語
以上のような感じで書いている内に、源氏物語は面白い物語という徐々に評判となっていきます。
やがて、源氏物語の評判は「藤原道長」の耳にも入り、紫式部は宮廷へと引っ張り出される形になったのです。一説には、道長の正妻「倫子」の影響もあったとされています。

源氏物語を書くような才女を、ぜひとも我が娘に仕えさせたい。帝(一条天皇)もお好きな源氏物語の作者を召し抱えれば、帝も彰子(道長の娘)の元へ通うようになるかもしれん。
こうして紫式部は藤原道長の娘「彰子」の女房として、宮廷で働くことになったのでした。
実は、紫式部が宮廷で働くようになる理由は、源氏物語の評判があったからなのです。
藤原道長が源氏物語のスポンサーになっていたのは有名な話ですが、それはずっとずっと後のことだになります。
なお、紫式部は宮廷出仕にあまり乗り気ではなかったようで、出仕して間もなく実家へ逃げ帰るという事件を起こしています。紫式部が体験した現代でも起こり得る「とある出来事」とは?
興味のある方は↓コチラ↓の記事もご覧になってみてください。

豪華な本に仕立て上げられる源氏物語
紫式部は源氏物語とは別にもう一つ『紫式部日記』という文学作品を残しており、この日記に、源氏物語が豪華な冊子に仕立て上げられる様子が書かれています。
紫式部はこの作業の指揮を任されていたようで、
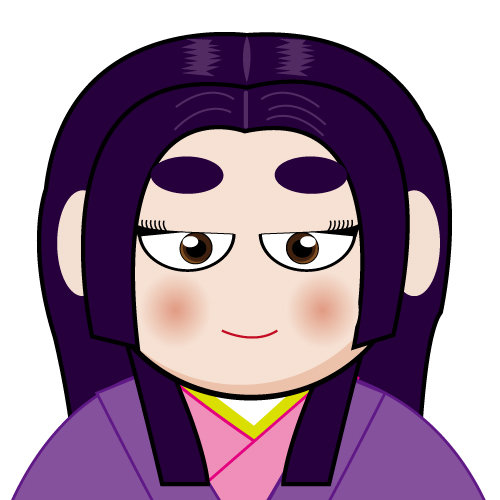
夜が明けると真っ先に編集作業にあたります。
色とりどりの用紙を選び、原稿を添え、清書の依頼状と一緒にあちらこちらに配るのです。
それと同時に、清書が完了したページを綴じ、整えていきます。
といった感じで、その過程を伝えてくれます。
このような、源氏物語の冊子づくりを発案したのは彰子でした。
この時、彰子をはじめ、紫式部たち女房は里帰りをしており、間もなく御所に戻るというタイミングでした。
なので、御所へ戻るための準備で大忙しの中で、源氏物語の編集作業は行われていたのです。
なぜ、こんなタイミングで彰子は冊子作りを命じたのかはハッキリしていませんが、一説には「一条天皇(彰子の夫)への里帰りのお土産」だったのではとも言われています。
一条天皇も源氏物語の一部を嗜み、感心していたことが紫式部日記に書かれているので、製本したものを一緒に楽しみたいと言う意図があったのかもしれませんね。
この時に編集された冊子が、いわゆる源氏物語の豪華本として知られるものとなっています。
※現存はしていない
ちなみに、綺麗に飾られ新しくなった源氏物語を見て、紫式部は日記の中でこう漏らしています。

試しに物語を手に取ってみましたが、昔のような感じがしない・・私は呆然としました・・
書き始めた頃は、物語好きな友人たちと見せ合って楽しんでいた源氏物語。
しかし、紫式部は宮仕えを始め、自身の立場も、付き合う人たちも、当時とは大きく変わってしまいました。
書き始めた頃とは環境が大きく変わってしまったことで、昔のような感動が得られなくなってしまったようです。
源氏物語の原本をパクった藤原道長
なお、源氏物語の豪華本を編集していく最中、下書きが持ち出されるという珍事が起こっています。
原稿を持って行ってしまったのは藤原道長でした。
この下書きを修正したものが、清書される段取りだったようなのですが、意図せず原稿が持ち去られてしまったために、紫式部は

不完全な草稿が世に出回ってしまい、残念な評価を受けてしまうかもしれません・・・
と悲しんでいます。
源氏物語はいつ頃書かれ、いつ完成したのか?
最後に源氏物語がいつ書かれ、いつ完成したのかをお伝えします。
これについてもハッキリしたことは分かっていないのですが、源氏物語の完成時期は西暦1008年頃とされています。
紫式部が宮廷出仕を始めたのが1006年頃と言われているので、宮廷出仕してから約2年くらいで完成したようです。
では書き始められたのがいつ頃なのでしょうか?
一般的には、夫が没した半年後に書き始めたと言われています。
その夫は『藤原宣孝』という人物、そして宣孝が無くなったのが1001年。
なので、
ということになります。
源氏物語の文字数は、現代の一般的な400字詰めの原稿用紙で2400枚くらいなので、執筆から完成までの約7年(2555日)で平均すると、だいたい1日に原稿用紙1枚弱くらいのペースで書いていた計算になります。
まぁ、あくまで平均なので、いっぱい書いたり全然書かなったりした日もあったと思いますが。
源氏物語は石山寺(滋賀県大津市)で執筆された?
源氏物語執筆には、ひとつの伝説があるのではこちらにも触れてみましょう。
一説によると、紫式部が源氏物語を執筆した場所は、滋賀県大津市にある石山寺だという伝説があります。
ただ、石山寺の伝説はあくまで伝説であって、事実とは異なるというのが一般的な説となっています。
しかしながら、こういった伝説が残っているということ自体、昔から源氏物語が広く愛されてきたことの証明です。
史実じゃないと切り捨てるのは簡単ですが、なぜそうった伝説が生まれ、伝承されているのか?という部分を突き詰めて見るのも、歴史を知る楽しみなのかな感じます。
源氏物語の人気
紫式部が宮廷に出仕してからも、源氏物語を書き続けました。
その背景には藤原道長というスポンサーがあったためと考えられています。
そんな源氏物語は、紫式部の主君である彰子、そして彰子の夫てもある一条天皇も認める作品でした。
一条天皇と彰子。
日本のトップに君臨する天皇夫妻も読んでいる源氏物語は、豪華な冊子に編集されたのは、すでにお伝えした通りです。
そして、源氏物語を媒介とし、一条天皇と彰子は仲を深めていきました。
最初は、紫式部が夫を亡くした悲しみを紛らわすために書いていた源氏物語。
そんな源氏物語は評判となり、藤原道長の後ろ盾を得て、書き続けられました。
その結果、日本のトップである一条天皇と彰子にも認められる作品となり、豪華に編集されました。
こういった時代背景の元、源氏物語は人気作品となっていったのです。
紫式部、藤原道長、彰子、一条天皇。
これは想像ですが、もしこの4人が同時代に揃わなければ、源氏物語は歴史の表舞台には登場しなかったかもしれません。
そう考えると、奇跡的なことだとも思いますし、紫式部と源氏物語を引っ張り上げた藤原道長の功績は大きいのかもしれませんね。
源氏物語の執筆理由まとめ
以上、紫式部が源氏物語を書いた理由と、書かれた時代でした。
書き始めた理由は、
とされています。
そんな個人的な動機から書き始められた源氏物語は、その後も藤原道長や一条天皇、彰子の力を得て、どんどん書き進められていき、豪華な冊子となりました。
そして、千年と言う長い年月を経て、現代まで読み継がれています。
個人的には、紫式部が源氏物語を書き続けられた原動力のひとつには、やっぱり書くことが好きだったという部分もあるのかもしれないと感じます。
そんな源氏物語を、あなたもぜひ楽しんでみてください。

その他にも、平安時代の女性たちによる王朝文学、そして個性豊かな女性たち、そんな平安時代の文学作品や女性たちに関してたくさん執筆していますので、↓コチラ↓からぜひご覧になってみてください。
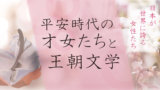
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
【参考にした主な書籍】