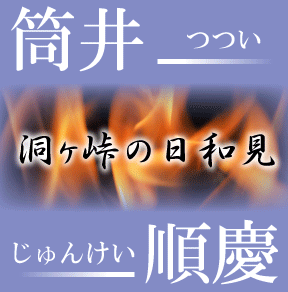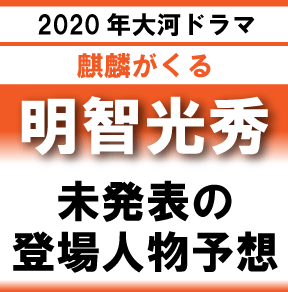ご来訪ありがとうございます。
拓麻呂です。
日本の歴史を大きく変えた『本能寺の変』。
そして、変の首謀者『明智光秀』と、信長の弔い合戦と意気込む『羽柴秀吉』が激突した『山崎の戦い』。
本能寺の変後から山崎の戦いで敗れるまでを、光秀を揶揄して『三日天下』と呼びますが、実際は約11日間に及び、双方の思惑が入り混じったドラマが存在しています。
本能寺の変から山崎の戦いまで、いったいどのように推移していったのか?
その経過を時系列で追いかけてみたいと思います。
本能寺の変から山崎の戦いへ
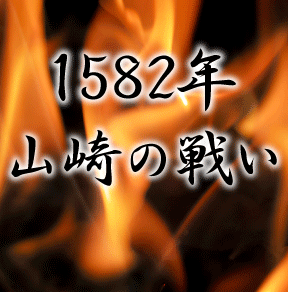
【本能寺の変】6月2日
天正10年(1582)6月2日、歴史を大きく揺るがす大事件『本能寺の変』が発生。
明智光秀の謀反により、織田信長が炎上する本能寺にて自刃。
次いで、徹底抗戦を挑んだ信長の嫡男『織田信忠』が、二条御所にて自刃。
これにより、歴史の行く末を左右する激動の11日間が始まります。
【秀吉、信長自害を知る】6月3日
本能寺の変が起きた翌日、中国地方の毛利氏と対峙していた羽柴秀吉の元に、変の一報が入ります。
現在の岡山県にある備中高松城(びっちゅうたかまつじょう)を包囲中だった秀吉は、急遽毛利氏との和平交渉を開始。
6月4日には、高松城の城将 清水宗治の切腹によって講和が成立し、秀吉軍は撤退準備に入ります。
【光秀、安土城を占拠】6月5日
本能寺の変の後、信長の居城であった安土城に光秀が入城。
無人になっていた安土城を拠点に、長浜城や佐和山城など、近江(おうみ、現在の滋賀県)の諸城を攻略。
光秀が近江の大半を支配下におきました。
【中国大返し】6月6日
毛利氏との和議をまとめた秀吉は、弔い合戦のため京都に向けて進軍を開始。
これより世に名高い『中国大返し』が始まります。
秀吉は道中、『信長が無事である』という情報操作を行い、周辺諸将の混乱を抑えながら京都を目指します。
この時の毛利家の動きは、コチラの記事をご覧ください。
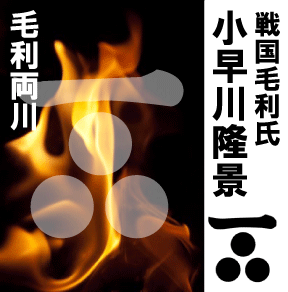
【光秀が朝廷と接触】6月7日
吉田神社の神主 吉田兼見が朝廷の使者として光秀と接触。
朝廷からは『京都のことは支障のないように』という意向を伝えられ、さらに贈答品を賜った後、光秀は居城の坂本城へと移動。
安土城の守りは、側近の明智秀満は担う。
【秀吉が姫路城で休憩】6月8日
怒涛の勢いで京都を目指していた秀吉軍は、道中の姫路城で休憩。
全軍に明智光秀討伐を告げ、食料や金銀を惜しみなく与えるなどして、士気を鼓舞。
【光秀、細川幽斎の説得に失敗】6月9日
光秀は入京し、吉田兼見の自宅を訪問。
また、旧知の仲である細川幽斎が味方するだろうと目論んでいた光秀に逆風が吹き始めます。
幽斎は、信長の喪に服することを理由に中立の立場をとってしまい、結果、説得に失敗。
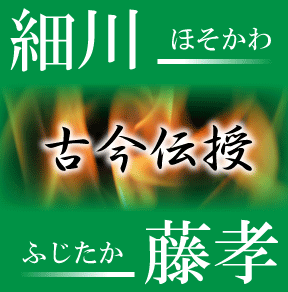
【光秀、筒井順慶の説得にも失敗】6月10日
細川幽斎と同じく、光秀が加勢を期待していた筒井順慶からも見放されます。
順慶は『洞ヶ峠の日和見』と言われる中立の立場をとります。

【光秀、勝龍寺城に入場】6月11日
想像以上の速さで京都に迫る秀吉。
その報を受けた光秀が、秀吉迎撃のため進軍、勝龍寺城に入城。
【秀吉、天王山を制す】6月12日
摂津(せっつ、現在の大阪府と兵庫県の間の辺り)まで戻ってきた秀吉が、重要拠点となる『天王山』を占拠。
これにより、京都への進軍ルートを確保。
現在、勝負どころとなるターニングポイントを【天王山】というのは、この時の出来事に由来しています。
【激突!山崎の戦い】6月13日
天正10年6月13日、両軍が決戦の地 山崎に布陣。
戦いの火ぶたが切って落とされました。
明智光秀軍1万5千、羽柴秀吉軍3万5千。
細川幽斎や筒井順慶らの協力を得られなかった光秀に対し、中国大返しの道中で諸将を味方に付けていた秀吉。
その兵力差は歴然でした。
序盤は善戦するも、兵力差は如何ともしがたく、明智軍は壊滅。
敗走を開始しました。
【光秀自刃】6月14日
山崎の戦いで敗れた光秀は再起を図り居城の坂本城を目指すも、途中の小栗栖(おぐるす)をいう場所で落ち武者狩りに襲われ負傷。
自らの命運を悟った光秀は自刃。
本能寺の変からわずか11日後の出来事でした。
秀吉の勝因と光秀の敗因
結局のところ、光秀の敗因は盟友の細川幽斎や筒井順慶を味方にできなかったことが影響しているのかなと感じます。
高山右近や中川清秀といった武将にも声をかけていたのですが、彼らも光秀には応じませんでした。
それどころか、秀吉に味方しています。
秀吉は、中国大返しの道中で、諸将に書状を出し味方を増やした上で、山崎の戦いに臨んでいます。
やはり、この差は多きかったと言わざるを得ないでしょう。
諸説ありますが、秀吉の帰還速度も勝因のひとつでしょう。
一連の流れの中で光秀と接触のあった吉田兼見は、自身の日記で光秀の最後を記録しています。
醍醐で一揆勢に討ち取られた。
首と胴体は本能寺で晒されたらしい。
大事件を起こした本能寺に戻って、晒し首になった光秀。
この記述の通りだとするならば、なんとも皮肉なものです。
まとめ
以上、本能寺の変から山崎の戦いまでの経緯でした。
わずか11日間の中に、日本の歴史を大転換期が詰め込まれいます。
この11日間が、その後の戦国時代の流れを決定づけ、日本の歴史にも影響を与えていると言っても過言ではないと考えています。
他の明智光秀関連の記事はコチラになります。
1582年本能寺の変。歴史をひっくり返したこの大事件の裏には人間 明智光秀の悲しき感情が隠されています。そんな光秀の心に迫ります。
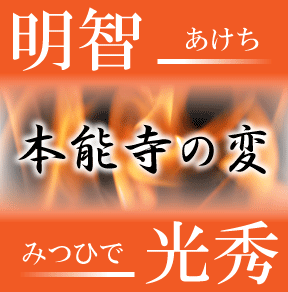
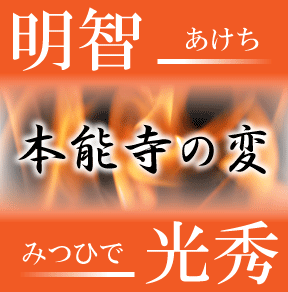
旧勢力の権威を重んじた実直な男というイメージが強い『明智光秀』。ところが本当の光秀の人物像は全然違ったものでした。

明智光秀は山崎の戦の後に亡くなっておらず、生き延びて天海という僧侶になったという説があります。その真偽を、歴史的背景から紐解いてみたいと思います。
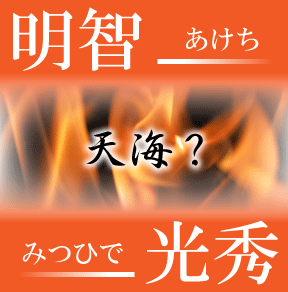
明智光秀を陰で支えた『妻木煕子』。光秀の妻として彼を支えた心温まる夫婦仲、そして現在の光秀のイメージにも大きな影響をあたえつづける煕子の存在。そんな光秀と煕子のエピソードをお伝えします。

信長の正妻『濃姫』と明智光秀は恋仲だったのでしょうか?二人の本当の関係に迫ります。
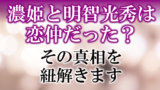
では、今回はこの辺で!
ありがとうございました。