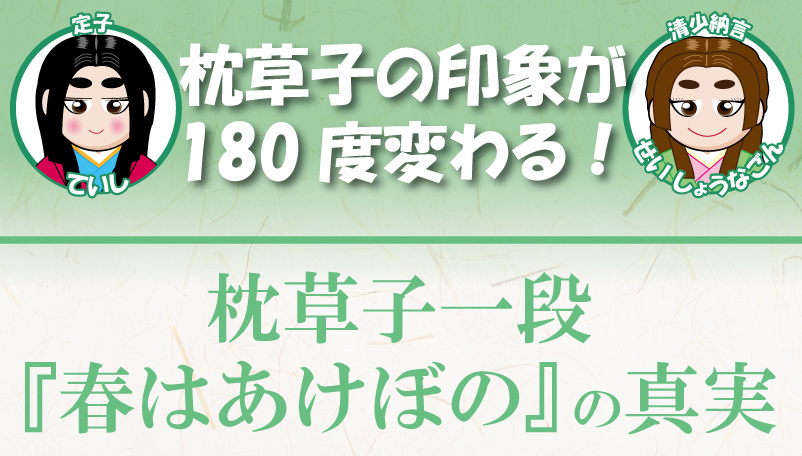枕草子の冒頭部分。

春はあけぼの やうやう白くなりゆ山ぎは すこし明かりて 紫だちたる雲のほそくたなびきたる
中学や高校時代の授業で聞いたことのあるフレーズではないでしょうか?
ですが授業などでは、その意味などを学ぶだけで、作者の清少納言が「春はあけぼの~」に込めた意図までは教えていないのではないかと思います。
この記事では、清少納言が枕草子冒頭の「春はあけぼの~」に込めた想い、そして「春はあけぼの~」の真実をお届けします。
結論から言ってしまうと、「春はあけぼの~」には、清少納言が「定子」という女性に対して込めたある想いと、悲しい現実が秘められています。
その詳細をお伝えするには、事前に把握しておかなければならないことがあるので、順を追って解説していきます。
早く真実を知りたい方は、下記の目次からお目当ての部分に飛べますので、ぜひご活用ください。
あなたがこの記事を読み終わる頃には、枕草子や清少納言に対する印象が180度変わっていることでしょう。
「春はあけぼの」の現代語訳
ということで、まずは「春はあけぼの~」の現代語訳を把握しておきましょう。
【原文】
春はあけぼの やうやう白くなりゆ山ぎは すこし明かりて 紫だちたる雲のほそくたなびきたる
現代語訳は以下のようになります。

春と言えば夜明けが好き。辺りが次第に白み始め、遠くに見える山の輪郭が少しだけ明るくなり始める。その周りには紫がかった細い雲がたなびいている。
おおよそ、このような意味になります。
では、「春はあけぼの~」の意味を把握したところで、いよいよ真実の核心に迫ってまいります。
まずは、冒頭で触れた「定子」という女性と清少納言の関わりについて見て行きましょう。
清少納言と藤原定子
定子と清少納言の関係は主従関係です。
清少納言は定子に仕える女房(高貴な人物に仕える女性のこと)でした。
定子は藤原道隆という人物の娘で、一条天皇の中宮(お后様のこと)でした。
藤原道隆は関白(天皇を補佐するNo.2的なポジション)で、当時の宮廷で絶大な力を持っていました。
そんな実力者の娘が定子で、その定子に仕えていたのが清少納言だったのです。
定子と清少納言は主従関係ではあったものの、強い信頼関係で結ばれており、枕草子の中には定子を賛美する記述がたくさん出てきます。
また、枕草子を執筆した紙は定子から賜ったもので、執筆の動機にも大きく関わっているのです。
実は、とある出来事(詳しくは後述)がキッカケで、清少納言は宮廷から離れて里帰りをしてた時期があるのですが、その時に定子から貰った紙に思いつくことをツラツラを書き始めました。
これが後に枕草子となります。
枕草子の執筆動機にかんしては↓コチラ↓の記事でも詳しく解説しています。

次に「春はあけぼの」を清少納言が書いた時の状況や、時代背景を見て行きましょう。
枕草子が書かれた時の状況
枕草子を書いていたタイミングは、清少納言と定子にとって強烈な逆風が吹いている時期でした。
前述の藤原道隆(定子の父親)が急逝したため、定子を含む藤原道隆の一族(中関白家)の栄華は衰え、変わって藤原道長が台頭してきました。
父の急逝だけでなく、兄(藤原伊周)と弟(藤原隆家)も、長徳の変と呼ばれる大事件の責任を問われ左遷されてしまいます。

さらには実家の焼失、母(高階貴子)の逝去なども重なり、定子はかなり苦しい状況に立たされました。
このような事件が起こる中、周囲から藤原道長との内通を疑われた清少納言は里へ帰り、この時に定子から賜った紙に、思いついたことを色々と書き連ね始めました。
これが枕草子の原型になるのです。
ザックリですが、以上が枕草子は書き始められた背景になります。
なお、この時の詳細は以下の記事で詳しく解説しています。
より深く理解できるので、ぜひ一度目を通して頂けると幸いです。
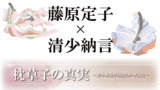
定子の苦境が書かれていない枕草子
以上のような状況で書き始められた枕草子。
枕草子には、定子との想い出や定子が輝いていた頃の出来事がたくさん書かれています。
ですが、苦境に立たされた定子の姿は書かれていません。
定子が一番苦しかった時期に書かれていたにも関わらず。
なぜでしょうか?
そこには、枕草子の執筆方針が大きく影響しています。
枕草子は、苦しい中でも前向きに生きた定子と、定子を中心とした笑顔に包まれる定子サロンの姿だけを綴っているのです。
その明るさは、定子が最も輝いていた時から変わらない定子サロンの姿でした。
例え苦しい状況だとしても、笑顔と知的な空間を是とする定子と清少納言、そして定子に仕えた女房たち。
そんな定子サロンの姿を伝えるため、あるいは定子自身を勇気づけるため。
苦しい状況でも前向きに、決して後ろは振り向かない。
だからこそ、枕草子に登場する定子や清少納言ら女房たちは、よく笑い、そして風流なやりとりをしているのです。
こうした執筆方針で綴られた枕草子は、もともとは定子が持っていた紙に書かれたものであり、定子の意向で清少納言に執筆を託しています。
ゆえにおそらく清少納言は、定子に見せるために書いていたという側面もあったことでしょう。
苦境に立たされた定子を勇気づけたい、笑顔で包まれる定子サロンの生き様を伝えたい。
こうした清少納言の想いが、枕草子のトップを飾る「春はあけぼの」の込められています。
その想いを込めた「春はあけぼの」には、どのような意味が込められているのでしょうか?
ここまでのまとめ
ちょっと長くなってしまいましたが、ここまでを簡単にまとめます。
春と言えば夜明けが好き。辺りが次第に白み始め、遠くに見える山の輪郭が少しだけ明るくなり始める。その周りには紫がかった細い雲がたなびいている。
となります。
それでは、いよいよ「春はあけぼの」の真実に迫っていきましょう。
清少納言が「春はあけぼの」に込めた真実

春はあけぼの やうやう白くなりゆ山ぎは すこし明かりて 紫だちたる雲のほそくたなびきたる
この有名な枕草子の有名な冒頭部分は、おおよそ以下のような意味になります。
春と言えば夜明けが好き。辺りが次第に白み始め、遠くに見える山の輪郭が少しだけ明るくなり始める。その周りには紫がかった細い雲がたなびいている。
このように、清少納言は「春」の好きな情景を「明け方」としました。
真っ暗な夜から日が昇り始め、まさに光明が差し始めた一瞬をとらえた情景。
また「紫だちたる雲」、いわゆる紫雲は「めでたいことが起きる兆し」としての意味を持っていると言われています。
まさに、暗く先の見えない状況にあった定子の将来を明るく照らすかのような表現、明けない闇は無いと勇気づけるかのような表現、これこそが枕草子冒頭に込められた意味ではないかと感じるのです。
また、「春」から連想するものとして、多くの場合は「桜」などを思い浮かべると思います。
しかし、清少納言は「明け方」を選びました。
「春」から「明け方」を連想する人は決して多くはないでしょう。
紫式部は自身の日記(紫式部日記)で、清少納言をこう評しています。

清少納言のように、好んで人と違っていたいと思っている人は、最初は面白がられてもやがて飽きられ、その行く末は異様なものになることでしょう。(一部抜粋)
「好んで人と違っていたい」
まさに「桜」などの普遍的な表現ではなく、あえて「明け方」を選ぶような清少納言の感性を言っているのではないでしょうか。
さらに、清少納言は「夏」は「夜」、「秋」は「夕暮れ」、冬は「早朝」と、これらも普通とは異なる情景に美を見出しています。
多くの場合、夏は「海」、「秋」は「紅葉」、「冬」は「雪」などを思い浮かべるのではないでしょうか?
しかし、清少納言は人とは違う感性で、枕草子の一段を書きあげました。
この人とは違った気風こそ、定子サロンが是としたものでした。
枕草子の中の「清涼殿の丑寅の隅の」や「雪のいと高う降りたるを」といった章段では、定子の問いに対し、一風変わった気の利いた回答を求める定子の姿、そしてそれに応える清少納言の姿が描かれています。
「人とは違う」回答を望む定子と、それに応える清少納言。
そして、「明け方」や「紫きだちたる雲」に込めた、定子への想い。
枕草子の開幕を飾る「春はあけぼの」こそ、まさしく定子サロンの気風を前面に押し出しつつ、定子の未来を明るく照らさんとする願いを込めて書かれていたのです。
もちろん、枕草子の中で清少納言が名言しているわけではありません。
ですが、枕草子が書かれ背景などを鑑みると、私にはそう思えてならないのです。
「春はあけぼの」の真実まとめ
以上、春はあけぼのの真実についてでした。
学校の授業では、「春はあけぼの」の意味を理解することはできますが、その背景まではなかなか語られません。
ですが、こうした背景を理解しつつ考えてみると、歴史や偉人に対する興味や楽しみ、そして理解も深まるのではないでしょうか?
以下のリンクでは、枕草子に関するいろいろな情報を扱っていますので、ぜひお楽しみ頂ければ幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。
【参考にした主な書籍】